円高・円安要因のバランス
2017年12月28日
住友商事グローバルリサーチ 経済部
鈴木 将之
概要
2017年を振り返ると、円ドルレートは約10円の幅を変動し、年初の円安水準を回復していない。実質金利差やマネタリーベース、購買力平価など、為替レートの決定要因をみると、必ずしも円安に振れてこなかった原因が読み取れる。先行きについては、検討した要因から、一方的な方向に進む環境になりにくいと考えられ、これから半年程度の間、足もとの為替レート±5円程度のレンジで推移するとみられる。
1. 年初からみると円高ドル安に
図表①のように、2017年の年始に1ドル=117.99円だった円ドルレートは、9月に107円台まで円高が進んだものの、11月末には112.29円まで戻しており、年間の振れ幅は約10円であった。
この間、FRBは12月までに、事前の予想通りに3回利上げを実施し、10月にはバランスシートの縮小にも踏み切った。その一方で、日本銀行は、実質的に国債買い入れを減額してきたものの、長短金利操作付き量的・質的金融緩和(YCC)によって緩和姿勢を演出してきた。このように、日米で金融政策の方向性が異なっている中でも、年始の円安水準には戻っていない。
先行きについても、引き続き国内外の金融政策の方向性は異なるとみられる。米国では、2018年も3回程度の利上げが見込まれている。そのため、もう一段円安が進みそうだが、必ずしもそうとは言えない要因もある。そこで、以下では、為替レートに関係する要因を検討してみる。
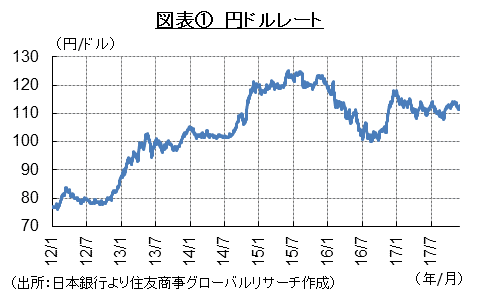
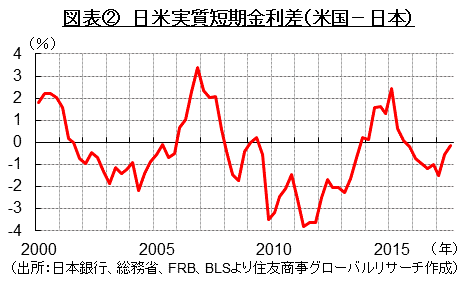
2. 為替レートの決定要因の検討
まず、短期的には、為替レートは金利差の影響を受けやすいことが知られている。日米の実質短期金利の動きをみると、図表②のように、日米金利差は2017年第1四半期を底に足もとにかけてマイナス幅を縮小してきた様子がうかがえる。
米国では、緩やかに利上げを行ってきたものの、それ以上に物価が上昇しており、実 質短期金利はマイナス圏を推移していた。しかも、その水準は、日本の実質金利を下回るものだった。日本でも、マイナス金利の導入によって名目短期金利はマイナス圏にあった一方で、物価上昇率が低いため、実質でみると米国よりも高い金利だった。名目の金利差では米国の金利の方が日本よりも高いことから、円安圧力に振れやすくみえるのに対して、実質では反対に円高圧力であった可能性がある。ただし、その状況は徐々に変化しており、年末にかけて円高圧力が弱まってきている。
次に、中期的に影響を及ぼすとされる金融政策について、代表的な指標であるマネタリーベースを比べてみる。図表③のように、米国では量的緩和政策が終了しているため、マネタリーベースは頭打ちになっている一方で、日本は金融緩和を続けており、マネタリーベース比は上昇している。2016年9月の長短金利操作付き量的・質的金融緩和(YCC)を導入してから、政策のターゲットが「量」から「金利」に変わったこともあり、量の拡大ペースが鈍化したものの、拡大傾向に変わりない。そのため、日米のマネタリーベース比の拡大によって、中期的には円安圧力が高まってきたとみられる。
長期的なトレンドとしては、相対的な物価上昇率の相違に基づく購買力平価(PPP)の動きが重要になる。図表④のように、量的・質的金融緩和(QQE)への期待が高まった時期に、円安による輸入物価を通じた物価上昇によって、1973年を基準にしたPPPは底を打った。それまでの、事実上の下限となってきた輸出デフレータに基づくPPPに沿うような動きから、上限となってきた消費者物価指数に基づくPPPに接近した。多少の揺り戻しはあるものの、PPPから見ると、約30年ぶりの円安圧力がかかっているといえる。
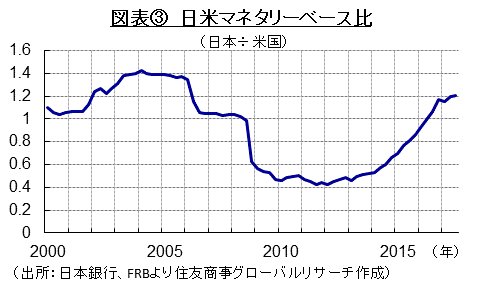
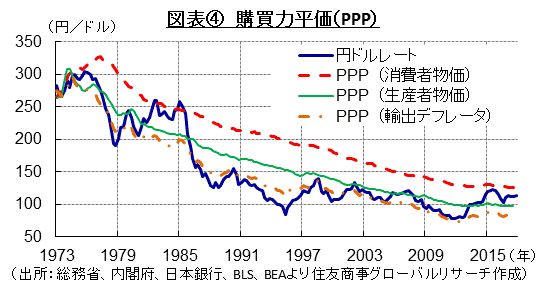
3. 金融政策の影響が大
円ドルレートの変動について、上記の要因の影響を確かめるために、為替レート関数を推計してみた。ここでは、上記の日米実質金利差、マネタリーベース比、購買力平価(PPP)とともに、国内外の資産の不完全代替性を表し、外貨建て資産のリスクに対して上乗せの収益性といえるリスクプレミアムを説明変数に加えている。
その結果をまとめた図表⑤をみると、量的・質的金融緩和(QQE)開始時に、そのアナウンスメント効果によって円安が進んだことで、直接投資と外貨準備の円建て価格が上昇して、リスクプレミアム要因が円安圧力になった。その後、金融緩和によって日本のマネタリーベースが拡大したことで、円安圧力が強まった。2015年末から、米国が利上げ局面に入ると、実質金利差が円安圧力に加わった。その一方で、経常黒字に比べて直接投資が増えたことでドル建て資産保有のリスクプレミアム要因が、円高要因として大きくなった。また、その他の円高要因として、物価上昇が一服したことからPPP要因の揺り戻しもみられた。足もとでは、リスクプレミアムやPPP要因が剥落してきた一方で、引き続き緩和政策による円安圧力がかかってきたと解釈される。ただし、2017年になると、国債買い入れが減額されており、マネタリーベース比からの円安効果は弱まってきている。
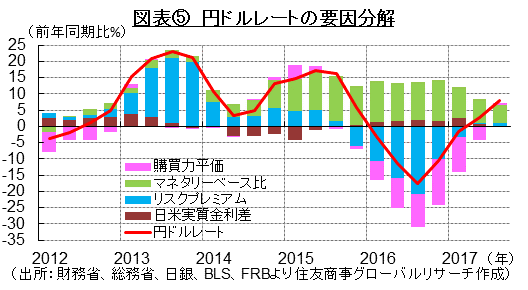
(図表⑤注)内閣府『平成24年度経済財政白書』「付注1-8為替レート関数の推計について」を参考に為替レート関数を推計した。被説明変数は円ドルレート(対数階差)、説明変数は日米実質金利差(短期金利、消費者物価指数で実質化)、リスクプレミアム((累積経常収支-累積直接投資-外貨準備高)÷名目GDPをHPフィルターによってトレンド要因を除いたもの、階差)、マネタリーベース比(日本÷米国、階差)、購買力平価(生産者価格ベース、対数階差)でカルマンフィルターによって推計し、パラメータはスムージング推定量を利用した。計算にはPetris, G., (2010), “An R Package for Dynamic Liner Models,” Journal of Statistical Software, Vol.36, Issues 12のdlm packageを用いた。
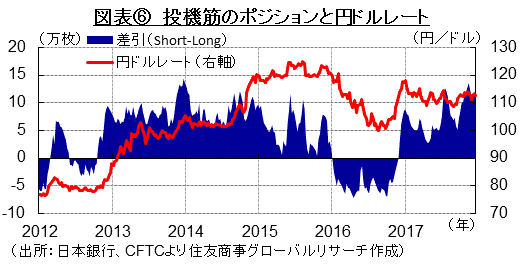
4. 円高・円安要因のバランス
先行きについて、まず、長期的な視点から、日本ではデフレではない状況が続き、デフレ脱却が視野に入り始めるなど、PPP要因は円安方向に寄与するだろう。次に、金融政策では、FRBのバランスシート縮小や利上げなど金融引き締めに対して、政策の見直しはあっても、日本銀行は均衡イールドカーブよりも実質イールドカーブを下げておく緩和姿勢をつづけることに変わりないと想定されるため、それは円安圧力になるとみられる。実質金利差については、米国の利上げに対して、日本の金利が据え置かれれば、金利差が拡大する。米国では、約30年ぶりとなる大型の税制改革が実施されたことで、景気が底上げされ、結果として利上げが進むこともありえる。その一方で、リーマンショック後に、米国の経済成長率が鈍化していることもあって、低下してきた自然利子率に歩調を合わせるように、FRBの長期的なターゲットである金利もこれまで下方修正が続いてきた。前回の利上げ局面と同じように、金利の上昇余地が限られることも想定される。また、日本の経常黒字が続けば、対外資産が増加して、リスクプレミアムが高まり、円高圧力が強まるだろう。これらを踏まえると、円高・円安要因の双方がある。
足もとでは、表⑥のように、投機筋のポジションは積みあがっていることも踏まえれば、日銀の金融政策の変更や、地政学的なリスクの高まりなどをきっかけに、円高に振れるリスクは残っている。しかし、上記の要因によって、基調としては一方的に円安や円高が進む環境にはなりにくいと考えられ、これから半年程度の間、足もとの為替レート±5円程度のレンジで推移するとみられる。
以上
記事のご利用について:当記事は、住友商事グローバルリサーチ株式会社(以下、「当社」)が信頼できると判断した情報に基づいて作成しており、作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、当社及び住友商事グループは、その情報の正確性、完全性、信頼性、安全性等において、いかなる保証もいたしません。当記事は、情報提供を目的として作成されたものであり、投資その他何らかの行動を勧誘するものではありません。また、当記事は筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社及び住友商事グループの統一された見解ではありません。当記事の全部または一部を著作権法で認められる範囲を超えて無断で利用することはご遠慮ください。なお、当社は、予告なしに当記事の変更・削除等を行うことがあります。当サイト内の記事のご利用についての詳細は「サイトのご利用について」をご確認ください。
 レポート・コラム
レポート・コラム
 SCGRランキング
SCGRランキング
- 2024年4月14日(日)
『日経ヴェリタス』に、当社シニアエコノミスト 鈴木 将之のコメントが掲載されました。 - 2024年4月12日(金)
日経CNBC『World Watch』に当社シニアアナリスト 石井 順也が出演しました。 - 2024年4月9日(火)
ラジオNIKKEI第1『マーケット・トレンドDX』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行が出演しました。 - 2024年4月9日(火)
『日本経済新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2024年4月9日(火)
『日刊産業新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。

