実感なき成長②~細くて長い海外から国内への波及経路
2018年03月13日
住友商事グローバルリサーチ 経済部
鈴木 将之
概要
景気回復の実感を得にくい理由として、その恩恵が消費者に到達するまでの波及経路が細くて長い可能性が考えられる。そこで以下では、海外現地法人の売上高の拡大が国内に波及する経路を検討してみる。対外的な日本企業のビジネスモデルが、輸出型から投資型に変化している中で、その所得配分について恩恵が広がるような構図にはなっていないと考えられる。それが、もともと長い海外現地法人の売上高の拡大が国内に波及するまでの経路を細いままにしている。
1. 海外からの波及経路
景気回復の実感を得にくい理由として、その恩恵が消費者に到達するまでの波及経路が細くて長い可能性が考えられる。そこで以下では、海外現地法人の売上高の拡大が国内に波及する経路を検討してみる。ここで想定しているのは、例えば現地法人売上高が拡大することで、国内にロイヤリティーや配当金などが増えて、企業業績が改善、家計の所得も増える経路である。
海外現地法人の動向から読み取れるのは、日本企業にとってその存在感が高まっていることだ。経済産業省『海外事業活動基本調査』によると、2015年度の海外現地法人の売上高は271兆円、うち135兆円が製造業だった。製造業の中でも輸送用機械が67.5兆円と最も大きかった。その一方で、財務省『法人企業統計調査』によると、国内法人の売上高は1,447.8兆円、うち製造業は397.8兆円(輸送用機械は70.9兆円)だった。
図表①のように、製造業の海外生産比率をみると、国内全法人ベースで2015年度に25.3%、海外進出企業ベースで38.9%に至るまでほぼ右肩上がりで上昇してきた。これより、特に製造業において海外現地法人の存在感が高まっていることがわかる。
また、注目されるのは設備投資や研究開発費の分野でも、海外現地法人の比重が高まっていることだ。海外設備投資比率は2015年度に25.5%と、設備投資全体の4分の1が海外に向かっている。研究開発費比率はまだ5%と低いとはいえ、設備投資と歩調を合わせるように上昇してきた。こうした変化の背景には、地産地消の生産体制が整う中で、設備投資や研究開発の増加も現地仕様が求められていることがあるのだろう。
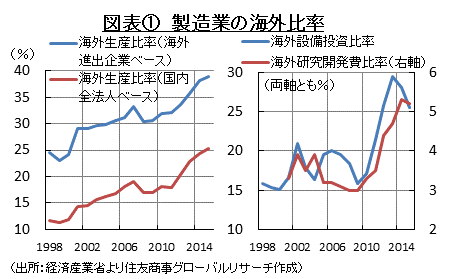
このような企業の海外シフトは、見方を変えると、国内から海外への生産工程の移管と捉えられる。そこで、一定の仮定の下で、製造業の現地生産による国内生産への影響を試算してみた。ここでは、その影響を、①逆輸入効果(海外現地法人の日本向け輸出額)、②輸出誘発効果(海外現地法人の日本からの輸入額)、③輸出代替効果(海外現地法人の販売額・輸出額のうち日本からの輸出が置き換わったと想定される部分)の3つに分けている。
その結果(図表②)によると、ここ10年間、逆輸入効果は8~14兆円程度、輸出誘発効果は16~20兆円程度でそれぞれ安定してきた。これより、海外現地法人企業と日本国内との間の貿易は、比較的安定していたといえる。
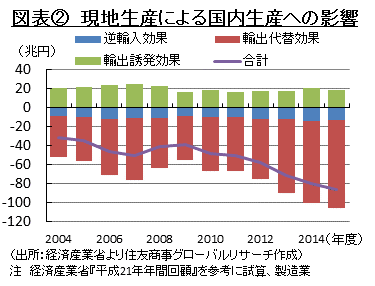
それに対して、輸出代替効果は大きく変化しており、2010年度の56.5兆円から2015年度の92.8兆円へと2倍弱の規模に拡大している。これは、海外現地の需要に対して、日本企業が国内からの輸出ではなく、海外現地法人による売上によって対応する企業が増えていることを示唆している。海外進出の目的が、かつてのコスト節約から現地での需要獲得、現地販売市場への参入へと変わってきているのだろう。
そう考えると、海外経済の成長によって、日本企業の海外現地生産法人が売上を伸ばす一方で、日本からの輸出はあまり増えない可能性がある。
2. 貿易から投資へ
このような変化の中で、企業の海外市場への対応は、輸出の拡大から海外現地法人があげた収益の回収という投資に移っている。
図表③のように、現地法人から日本側出資者への支払い(ロイヤルティや配当金など)をみると、2005年度の1.9兆円から2015年度には4.5兆円へと2.4倍に拡大している。配当金も比較可能な2004年度の1兆円から2015年度の2.7兆円へと2.7倍に拡大している。
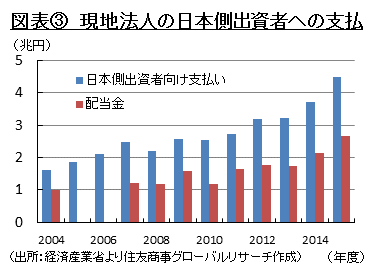
また、海外現地法人からのロイヤルティ収入も拡大している。図表④の『国際収支統計』上の産業財産権等使用料の受取額は2005年の1.8兆円から2015年には4.3兆円へと増加しており、国内企業の収益を押し上げている。特に、日本経済全体でみれば、知的財産権等使用料は1990年代末の支払超から、受取超へと転じており、日本企業のビジネスモデルの変化がうかがえる。
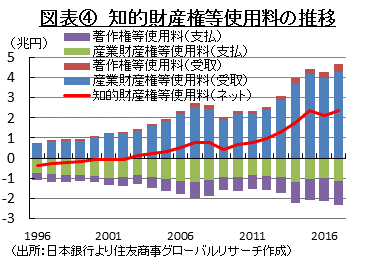
3. 細い波及経路
次に、注目されるのは、海外現地法人の売上高や収益の拡大が国内にロイヤリティーや配当金などとして還元され、企業業績が改善、家計の所得も増えるという波及経路がどこまで機能するかだ。
まず、海外現地法人の配当金が国内本社に戻ってきて、何に使われるのだろうか。経済産業省『海外事業活動基本調査』(2015年度、複数回答)によると、「雇用関係支出」(従業員給与・賞与、教育訓練など)にあてるという回答は9.0%にすぎなかった。また、「株主への配当」は9.2%と、それほど多くない。それに対して、「研究開発・設備投資」が20.0%と最多の回答だったものの、「分からない」が55.2%を占めている。雇用関係支出に回す部分はそれほど多くはなく、事実上明確な使途は決まっていないケースが多いということだろう。
2017年の直接投資収益(8.8兆円)のうち、再投資収益が4.4兆円と多くの資金が海外現地法人に滞留している(財務省『国際収支統計』)。もちろん、迅速かつ円滑に海外現地法人が投資できるように、内部で資金調達できる体制を整えているという一面がある一方で、国内に還流させずに、資金を上手く使いこなせていない可能性もある。
また、仮に株主への配当金が増えたとしても、それが消費を底上げする効果は限られると考えられる。第1に、配当金の源になる株式等の保有額が少ないことがあげられる。日本経済全体でみても、日本銀行『資金循環の日米欧比較』(2017年3月末時点)によると、家計の金融資産(1,809兆円)のうち株式等は10.0%に過ぎないなど、金額も必ずしも大きくはない。株式等の割合は米国では35.8%、ユーロ圏では18.2%と、日本とは異なった姿をしている。
第2に、配当金の恩恵が、一部の家計に偏る可能性もあげられる。総務省『平成26年全国消費実態調査』によると、有価証券保有率(総世帯)は23.5%、株式・株式投資信託保有率は19.4%だった。世帯主年齢別の株式・株式投資信託保有率は、30歳代11.2%、40歳代15.4%、50歳代22.2%、60歳代23.8%と年齢を重ねるにしたがって上昇している。もちろん、若年期の貯蓄形成が現金・預金から始まる傾向があることや、年齢が上がるにつれて親世代からの遺産を引き継いでいることが理由としてあげられる。そのため、現在の高齢者世代がすべて使い切らなければ、いずれ現在の若者世代も有価証券を遺産として引き継ぐことになるだろう。ただし現時点では、高齢世代ほど配当などの恩恵を受けやすいといえる。見方を変えると、企業の海外進出は、現役世代の雇用から高齢世代の資産収益へと、所得配分の形が変化していることになる。
第3に、配当金が消費に十分まわらない可能性がある。一般的に、所得が高い方が限界消費性向は低いと想定される。限界消費性向とは、例えば、所得が1万円増えたときに、どれだけ消費に回すのかを表すものであり、所得が高い人ほど、所得が増えてもそれをすぐに使う必要性が低いため、消費には向いにくいといえる。実際、内閣府『平成22年度経済財政白書』(P.201)は、年間収入五分位別に限界消費性向を推計しており、その結果によると、所得が低い方の第Ⅰ階級では限界消費性向が約0.40であるのに対して、所得が高い方の第Ⅴ階級では0.2~0.3となっており、高所得層ほど増加した所得が消費に回りにくい傾向がある。
また、株式など有価証券を保有している世帯の平均収入は、保有していない世帯に比べて高い傾向があると想定される。実際、金融広報中央委員会『家計の金融行動に関する世論調査』(平成29年)によると、年間収入300~500万円の世帯の金融資産額(二人以上の金融資産保有世帯)は1,479万円であり、そのうち株式・投資信託は180万円で12.2%だった。それに対して、年収750~1,000万円の世帯ではそれぞれ2,115万円、387万円、18.3%、1,000~1,200万円世帯では2,813万円、616万円、21.9%だった。これより、平均収入が多いほど株式などの保有も多く、配当金などの恩恵を受けやすいとみられる。
これらを合わせて考えると、海外現地法人からの配当金が国内に還元された場合に、広く消費を底上げする効果に対して、そこまで大きな期待はできないだろう。
4. 海外からの国内への波及経路は細くて長い
対外的な日本企業のビジネスモデルが、輸出型から投資型に変化している中で、その所得配分について恩恵が広がるような構図にはなっていないと考えられる。それが、もともと長い海外現地法人の売上高の拡大が国内に波及するまでの経路を細いままにしている。その結果として、景気回復の恩恵が国内に広く波及せず、実感を得にくくなっていると考えられる。
以上
記事のご利用について:当記事は、住友商事グローバルリサーチ株式会社(以下、「当社」)が信頼できると判断した情報に基づいて作成しており、作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、当社及び住友商事グループは、その情報の正確性、完全性、信頼性、安全性等において、いかなる保証もいたしません。当記事は、情報提供を目的として作成されたものであり、投資その他何らかの行動を勧誘するものではありません。また、当記事は筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社及び住友商事グループの統一された見解ではありません。当記事の全部または一部を著作権法で認められる範囲を超えて無断で利用することはご遠慮ください。なお、当社は、予告なしに当記事の変更・削除等を行うことがあります。当サイト内の記事のご利用についての詳細は「サイトのご利用について」をご確認ください。
 レポート・コラム
レポート・コラム
 SCGRランキング
SCGRランキング
- 2024年4月14日(日)
『日経ヴェリタス』に、当社シニアエコノミスト 鈴木 将之のコメントが掲載されました。 - 2024年4月12日(金)
日経CNBC『World Watch』に当社シニアアナリスト 石井 順也が出演しました。 - 2024年4月9日(火)
ラジオNIKKEI第1『マーケット・トレンドDX』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行が出演しました。 - 2024年4月9日(火)
『日本経済新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2024年4月9日(火)
『日刊産業新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。

