安定してきたドル円で燻る円高リスク
調査レポート
2018年12月04日
住友商事グローバルリサーチ 経済部
鈴木 将之
概要
世界経済の先行きに対する下押しリスクへの懸念が色濃くなっている。「一強」状態だった米国に対して、日欧の景気には弱い一面がみられたという構図の中で、堅調な米景気を背景としたドル買いと、リスク回避の円買いがせめぎ合う状況になり、ドル円は横ばい圏で推移してきた。そうした動きは、円高・円安要因が拮抗している足もとの経済ファンダメンタルズからも裏付けられる。その一方で、足もとのユーロ円レートは、欧州政治・経済リスクなどから、円高方向にある。先行きについては、経済状況に基づくと、引き続き横ばい圏内で推移すると見込まれる。ただし、政治・経済リスクを踏まえれば、円高リスクを考えざるを得ないだろう。
1. 世界経済の先行きへの懸念
2018年も終盤を迎えつつある中、世界経済の先行きに対する下押しリスクへの懸念が色濃くなっている。そうしたリスクの中でも、図表①のように、ドル円レートは1ドル=112~114円のレンジで推移しており、むしろ安定している様子が目立っている。
こうした背景には、経済環境の相違があった。図表②のように、米国の経済成長率は、2018年第3四半期(以下Q3)に前期比年率3.5%と引き続き高水準の成長となった。
それに対して、日本では景気回復局面が続くものの、その成長ペースは鈍化しつつある。2018年Q1の9四半期ぶりのマイナス成長から、Q2にはプラス成長に回復したものの、Q3は自然災害の影響などもあって、再びマイナス成長となった。一時的な要因ならば、成長ペースの再加速が想定される。しかし、足もとで下振れリスクが高まりつつあり、想定通りの成長が実現するかが懸念されるようになっている。
欧州経済でも、減速感が強まっている。2018年Q1からの反動増が期待されたQ2に成長ペースが加速しなかった上、Q3にはさらに鈍化した。ドイツでは、新しい排ガス規制導入を巡る自動車などの減産が響いたこともあって、マイナス成長になったほどだった。
こうした米国の1強状態ともいえる堅調な景気を背景に2018年半ばまでドルが買われた一方で、米中貿易戦争や中国経済の減速などによるリスク回避の円買いもあり、双方が拮抗したことでドル円は安定してきた。
しかし、そうした状況は徐々に変化しつつある。米国のQ3成長率は民間在庫純増を除けば1.2%成長と、見た目ほど強い成長とはいえない。年末商戦の堅調さが報じられる一方で、米中貿易戦争の影響などもあって、企業の設備投資にはピークアウト感もみられる。
また、欧州の景気自体が、それほど強くはないとの見方も広がりつつある。例えば、欧州委員会のユーロ圏景況感指数(ESI)では、年初から低下トレンドが続いており、水準が高いとはいえ、企業・消費者マインドなどの方向感は下向きが続いている。米中貿易戦争に加えて、Brexit交渉やイタリアの予算問題など、次々とリスクが発生していることも、欧州経済の重石になっている。
このように、ドル円の安定は、リスク回避の円高と1強状態の米国経済に裏付けされたドル高のバランスの上に成り立ってきた。今後、この前提が崩れることで、ドル円の状況は2018年後半とは異なったものになる可能性が高い。米中貿易戦争の落ち着きどころが見えない中で、実体経済の成長に対する先行き不透明感が高まりつつあるため、為替レートがどのように推移するのかが注目される。
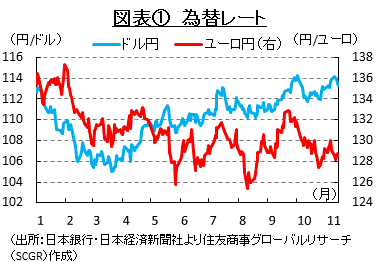
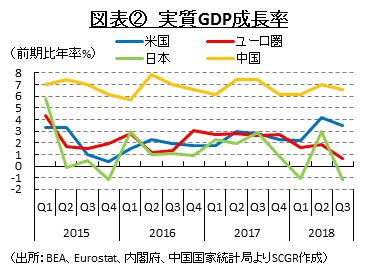
2. 堅調な実体経済に裏付けされた金融引き締め
金融政策の変化も注目される。図表③のように、FRBはいち早く金融引き締めに動いており、2018年はすでに3回の利上げを実施している。物価の安定と雇用の創出を背景にして、FRBはバランスシートの縮小も着実に進めており、米国の金融政策は緩やかに正常化に向かっている。
また、ECBも金融緩和の出口に向かっている。資産買い入れプログラムは、10月から月額150億ドルの購入に縮小されており、ドラギ総裁の発言によると、年末の停止が視野に入っている。当面、再投資によって、ECBのバランスシートの規模は保たれるものの、2019年夏以降の利上げが視野に入っている。
欧米の金融政策の緩和から引き締め方向に移行する背景には、経済成長と物価上昇という裏付けがある。物価上昇によって、実質金利は低下しており、図表④のように、金融緩和効果をより高めている。消費者物価指数によって調整した実質長期金利は、日欧でマイナス圏に突入しており、米国も0%台前半を推移している。その一方で、景気を過熱も冷やしもしない中立的な金利とされる「自然利子率」の近似として用いられる潜在成長率は、米国で約2%、欧州で約1.5%、日本で約1%であり、それぞれ実質長期金利を上回った状態が続いている。このため、足もとでは、緩和の状態が続いているといえる。このような緩和効果の中で、物価が持続的に上昇すれば、必然的に金融政策は引き締め方向に舵が切られる。
2018年に入って新興国通貨安が懸念材料として大きくなった。FRBの段階的な引き締めもあって、新興国から米国への資金の巻き戻しの動きがみられ、新興国経済のファンダメンタルズの弱さも加わって、2018年になって通貨安が目立つ新興国がみられるようになった。そうした影響が今後、欧米に跳ね返ると、金融引き締めを進める前提条件である経済環境が崩れてしまいかねない。足もとでは、米中貿易戦争という要因も加わって、先行き不透明感が高まりつつある。
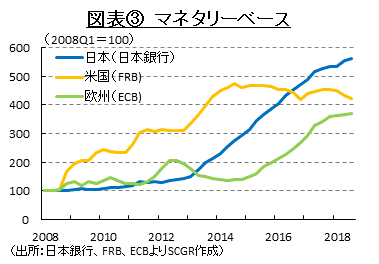
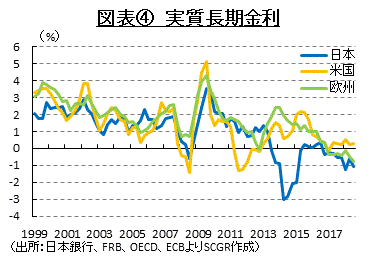
3. 為替レートは当面横ばい圏か
まず、ドル円レートを経済ファンダメンタルズの点から考えるために、為替レートに影響を及ぼす要因に分解してみた。
図表⑤のように、Q3時点では、ドル円レートの前年同期比がほぼゼロと横ばい圏内にあり、これらの影響力が拮抗している。日本では金融緩和が継続する一方で、米国では利上げが継続しており、バランスシートの縮小も着実に進んでいるという金融政策の方向性の相違から、マネタリーベース比要因は円安・ドル高に寄与している。また、日本の物価が伸び悩みをみせる一方で、米国ではインフレ目標の2%近傍を推移しているため、購買力平価要因から長期的な円高圧力が働いている。これまでの原油価格の上昇などによって黒字幅は縮小しているものの、日本の経常収支は黒字を保っているため、リスクプレミアム要因は円高方向に寄与している。こうした円高・円安要因の綱引きは足もとでは拮抗状態に陥っている。そうした状況が、ドル円の安定的な推移を生み出す一因になっていると考えられる。
同じように、ユーロ円レートについても要因分解してみた。図表⑥のように、足もとでは、日欧実質金利差は円高・ユーロ安要因となっていた。これは、欧州の物価上昇率が日本に比べて、前年同期からの伸び幅が大きかったため、その分実質金利が大幅に低下したためだ。ユーロ圏も経常黒字となった一方で、日本の経常黒字がそれ以前から継続しており、対外資産も積みあがっていたことから、リスクプレミアム要因は引き続き円高・ユーロ安要因となっている。その一方で、円安・ユーロ高圧力となっているものに、購買力平価がある。これは、消費者物価上昇率が、日本よりも欧州の方が高いことを反映しており、ユーロが円に対して減価しやすいことを表している。また、ユーロ円レートの現実値と理論値の調整弁となる部分調整項は2017年以降、緩やかに縮小しつつも、円安・ユーロ高要因となってきた。これらを均してみれば、ユーロ円の決定要因も双方の圧力が拮抗しており、Q3時点では横ばい圏にあるといえる。
Q4で試算したレートよりも円高・ユーロ安方向で推移している一因として、Brexit交渉やイタリアの予算問題などの政治リスクの高まりがあげられるだろう。また、欧州経済の景況感が想定以上に悪化しているように、先行きに対する懸念が高まっており、それらがユーロ売り・円買い材料になっていることが想定される。2017年に絶好調だったこともあり、2018年にはその反動が出やすい環境にあったこともあげられる。
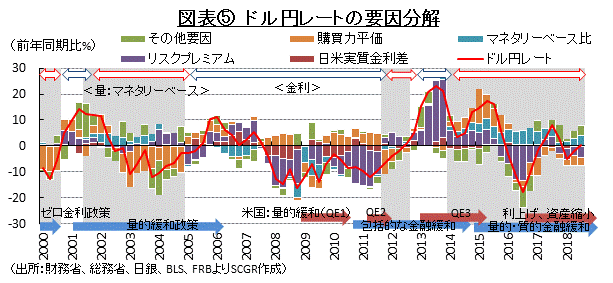
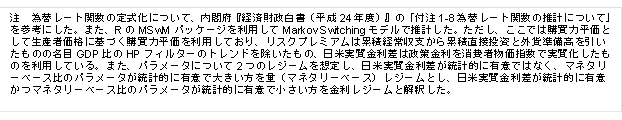
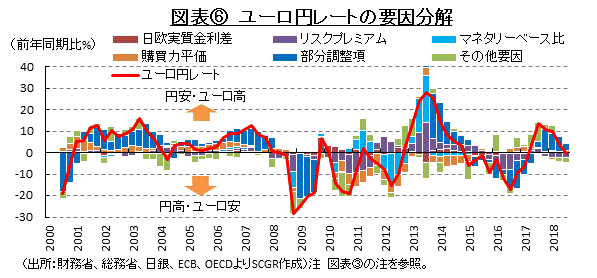
4. 先行きの円高リスクがじわりと高まる
為替レートの先行きについて、上記の点から検討してみよう。
まず、足もとでの原油価格の下落によって、今後の物価上昇率は鈍化すると見込まれる。これは購買力平価要因や実質金利差要因を通じて為替レートに影響を及ぼす。現在の物価上昇局面をみると、米国では賃金上昇を背景にサービス価格が上昇しており、持続的な物価上昇の基礎があるといえる。欧州では、雇用者報酬が増えており、これも労働環境の改善を反映しながら、物価の上昇トレンドを下支えしていると考えられる。それに対して、現在の日本の物価上昇はエネルギー価格に依存している面が大きい。実際、10月の『消費者物価指数』(総務省)では、前年同月比+14.8%の石油製品を含む財価格の同+2.1%に対して、サービス価格は同+0.2%にとどまった。賃金が上昇傾向にあるとはいえ、日本の物価上昇圧力は弱い。そのため、円高を想起させやすくなっている。
金融政策については、今後の米国の引き締め、欧州の緩和打ち止めを想定すれば、マネタリーベース比要因や実質金利差要因で円安圧力になりうる。もちろん、仮に2019年以降、景気の鈍化などによって、米国の利上げペースが緩やかになれば、円安圧力は当初の想定ほど働かなくなる。欧州についても、予定通り年末に資産買い入れプログラムを終了したとしても、次の利上げが遠のくようなアナウンスがあれば、ユーロ高圧力にはなりがたいだろう。その一方で、経常黒字を背景とした日本の対外資産増加という傾向には大きな変化がないとみられるため、リスクプレミアム要因は円高要因となりつづけるだろう。
こうしたことを踏まえると、為替レートは当面横ばい圏内の推移となるものの、円高圧力がじわりと高まっているといえるだろう。上記の推計結果に基づいて、足もとの経済環境に大きな変化がないと仮定した場合の為替レートを試算すると、図表⑦のように、ドル円レートは1ドル=113円40銭(108~115円のレンジ)、ユーロ円レートは1ユーロ=132円60銭(125~135円のレンジ)程度と、円高リスクを伴いながら推移するとみられる。
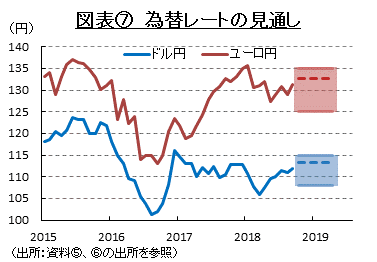
上記以外で当面注目されるリスク要因は、貿易摩擦があげられる。2019年には、日米間の物品貿易協定(TAG)交渉が本格化する見込みだ。そこでの注目点は、自動車輸出や為替条項などである。また、米中貿易戦争でも、知的財産権や技術移転などの根深い問題が残されており、交渉が難航することが予想されている。
また、欧州政治では、当面Brexit交渉、イタリア予算問題・政治リスクが懸念材料である。その他にも、ギリシャの債務返済状況、ドイツ政治状況、欧州議会選挙など、市場がリスクとみなしうる項目は数多くある。
こうしたことを考えると、市場にとって先行き不透明感が高まる要因が多いため、円高シナリオをリスクとして意識せざるを得ないだろう。
以上
記事のご利用について:当記事は、住友商事グローバルリサーチ株式会社(以下、「当社」)が信頼できると判断した情報に基づいて作成しており、作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、当社及び住友商事グループは、その情報の正確性、完全性、信頼性、安全性等において、いかなる保証もいたしません。当記事は、情報提供を目的として作成されたものであり、投資その他何らかの行動を勧誘するものではありません。また、当記事は筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社及び住友商事グループの統一された見解ではありません。当記事の全部または一部を著作権法で認められる範囲を超えて無断で利用することはご遠慮ください。なお、当社は、予告なしに当記事の変更・削除等を行うことがあります。当サイト内の記事のご利用についての詳細は「サイトのご利用について」をご確認ください。
 レポート・コラム
レポート・コラム
 SCGRランキング
SCGRランキング
- 2024年4月22日(月)
『Yahoo!ニュース』に、公式コメンテーターとして米州住友商事会社ワシントン事務所調査部長 渡辺 亮司のコメントが先週4本掲載されました。 - 2024年4月22日(月)
毎日新聞出版『週刊エコノミスト』2024年5月7日号に、米州住友商事会社ワシントン事務所長 吉村 亮太が寄稿しました。 - 2024年4月18日(木)
『鉄鋼新聞』に、ロンドン金属取引所(LME)主催「東京フォーラム」で、当社チーフエコノミスト 本間 隆行が講演したことについて掲載されました。 - 2024年4月17日(水)
『日本経済新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2024年4月14日(日)
『日経ヴェリタス』に、当社シニアエコノミスト 鈴木 将之のコメントが掲載されました。

