長期化する低金利の世界
調査レポート
2020年10月05日
住友商事グローバルリサーチ 経済部
鈴木 将之
(2020年9月25日執筆)
概要
新型コロナウイルス(COVID-19)危機の中、日米欧の金融緩和が一段と進んだ。推計した均衡実質金利は足元でマイナス圏にあり、様々な経済のゆがみを表していると考えられる。今後も当面低金利が継続する見込みである一方、「ウィズ・コロナ」や「デジタル化」という大きな時代の変化もある。現在の人々や企業の決断の積み重ねが、低金利の現状から早期に脱却できるかなど、将来を大きく変える分岐点になるかもしれない。
1. コロナ危機と金融緩和
新型コロナウイルス(COVID-19)危機の当初、日米欧の中央銀行(中銀)は金融緩和姿勢を強めた。資金繰り支援や市場の流動性供給など、経済の下支えという性格が強かったものの、それらが奏功し、経済活動が再開しはじめたことによって、景気は持ち直しつつある。ただし、景気回復局面では、感染抑制と需要回復の両立を図らねばならず、通常の景気対策が難しい状況にある。そのため、感染拡大前の経済水準への回復は2021年以降と、当面低成長が続く見通しだ。
こうした中、米連邦準備制度理事会(FRB)は8月末、「平均2%インフレ目標」を発表、少なくとも2023年末までゼロ金利が続く公算が高まった。日欧の中銀も金融緩和方針に変わりなく、市場では低金利の長期化が織り込まれている。そこで、金利という視点から日米欧を比較しつつ、今後を考えてみる。
2. 日米欧の金利低下
低金利が継続してきた中で、利下げの効果に懐疑的な見方も増えつつある。例えば、FRBはマイナス金利やイールドカーブ・コントロールの導入に否定的な姿勢を示している。また、スウェーデンのリクスバンクはマイナス金利から脱却後、今回の危機においても金利を下げておらず、むしろ流動性供給が重要という考えを明らかにしている。この背景には、非伝統的な金利政策の深掘りに対する警戒感があるのだろう。
2000年代以前のように、金利が高かった時には、中銀が例えば6%から2%へと金利を引き下げれば、資本コストも明確に低下して設備投資などの需要を押し上げることができた。しかし、リーマンショック後、すでに低い水準から金利をさらに引き下げても、その他のリスク要因を加味すれば、資本コストの低下効果はかなり小さくなった。また、低金利が長期化する中、低金利が前提条件となった状態の下で、企業の事業戦略が決定されており、利下げが設備投資の増加に結び付きにくくなっている。実際、低金利時代の利下げは、中銀の金融緩和姿勢のアピールにはなっても、需要を十分に押し上げられなかったようだ。
その一方で、低金利の悪影響も懸念されている。利下げの初期段階では、債券価格の上昇によって、債券売却益が押し上げられるメリットが金融機関にはあった。しかし、低金利が長期化した段階では、低利で資金調達できる一方で、低利の融資にせざるを得ず、金融機関の収益に下押し圧力がかかっている。その結果、貸出行動などの変化など、金融システムへの影響も懸念されている。また、家計では利子収入が減少してきた上、海外では口座維持などに手数料がかかるケースもありうる。このように悪影響が目立つようになる、いわゆるリバーサルレート(金利の下げ過ぎによる利下げ効果の反転)を欧州中央銀行(ECB)などは意識していた。
そこで、金利について「均衡実質金利」から考えてみる。この均衡実質金利とは、実際の生産量が潜在生産量に一致して物価を急騰や下落もさせない金利とされる(詳しくは鎌田(2009)を参照)。これは潜在成長率などと連動するなど経済の動向を示しており、中銀も政策決定時に参照しているとされている。以下では、鎌田(2009)で紹介されている方法を用いて、均衡実質金利(自然利子率)を推計した。
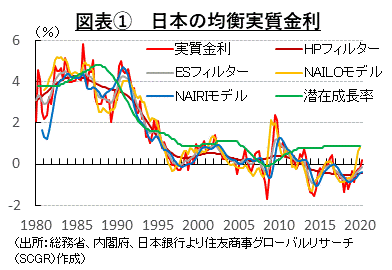
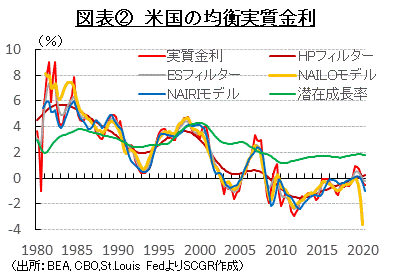
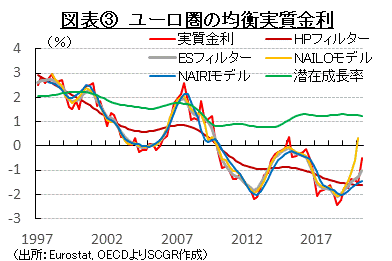
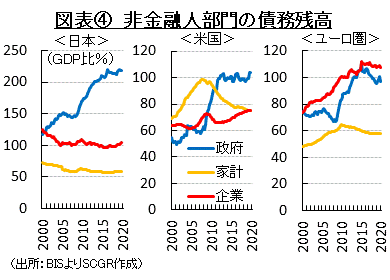
ここでは、均衡実質金利は観察されず、推計せざるを得ないものであり、幅を持ってみる必要があるため、1) Hodrick and Prescott(HP)フィルターや2) Exponential Smoothing(ES)フィルター、3) 鎌田・廣瀬(2003)の方法(潜在GDPとフィリップス曲線の同時推計法。それによるNon-Accelerating Inflation Level of Output(NAILOモデル)から導出したGDPギャップと均衡実質金利の同時推計)、4) 物価上昇率を加減速させない均衡実質金利であるNon-Accelerating Inflation Rate of Interest(NAIRIモデル)の4つのタイプの均衡実質金利を計算した。対象は日本の無担保コール・オーバーナイト物金利、米国の実効フェデラルファンド(FF)金利、ユーロ圏の3か月物金利であり、過去を踏まえて将来見通しを設定する適応的期待の仮定を置いて各国・地域の消費者物価指数によって実質化した。
図表①、②、③のように、日米欧で共通することは、足元で推計方法による差が大きいことだ。これは、感染対策として経済活動を部分的に止めたことで2020年第2四半期のGDP成長率が急落したことが一因だ。このため、均衡実質金利の把握が難しくなり、政策の難易度も高まっている。さらに、現在の回復局面では、感染抑制と経済活動の再開の両立が要請されるなど、通常とは異なる景気政策の難しさもある。
また、均衡実質金利がリーマンショック前とリーマンショック後で段階的に低下し、マイナス圏に突入したことが挙げられる。ただし、リーマンショック前には、均衡実質金利はマイナス圏に大きく踏み込まず、比較的早期にプラス圏に戻っていた。しかし、リーマンショック後には、マイナスの状態が続いた。これは、金融緩和効果を生み出すにはゼロやマイナス圏までの利下げが必要なことを意味する。その結果、マイナスの均衡実質金利を下回るマイナスの実質金利という理論的には整合性のある緩和政策も、現実的には実感しにくくなっており、しかもその状態がこれまで継続してきた。
さらに、日米欧の均衡実質金利が潜在成長率(図中の日本は内閣府推計、米国は議会予算局(CBO)推計、ユーロ圏はOECD推計)を下回っていることも共通している。均衡実質金利が潜在成長率で近似されることがある。ただし、潜在成長率で均衡実質金利が近似されるためには、例えば長期的な経済成長において、生産量や消費、資本ストックなどが定率で成長すること(均斉成長)や、実質金利と実質消費の変動率が近い(異時点間の代替率が1で近似)、異時点間の消費からの効用が無差別(時間選好率がゼロ)などの仮定を満たすことが必要になる(詳しくは小田・村永(2003)を参照)。ここで図示された潜在成長率が真の潜在成長率ならば、この乖離は経済が安定的な成長経路から外れていることなどを示唆する。つまり、何らかの歪みが生じている可能性があり、その歪みの調整を行わないかぎり、現状が続くのかもしれない。
また、仮に均衡実質金利が真の潜在成長率に一致している、すなわち図示された潜在成長率が真の潜在成長率ではないならば、図示された潜在成長率は何らかの要因によって上振れている可能性がある。例えば、ここでの潜在成長率は生産関数アプローチによって推計されているため、過剰になったり、社会のニーズに合わなくなったりした資本ストックも潜在生産力に換算されている可能性がある。また、設備投資の中でも、ITや知的財産権などソフト面の投資が増加していたり、海外生産拠点に移管・代替などをしていたりするため、国内生産能力の位置づけも実態的には変化している。
ただし、潜在成長率がマイナス圏に沈みつづけるということも想定しがたいため、現実的には、安定成長からの外れや潜在成長率の上振れなどのいずれか一方ではなく、双方の要因が絡みあった結果であり、経済の歪みが表れていると考えられる。
3. 現在は大きな分岐点か
一方で、債務残高のGDP比が拡大しており、利上げに財政が耐えられない懸念もある。図表④のように、日本では政府、米国では政府と企業、ユーロ圏でも政府と企業の債務が増加してきた。今回のCOVID-19危機でも財政が拡大しており、さらに債務が拡大する中では、利上げには慎重にならざるを得ない一面がある。また、財政には徴税権があるのに対して、企業の債務においてはそうしたものはない。こうした状況を踏まえると、将来的な利上げといっても、2000年代以前のような水準に金利を戻すことのハードルは高い。
そもそも成長が鈍化している中では、低金利の継続がますます想像されやすくなる。低金利の世界が続くという前提で、企業や家計などが行動することで、結果として低金利世界が継続してしまうという悪循環が懸念される。そうした状況は、低金利からの脱却の難易度を上げてしまう。実際、マイナス金利から脱却したスウェーデンは、利上げを市場に織り込んでから、実際にゼロ金利にするまでかなり時間がかかり、世界経済の景気がピークアウトして、ギリギリのタイミングでようやく成し遂げられたという状況だった。また、米国は新型コロナ危機前に事実上のゼロ金利から脱却したものの、当初の利上げペースはゆっくりと慎重で、利上げ幅も限定的でリーマンショック前の水準には到達できなかった。
こうした前例を踏まえると、抜け出すことが難しい「ゼロ近傍の低金利」という変わらない世界が当面継続する。その一方で、「ウィズ・コロナ」や「デジタル化」という変わりゆく世界があることも事実だ。後者は、社会的なニーズに対応した投資を増やして、真の潜在成長率を押し上げていく機会になる。この変化への対応をテコにして成長できれば、結果的に低金利の世界から脱却する時期も早まるかもしれない。ただし、低金利の世界に慣れすぎてしまったため、成長の機会を見つける感度が鈍くなり、それをつかみ損ねる恐れもある。現在の人々や企業の決断の積み重ねが、低金利の現状から早期に脱却できるか否かなど、将来を大きく変える分岐点になるのかもしれない。
参考文献
小田信之・村永淳(2003)「自然利子率について:理論整理と計測」日本銀行ワーキングペーパーシリーズNo.03-J-5.
鎌田康一郎・廣瀬康生(2003)「潜在GDPとフィリップス曲線を同時推計する新手法」『金融研究』第22巻第2号pp.13-34.
鎌田康一郎(2009)「わが国の均衡実質金利」深尾京司編『マクロ経済と産業構造』慶應義塾大学出版会.
以上
記事のご利用について:当記事は、住友商事グローバルリサーチ株式会社(以下、「当社」)が信頼できると判断した情報に基づいて作成しており、作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、当社及び住友商事グループは、その情報の正確性、完全性、信頼性、安全性等において、いかなる保証もいたしません。当記事は、情報提供を目的として作成されたものであり、投資その他何らかの行動を勧誘するものではありません。また、当記事は筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社及び住友商事グループの統一された見解ではありません。当記事の全部または一部を著作権法で認められる範囲を超えて無断で利用することはご遠慮ください。なお、当社は、予告なしに当記事の変更・削除等を行うことがあります。当サイト内の記事のご利用についての詳細は「サイトのご利用について」をご確認ください。
 レポート・コラム
レポート・コラム
 SCGRランキング
SCGRランキング
- 2024年4月14日(日)
『日経ヴェリタス』に、当社シニアエコノミスト 鈴木 将之のコメントが掲載されました。 - 2024年4月12日(金)
日経CNBC『World Watch』に当社シニアアナリスト 石井 順也が出演しました。 - 2024年4月9日(火)
ラジオNIKKEI第1『マーケット・トレンドDX』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行が出演しました。 - 2024年4月9日(火)
『日本経済新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2024年4月9日(火)
『日刊産業新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。

