イタリアの政治的不安定:経済への影響
2018年08月06日
住友商事グローバルリサーチ 経済部ポール エル メディオニ
概要
2018年6月以降、イタリア政治の不安定さが高まっている。こうした政治的不安定は、イタリア経済にどのような影響を与えるのだろうか。イタリアの経済成長率への寄与の中で、輸出は牽引役だった。輸出を需要側からみると、世界景気がイタリアの輸出に重要な影響を与えてきたことがわかる。また、供給側からは、労働コストと法人税率が重要な要因であったことが示唆される。これらを踏まえながら、当面、世界経済は成長するとみられるため、輸出がイタリア経済の成長に貢献しつづけると期待される。また、コンテ政権は法人税率を引き下げる予定なので、ビジネス環境にとってはプラス効果が期待される。しかし、最低所得保障の実施は、長期的に見れば労働コストの増加を通じて価格競争力を低下させる。これまで成長を牽引してきた輸出が経済成長の足を引っ張る恐れがあるので、今後の同国の政策動向が注目される。
1. イタリアの政治の背景
2018年3月のイタリア総選挙の結果、下院で五つ星運動は227議席(36%)、同盟は125議席(20%)、上院ではそれぞれ112議席(36%)、58議席(18%)を獲得した。この2政党が連立政権を樹立し、イタリア政治は大きな転換点を迎えた。両政党はポピュリズム(大衆迎合)的であり、反欧州統合・反移民を政策として掲げている。両党の支持を得て、6月1日にジュゼッペ・コンテ氏が首相に就任した。これにより、市場ではイタリアの政治リスクが強く意識されるようになった。
現在のような政治的な不安定さは、今後のイタリア経済にどんな影響を与えるのだろうか。そこで、経済成長の牽引力を検討した上で、先行きについて考えてみる。
2. イタリアの経済成長の要因分解
まず、図表①のように、イタリア経済の成長源を確かめるために、経済成長率を要因分解してみた。イタリアの景気循環をみると、リーマンショック前の景気拡張期間は2003年7月から2008年2月までであり、現在の拡張期間は2013年4月以降である。個人消費・公共事業と企業設備投資などを含む「内需」の経済成長率(前期比)への寄与度は、2003年第3四半期(以下Q3)~2008年Q1平均で0.29%ポイント、2013年Q1~2017年Q4平均では0.17%ポイントだった。一方、「輸出」の寄与度はそれぞれ0.36%ポイント、0.27%ポイントだった。いずれの景気拡張期間を見ても、寄与度は輸出の方が大きいので、輸出が経済成長の牽引役であったことがわかる。
また、リーマンショック前(2007年)の水準と比べて、2017年の輸出額は22.8%増加した。また、個人消費は8.7%増加し、公共事業は4.8%増加した一方で、企業設備投資は16.5%減少したので、内需は3.9%減少となった。同じ期間にGDPは6.8%増加していたので、輸出によって経済が成長してきたといえる。
以上を踏まえて、イタリアの輸出について考察する。イタリア政治の先行き不透明感から、個人消費など内需の動向が懸念される中、成長の牽引役として輸出への期待が大きくなる。一般的に、輸出は主に海外市場を対象にしているので、国内の悪影響を受けにくいというメリットがあるとはいえ、イタリアの先行きを考える上で、輸出の背景を整理しておくことは重要だろう。
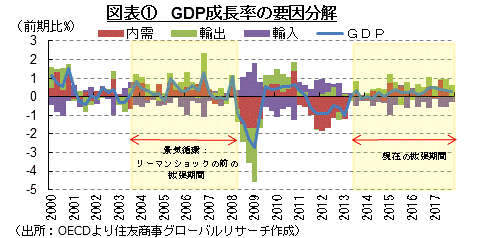
3.輸出の需要側の影響
まず、輸出について需要側から考えてみる。一般的に輸出需要において、価格と所得の2つの要因が重要な役割を果たすことが知られている。
価格の代理変数として、ここでは、実質実効為替レート(REER:Real Effective Exchange Rate)に注目する。REERは貿易相手国ごとに、為替レートを貿易額ウェイトで加重平均したものを、お互いの物価指数によって実質化した数値である。そのため、相対価格を為替レートで変換した上で、さらに貿易の競争力や貿易相手国の市場規模などを加味した価格指数と解釈できる。
このREERの水準が低いと自国通貨安と解釈されるので、輸出需要が拡大する傾向があると想定される。図表②のように、2003年Q3~2008年Q1のイタリアのREER平均は98.9であった。同時期のオランダ(100.1)、フランス(100.7)とドイツ(100.7)よりも、イタリアは低水準にとどまっていた。
また、2013年Q1~2017年Q4のイタリアのREER平均は98.1であった。オランダ(99.5)はイタリアより高いものの、フランス(96.2)とドイツ(96.9)は低かった。
2003年Q3~2008年Q1から2013年Q1~2017年Q4にかけてイタリアのREER平均はそれほど変化しておらず、むしろフランスなどの方が低いため、価格面からはイタリアの輸出競争力は低下している可能性があると考えられる。
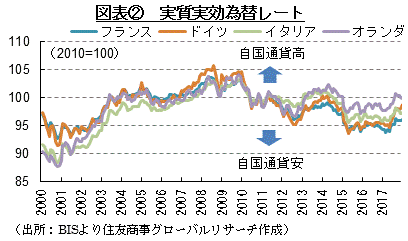
次に、輸出先の需要の指標をみておく。図表③では、REERのように貿易相手国ごとの輸出額の大きさを加味した需要について考える。ここでは、輸出先の市場規模や需要動向の代理変数としてGDPを用いた。それを国別の輸出シェアで加重平均したものを、イタリアからみた輸出市場の需要動向(輸出加重平均GDP成長率)と解釈する。なお、輸出先として輸出額が多い上位10か国を対象としている。
2003年Q3~2008年Q1と、2013年Q1~2017年Q4のいずれの期間でも、輸出加重平均GDPと、イタリアの輸出の動きは連動している。そのため、海外需要がイタリアの輸出増に大きく貢献してきたと考えられる。
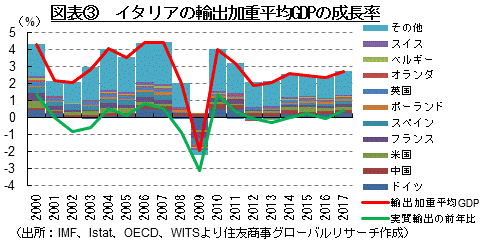
以上のように、輸出を需要側から見ると、価格要因(REER)よりも、所得要因(輸出加重平均GDP)の方が、イタリアの輸出に強い影響を及ぼしてきたと考えられる。そのため、為替レートよりも、世界景気の動向がイタリア輸出を見る上で重要な要因といえる。
4.輸出の供給側の影響
続いて、イタリアの輸出を供給サイドから考えてみる。まず、イタリアの輸出競争力を把握する上で、顕示的比較優位(RCA:Revealed Comparative Advantage)指数を計算してみた。これは、輸出商品別に各国の輸出総額シェアと世界の輸出総額におけるシェア(世界平均シェア)を比べたものである。そのため、ある国のシェアが世界平均シェアよりも高い場合、その国は競争力をもっているとみなされる。
ここでは、全体的な競争力をみるために、輸出商品別のRCAを、輸出額をウェイトとして集計した加重平均RCAを比較した。イタリアの加重平均RCAは緩やかな低下傾向にあるものの、ドイツやフランスよりも高い水準を維持している。そのため、イタリアの輸出には、競争力が高い輸出商品があることが示唆される。
それでは、その競争力の源泉はどこにあるのだろうか。以下では、イタリアの単位労働コスト、全要素生産性(MFP:Multi-factor productivity)、資本装備率と法人税率に注目して分析する。
はじめに、マクロの単位労働コストから、コスト競争力に焦点をあてる。これは、雇用者報酬総額を実質GDPで割ったものであるので、1単位の実質GDPを生み出すために必要な労働コストと解釈できる。そのため、このコストが低いと、コスト競争力があるといえる。
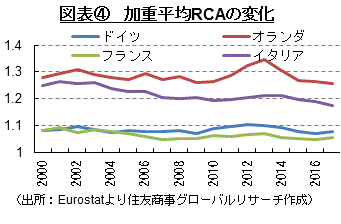
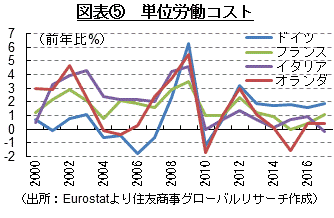
図表⑤のように、リーマンショック以前では、イタリアの単位労働コストは、ドイツやフランス、オランダよりも高い伸びを示した。そのため、イタリアのコスト競争力が高いとは言えない状況にあった。しかし、リーマンショック後になると、状況は変わった。イタリアの単位労働コストの上昇率は、ドイツ、フランス、オランダを下回る年が多くなった。つまり、単位労働コストという点からは、イタリアの競争力は改善方向にあったといえる。
また、単位労働コストは、名目賃金と労働生産性の掛け算で表される。その労働生産性は一定の仮定の下で、技術進歩などを含む生産性の向上と、資本装備率(1人あたりの資本ストック)の2つの変数に分解される。そこで、技術進歩を含めた生産性の動向を確認しておく。ここでは、生産性の指標として全要素生産性(MFP)に着目する。
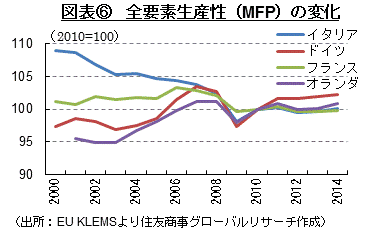
図表⑥のように、イタリアのMFPは、2003~08年平均から2013~14年平均にかけて、4.7%低下した。しかし、欧州債務危機後は下げ止まっており、少なくとも生産性が悪影響を及ぼしているとはいえないようだ。
また、資本装備率について、労働力と資本ストックの2つに分けて捉えてみる。労働者数は2000年の2,108万人から2016年の2,276万人へと8%増加した。また、設備投資の伸び悩みから、資本ストックは2011年までは増加してきたものの、それ以降はほぼ横ばいで推移している。そのため、図表⑦のように、資本装備率は2011年にかけて上昇し、緩やかに低下する方向に転じたとみられる。
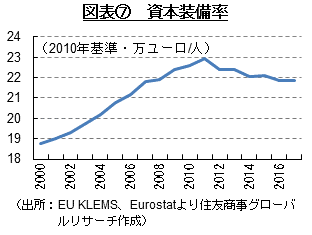
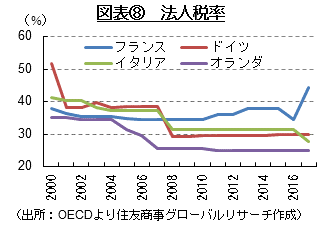
これらを踏まえると、2013年以降、MFPと資本装備率の動きから労働生産性はそれほど向上していないことがわかり、単位労働コストの上昇圧力につながっていないことになる。また、労働生産性がそれほど向上していないため、実質賃金の押し上げ圧力も弱くなり、名目賃金を通じた単位労働コストの上昇圧力も弱めている可能性がある。言い換えると、高付加価値化などによって競争力を高める半面、賃金が上昇することで単位労働コストも上昇するのではなく、低付加価値な分野において競争力を高めているとみられる。
その他、競争力に関連するものに、法人税率がある。法人税は一般的に、企業にとってのビジネスコストとして意識されている。2003~07年に比べて、2013~17年の法人税率が13.4%ポイント低下した。2017年にはドイツよりも低下しており、企業にとってより魅力的なビジネス環境になっている可能性がある。
以上のように、輸出を供給側からみると、MFPよりも名目単位労働コストと法人税率の方が、イタリアの輸出に影響を及ぼしているとみられる。
5. 結論
上記を踏まえると、リーマンショック前と現在の景気拡張期間において、イタリアの経済成長の牽引役は輸出だった。その輸出を需要側からみると、海外需要動向が重要である。
世界銀行『Global Economic Prospects, June 2018』によると、世界経済は2018年に3.1%、2019年に3.0%と堅調に成長する見通しになっている。そのため、イタリアの海外需要も堅調に推移すると想定され、今後輸出が伸びることで、イタリアの経済成長も底堅く推移する可能性が高い。
そこで、懸念されるのは、現在進行中の貿易戦争だ。米国は、鉄鋼・アルミニウムなどの輸入品に追加関税を課し、EUも報復関税を課している。そうなれば、イタリア輸出にとって重要な海外の景気が悪化する恐れがある。
イタリアの輸出動向を確認すると、2013~17年平均で輸出先の上位5か国は、ドイツ(全輸出の12.5%)、フランス(10.5%)、米国(8.2%)、英国(5.2%)、スペイン(4.8%)であった。そのうち、貿易摩擦で注目される米国向け輸出財では、ボイラー及び機械類(22.1%)、自動車及びその部品(10.9%)(以下、自動車)、飲料・アルコール類(4.9%)、医療用品(4.6%)、精密機器(4.1%)のシェアが大きい。
また、同時期のイタリア全輸出のうちの47%は中間財だった。その中間財は、ドイツ向け輸出の8.7%、フランス向けの6.2%、英国向けの6.8%、スペイン向けの8.2%を占めていた。しかし、自動車輸出に限ると、中間財(自動車用部品・原材料など)の存在感は大きい。イタリアのドイツ向け自動車輸出のうちの79.5%は中間財で、フランス向けでは63.6%、英国向けでは63.9%、スペイン向けでは80.5%と、イタリア自動車産業が欧州のサプライチェーンに組み込まれていることを表している。
一方、米国向け全輸出額のうち、アルミニウムは0.4%、鉄鋼は4.1%を占めている。つまり、鉄鋼・アルミニウムより、自動車に追加関税を課す直接的な影響(約2倍)の方が重要である。
具体的に自動車輸出をみると、2014年のイタリアの米国向け自動車輸出額は約26億ユーロだった。イタリアは、フランス・ドイツ・英国・スペインに中間財を9.9億ユーロ輸出し、それらの国で加工・組み立てた自動車が米国に輸出されるので、ドイツなどに関税が課せられればイタリアの中間財輸出にも影響が及ぶ。仮に、米国の自動車輸入が25%減少すれば、イタリアの輸出先トップ4国への中間財輸出は1.3億ユーロ減少するとの計算だ。この中で、ドイツのシェアは79.4%(1.0億ユーロ)と最も大きい。イタリアから米国への直接の自動車輸出額を追加すると(イタリアの自動車関連輸出先トップ5か国では)、イタリアの自動車輸出は7.8億ユーロ減少することになる(イタリアから全世界向け自動車輸出の2.7%、イタリアの全世界向け輸出全体の0.2%)。イタリアの自動車の全輸出のうちの53.2%は上記のトップ5か国向けであった。この結果をみると、7.8億ユーロのうちの13.2%は上位4か国の中間財の間接的な影響であるので、米国への直接的な輸出だけではなく、中間財など他国への輸出を分析に含めることも必要である。仮に米国が自動車の輸入を25%減少すれば、米国による貿易摩擦は、イタリアから米国への輸出とその他の国への輸出の双方に重大な影響を及ぼすとみられる。
次に、先行き懸念が高まっているコンテ政権の政策が輸出にどのような影響を及ぼすのかを考えてみる。まず、コンテ政権の重要政策として、15%個人と20%法人フラット税(注)を設定し、失業者等のために月額780ユーロの最低所得保障制度を導入することがあげられる。20%法人フラット税の恩恵により、製造コストの低下を通じて価格競争力が高まるので、輸出の追い風になると考えられる。
一方で、月額780ユーロの最低所得保障制度の導入によって、今後、名目単位労働コストは上昇する可能性がある。イタリアの非熟練建設労働者の所得(除く所得税)は月額約881ユーロ(約11万円)、専門建設労働者は同約1,084ユーロ(約14万円)である。働かないで受け取れる最低所得保障によって、労働インセンティブが低下し、労働者数は減少すると考えられる。また、最近、コンテ政権は移民の人数を削減しようとしており、これも労働者数を減少させる一因だ。相対的過剰人口(低い給料でも働く労働者)が少なくなるといえる。そのため、必要な人材を確保するためには、企業は給料を上げなければならなくなる。このように、最低所得保障制度の導入によって、賃金を通じて労働コストも上昇する可能性がある。また、仮に給料が上がらなければ、働かないことを選択する人や、最低所得保障を受けながら報告せずに働く人が増える可能性もある。以上のように、労働コストが上昇したり、必要な労働力を確保できなかったりするため、中長期的にみれば、輸出の成長の妨げになりうる。
このため、短期的には世界経済の成長を追い風に輸出が伸びることで、イタリアは経済成長すると期待される。また、法人税率引き下げが実施されれば、それもビジネス環境の改善を通じて、輸出競争力を高めるだろう。しかし、中長期的に、最低所得保障制度の導入によって労働コストが増加し、輸出競争力が損なわれることで、これまで経済成長を牽引してきた輸出が逆に足を引っ張る恐れがあるため、今後のイタリアの政策動向が注目される。
(注)2017年の個人所得税の累進税率は23%から43%までで、法人所得税は27.5%であった。コンテ政権は個人所得税率を一律15%、法人税率を20%に引き下げることを目指している。
以上
記事のご利用について:当記事は、住友商事グローバルリサーチ株式会社(以下、「当社」)が信頼できると判断した情報に基づいて作成しており、作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、当社及び住友商事グループは、その情報の正確性、完全性、信頼性、安全性等において、いかなる保証もいたしません。当記事は、情報提供を目的として作成されたものであり、投資その他何らかの行動を勧誘するものではありません。また、当記事は筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社及び住友商事グループの統一された見解ではありません。当記事の全部または一部を著作権法で認められる範囲を超えて無断で利用することはご遠慮ください。なお、当社は、予告なしに当記事の変更・削除等を行うことがあります。当サイト内の記事のご利用についての詳細は「サイトのご利用について」をご確認ください。
 レポート・コラム
レポート・コラム
 SCGRランキング
SCGRランキング
- 2025年10月31日(金)
『日刊工業新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2025年10月29日(水)
『日刊工業新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2025年10月22日(水)
『日本経済新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2025年10月15日(水)
『日経ヴェリタス』に、当社シニアアナリスト 鈴木 直美が寄稿しました。 - 2025年10月14日(火)
『日刊産業新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。

