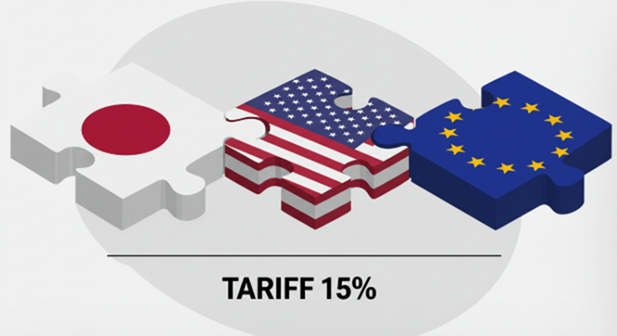日米・米欧関税協議の合意
2025年07月29日
住友商事グローバルリサーチ 経済部
鈴木 将之
米国は、日本とEUと貿易交渉でようやく合意に達した。米国と日本、米国とEUの言い分が現時点で異なっている点に懸念が残るものの、ここ1年弱にわたって世界経済を揺るがしてきた貿易摩擦という大きな不確実性が緩和に向かうことは、前向きに捉えられる材料と言える。
注目点はいくつかあり、1つ目は、相互関税が日本とEU、ともに15%になったことだ。米国から見ると、日本産品もEU産品もともに15%上昇するので、それらの相対価格は変わらない。例えば、日本が25%で、EUが30%だったら、相対的にEU産品が割高になって、それに応じてEU産品の需要が減少する。今回、日本とEUの関税率が同じであり、相対価格が変わらないので、そうした現象は起きにくい。
ただし、米国の実質購買力の低下を通じて、需要を押し下げることになる。関税に応じて輸入財価格が上昇して、米国内物価にも上昇圧力がかかれば、その分だけ米国の需要者の購買力が失われる。つまり、実質購買力の低下を通じて、需要が抑制されることになる。もちろん、関税を再配分政策によって低所得者層などに重点的に支援すれば、そうした需要の落ち込みを軽減できるかもしれない。しかし、そうしたきめ細やかな政策は難易度が高いため、需要は少なからず抑制されることになるだろう。
2つ目は、時間軸のズレが挙げられる。関税がすぐに戻らないという見通しが強まるほど、海外企業が米国内での生産を増やす可能性が高い。ただし、米国内の生産増加といっても、既存設備の稼働率を高めることで対応できる部分はすぐに増産できる。しかし、工場建設などによって生産能力を拡充しなければならないのであれば、相応の時間がかかる。その間、結果的に関税の悪影響を米国内で受けとめる必要がある。
3つ目は、米国企業の競争力が中長期的に低下する恐れがあることだ。米国内ビジネスが15%の関税という下駄を履いて成り立つビジネスに最終的落ち着いてしまっては、米国市場以外では競争力を持たないものになるだろう。製造業が復活する初期段階では、関税による保護も1つの手段であるものの、いつまでも頼っていられない。そうした関税がない中で活動しているほかの国の企業は、生産性や競争力が数段上に高まっている可能性がある。非関税障壁などを理由に関税を引き上げているものの、米国産品は米国市場でしか通用しないものになってしまうリスクもある。
4つ目は、対米投資の拡大が、日本とEUとの合意に至る上で一つの鍵になったことだ。対米投資の拡大は意義があるものの、それはタダでお金をくれることを意味しない。投資は、将来の収益を獲得するために、現在お金を使うことである。そのため、米国ビジネスが成功して利益をあげれば、その一部は投資元に回収される。それは、直接投資収益や証券投資収益の支払いとして、米国外に資金が流出することを意味する。
また、生産活動であれば、それに付随してロイヤルティーなども生じるだろう。それはサービス収支の支払となる。つまり、貿易赤字を削減しようとして海外からの投資を受け入れて米国内で生産しても、サービス収支や第一次所得収支の支払が増える可能性がある。相対的に赤字削減のほうが金額としては大きいとみられるものの、貿易収支やサービス収支は売上高概念に近い一方で、第一次所得収支は利益概念に近いなど、性質が異なることにも注意が必要だろう。
このように、波及経路や時間軸などが複雑なこともあって、米関税政策が最終的にどのような影響をもたらすのかは予想しがたい。足元での暫定的な合意、帰結が中長期的なものと大きく異なることも十分あり得るため、今後とも動向を注視して、その影響を考察していくしかない。
記事のご利用について:当記事は、住友商事グローバルリサーチ株式会社(以下、「当社」)が信頼できると判断した情報に基づいて作成しており、作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、当社及び住友商事グループは、その情報の正確性、完全性、信頼性、安全性等において、いかなる保証もいたしません。当記事は、情報提供を目的として作成されたものであり、投資その他何らかの行動を勧誘するものではありません。また、当記事は筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社及び住友商事グループの統一された見解ではありません。当記事の全部または一部を著作権法で認められる範囲を超えて無断で利用することはご遠慮ください。なお、当社は、予告なしに当記事の変更・削除等を行うことがあります。当サイト内の記事のご利用についての詳細は「サイトのご利用について」をご確認ください。
 レポート・コラム
レポート・コラム
 SCGRランキング
SCGRランキング
- 2025年11月20日(木)
「景気とサイクル」景気循環学会40周年記念号第80号に、当社シニアエコノミスト 鈴木 将之が寄稿しました。 - 2025年11月18日(火)
『日本経済新聞(電子版)』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2025年11月17日(月)
『Quick Knowledge 特設サイト』に、当社シニアエコノミスト 鈴木 将之のQuick月次調査・外為11月レビューが掲載されました。 - 2025年11月13日(木)
『日経ヴェリタス』に、当社シニアエコノミスト 鈴木 将之のコメントが掲載されました。 - 2025年11月11日(火)
『週刊金融財政事情』2025年11月11日号に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行が寄稿しました。