フランスの労働時間からみた消費支出
2018年11月28日
住友商事グローバルリサーチ 経済部ポール エル メディオニ
概要
1980年以降、先進国の労働時間には減少傾向がみられる。フランスの労働時間は1980年から2016年までに13%減少した。労働時間の減少により、自由時間が増加してきた。この現象は、個人消費のどのような要因に影響を及ぼすのだろうか。今回のレポートは、実質消費支出に対する労働時間の影響を分析する。フランスの労働時間は1980年から減少している一方で、同期間の実質消費支出(1人あたり)は増加した。労働時間から計算した自由時間を作ったデータを使い、自由時間が各品目の消費に及ぼす影響を考察した。そこから、企業にとって、労働時間が短縮された場合、どの分野、商品・サービスが成長するのかを把握できる。
1. 消費支出の研究の背景
最近、貿易摩擦の経済成長への影響に関して懸念が高まりつつある。確かに、輸出の寄与度はGDP成長率において大きく、2017年のフランスのGDP成長率(前年比)における輸出の寄与度は0.9%ポイントであった。それは、消費支出の寄与度が0.6%ポイントであったことと比べ、大きさが目立っている。しかし、金額でみると、消費支出は輸出の1.82倍であり、消費支出の経済成長に対する潜在的な寄与度が大きいので、消費支出を理解することは重要だ。
一般的に、消費支出は所得と価格から検討されることが多い。それに加えて、今回は自由時間の消費支出への影響について考察する。仮説として、労働時間が減少すると反対に自由時間は増加するので、例えば、買い物の時間が増えて、結果として消費支出が増加することが考えられる。その他には、レジャーや旅行などに費やす時間も増えることが想定される。そうした消費スタイルの多様化が、ビジネスや産業に変化をもたらすだろう。
こうした仮説を検証するために、分析の対象期間として、1980年(フランソワ・ミッテラン政権成立の1年前)から2016年までをとりあげた。ミッテラン政権樹立後に、労働時間に関する法律が改正されたので、その1年前から分析する。
2. フランスの労働時間と消費支出の動向
フランスの労働時間は、図表①のように、1980年の1638.4時間(1年あたり)から2016年の1422.7時間まで減少している。ただし、常に減少してきたわけではなく、2002年から2008年の間には税制改正の影響もあって、1401.5時間から1447時間へと増加した。均してみれば、1980年から2016年にかけて法改正などの影響もあって、労働時間は減少トレンドを示して来た。
この間、労働時間に関して4つの大きな法律の変更があった。一つ目は1981年にフランソワ・ミッテラン政権が年次有給休暇を4週間から5週間に増やし、週40時間労働制から週39時間労働制に改めたことだ。二つ目は、1998~2002年にジャック・シラク政権が、労働時間を週39時間から週35時間に段階的に減少させたことである。この2つの改革後に、労働時間はすぐに減少した。三つ目に、2003年にジャック・シラク政権は週35時間の政策として、残業がしやすくなるよう労働法を成立させた。また、四つ目として、2007年からニコラ・サルコジ政権が成立させた、残業所得に対する税金と社会保険料を免除する労働法の改正があげられる。
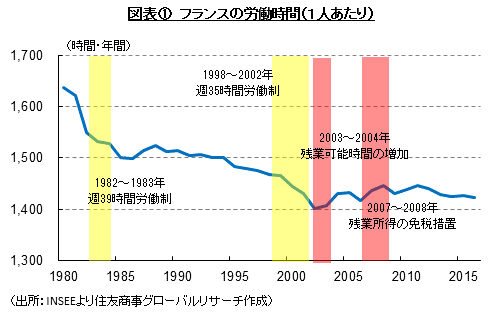
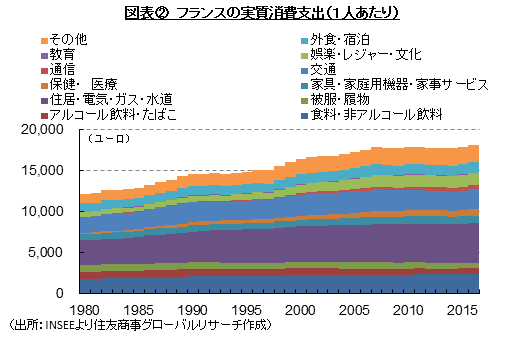
図表②にように、フランスの実質消費支出(1人あたり)は1980年から2016年にかけて59%増加した。費目別にみると、被服・履物とアルコール飲料・たばこの減少に対して、他の費目は増加している。
これらの費目を「①100%以上増加、②0~100%増加」の2つに分けてみると、①娯楽・レジャー・文化、通信と保健・医療はそれぞれ178%、1,321.1%、342.6%増加した。一方、②食料・非アルコール飲料、住居・電気・ガス・水道、家具・家庭用機器・家事サービス、交通、教育、外食・宿泊、その他は①の分類ほど増加しなかった。
消費支出額が大幅に増えた①の分野では、社会・経済の構造的な変化の影響が強かったといえる。例えば、1980年から2016年にかけて保健・医療が342.6%増加した理由として、フランスの75歳以上人口が1980年の301万人から2016年の599万人に増加したことがあげられる。また、同期間に、通信が1,321.1%増加した背景には、コンピューターやスマートフォンなどの普及という技術的な変化があった。
そうした要因以外で、労働時間が減った一方で消費支出は増えてきた背景は何か、について考察する。
3.自由時間と消費支出の関係
ここでは、労働時間と消費支出を考える上で、労働時間と表裏一体の関係にある自由時間に注目してみた。自由時間として、睡眠時間、仕事の時間、家事時間、食事の時間等を除いた消費に充てられうる時間を対象とした。
これまで法改正によって労働時間が削減されてきた一方で、自由時間は増加してきた。それによる消費者のライフスタイルの変化を通じて、消費に影響が及び、ビジネスにも変化をもたらしてきたと考えられる。実際、図表③のように、これまで自由時間とともに消費支出は増加してきた。
ただし、品目によって増減の方向性は異なっていた。図表④のように、消費費目別に相関係数を計算したところ、自由時間は食料・非アルコール飲料、住居・電気・ガス・水道、家具・家庭用機器・家事サービス、保健・医療、交通、通信、娯楽・レジャー・文化、教育、外食・宿泊、その他の支出と正の相関関係があった。その一方で、アルコール飲料・たばこ、被服・履物とは、負の相関関係がみられた。これより、自由時間と消費支出の関係について、全体的な動きとともに、個別の費目・商品などにも焦点を当てる必要があると考えられる。
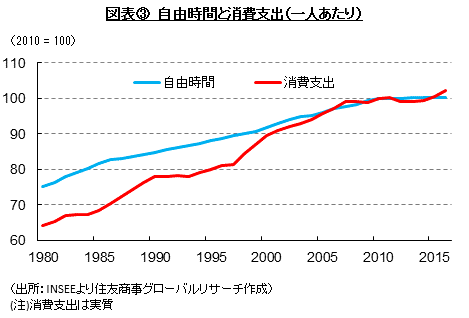
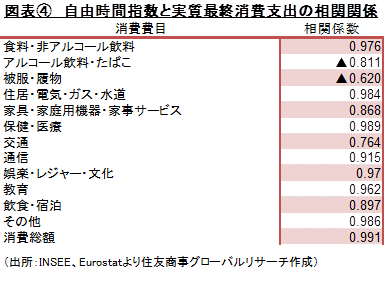
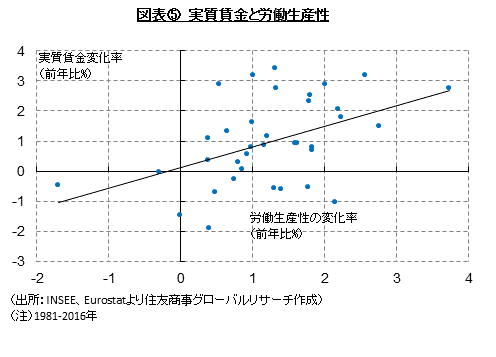
もちろん、一般的に、自由時間の増加による労働時間の減少によって、所得の低下を通じて、消費が減少する可能性が考えられる。労働時間の減少は、企業の生産活動の下押し要因になりうるからだ。しかし、過去をみると、図表⑤のように、自由時間が増える一方で、賃金は上昇してきた。これは、自由時間が増えても、その一方で労働生産性が向上して、賃金が上昇してきたためだ。これを踏まえて、以下では自由時間と消費の関係に注目する。
4.自由時間の消費への影響力
ここでは、自由時間が消費支出に及ぼす影響について考えるために、消費関数を推計してみた。被説明変数を1人あたり実質消費支出額()とし、説明変数には実質賃金(W)、自由時間(H)、不確実性指標(U)(失業率から計算した)を用いた。推計式はとした。ただし、は前年差で、はその他要因を表す。
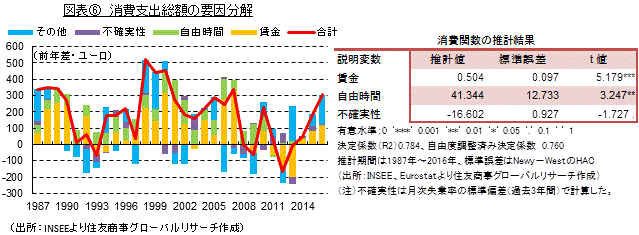
図表⑥の推計結果より、自由時間の寄与度が大きいことから、自由時間の増加が、一般的に想定される賃金に次いで重要な要因であることが読み取れる。特に、2000年から2002年にかけて労働時間を短縮する法改正が、自由時間の増加を通じて消費を押し上げていたことが注目される。このように、自由時間の増減が消費スタイルに大きな影響を及ぼしてきたことが確認できる。
この結果に基づくと、1日あたりの自由時間が1分増加した場合、フランス全体の1年の消費額は約27億ユーロ(約3,422億円、消費総額の0.2%)増加する計算になる。この影響をみるとき、労働時間が減少した時点の前後で、消費パターンが変化すると考えられる。
ここでは、週35時間労働制が導入される前の1997~98年と、その後の2002~03年を比べてみた。労働時間は1997~98年平均の1471.5時間から2002~03年の1404.2時間へと4.5%減少していた。図表⑦は、消費費目のシェアについて、横軸は2002~03年平均の消費額に占めるシェア、縦軸は1997~98年平均と2002~03年平均の変化(変化分)を示したものである。
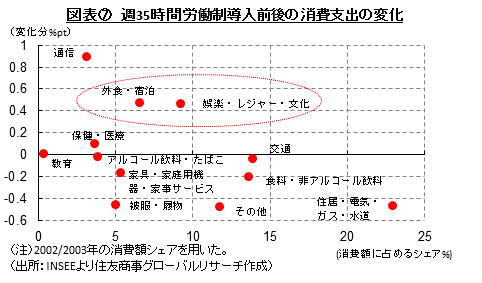
シェアが増加した費目は通信(0.9%ポイント)、外食・宿泊と娯楽・レジャー・文化(0.5%ポイント)、保健・医療(0.1%ポイント)であり、反対に減少したのは住居・電気・ガス・水道、被服・履物(▲0.5ポイント)、食料・非アルコール飲料(▲0.2%ポイント)と家具・家庭用機器・家事サービス(▲0.2%ポイント)だった。この結果より、旅行やレジャーと関係が強い費目の消費シェアが増加した一方で、日常生活と関係が強い費目のシェアが減少したと言える。労働時間が減少したことで自由時間が増加したため、旅行やレジャーと関係が強い費目の消費シェアが増加したのは、前項1.で述べた仮説と整合性があるといえる。
次に、費目の中でどの商品やサービスが増加するのかに焦点をあてる。まず、通信については、労働時間の変化の前後で、消費額シェアの変化分が非常に大きかった。ただし、通信のうち自宅電話および携帯電話、インターネットアクセスが全体の約90%を占めていた。1999年のフランス人口のうちインターネットにアクセスしている人は7.7%であったが、2003年には33.9%まで増加した。これは自由時間増加の影響というよりも、パソコンや携帯電話の普及など、技術進歩の恩恵が大きかったと考えられる。
図表⑧は、娯楽・レジャー・文化の商品・サービスの1997~98年平均と2002~03年平均のシェアの変化である。他の分野と比較すると、他の分野と比較すると、娯楽・レジャー・文化の商品・サービスの種類の増加と消費シェアの増加が際立っていた。
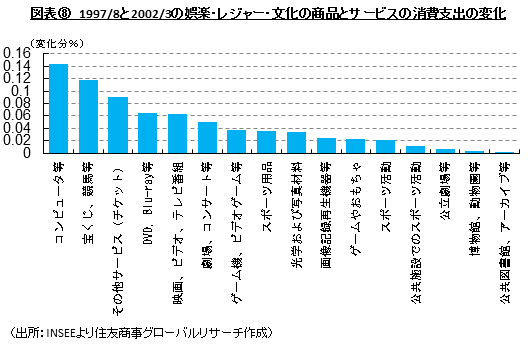
この結果をみると、宝くじなど賭け事やコンピューター等のデジタル系商品が増加した。もちろん、技術の進歩の影響もあるものの、自由時間が増加したことで、これらの商品を使える時間も増えたと考えられる。また、文化と芸術に関連する活動の様々な商品・サービス、スポーツに関連する商品・サービスのシェアも増加した。
図表⑨は、外食・宿泊について、1997~98年平均と2002~03年平均のシェアの変化である。レストランとファーストフードが増加した。自由時間の増加とともに食事に充てられる時間が増えたことで、レストランに行く機会が増加したと考えられる。観光宿泊施設、ホテル、キャンプのサービスも増加した。労働時間が減少したことで、旅行やホテル、キャンプ等のサービス消費が増加したとみられる。2004年にフランス人は国内旅行の時に、全体の宿泊のうち61.5%は個人の別荘、家族・友人宅等を利用しており、38.6%がホテル、キャンプ等であった。つまり、観光について考えるときには、一般的なホテルに加えて、他の宿泊方法をビジネスの視野に入れる必要があるといえる。
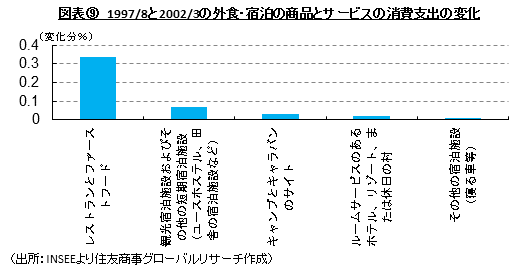
同じように、図表⑩はその他の商品の1997~98年の商品・サービスの消費の平均と2002~03年の商品・サービスの消費の平均のシェアの変化(前年差)である。この中で、3つの傾向がみられる。
1つ目は、交通・旅行である。キャンピングカー、中古車、軽油、航空輸送、遊覧船、鉄道輸送、倉庫保管及び補助輸送サービスが増加した。上記と同じように、労働時間が減少すると、旅行する機会が増加し、ホテルや宿泊施設に行くために自動車、鉄道、飛行機等の利用が増加するためである。
2つ目は旅行・休暇・休憩時の飲食である。果物、魚、ペストリー、チョコレート、清涼飲料水、ソフトドリンク、シャンパン等の消費のシェアが増加した。特に、果物、魚、ペストリー、清涼飲料水等は休日や旅行の時によく消費される傾向がある。
3つ目は身の回り・くつろぎ関連である。香水、バスアメニティ、美容トリートメント、メガネは増加した。自由時間が増加し、自分自身をケアする時間も増えるので、美容関連商品の消費が増加するとみられる。
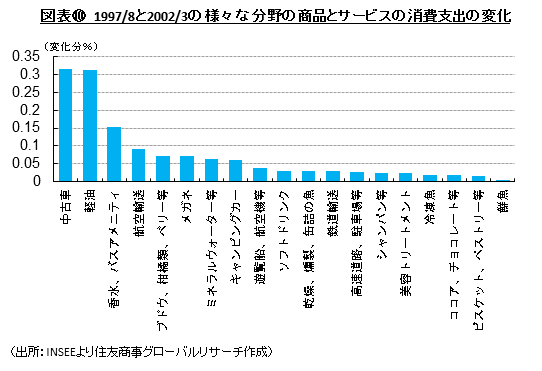
5. 結論
以上のように、自由時間と消費支出の関係を考察してきた。フランスの1日あたりの自由時間は1980年の217分から2016年の290分に増加した一方で、実質最終消費支出は同期間に59%増加した。これまで労働生産性の向上と賃金上昇という裏付けもあって、自由時間が1分増えれば、フランスの消費額は年間約27億ユーロ増える可能性がある。もちろん、高齢化の進展や電子商取引の拡大など構造変化もあるものの、自由時間と消費の関係に注目する意義があると考えられる。
仮にどこかの国で労働時間を短縮する法律が導入されて自由時間が増えたとき、どのようなビジネスの商品・サービスが成長する可能性があるかを考えるヒントになる。上記のフランスの結果に基づくと、自由時間が増加すれば(労働時間の減少)、フランス人は自宅で、あるいは外で、食事を楽しむ(レストラン、果物、魚、ペストリー、ソフトドリンク等)。例えば、特に日が長い夏など、フランスでは晩御飯の前に酒を飲み、ピーナツや果物、ピスタチオ等を食べる「アペリティフ」という食事を楽しむ。その他、劇場、図書館等の文化施設を訪れ、スポーツ活動をする(劇場、プライベートコンサート、博物館、動物園、自然公園、スポーツ協会、フィットネスセンター、スポーツイベント等)。平日に早めに仕事が終われば、展覧会に行ったり、スポーツの活動に参加したりすると考えられる。また、移動の結果から、旅行をする人が多いということも理解できる(セーリングボート、モーターボート、鉄道輸送、航空輸送、キャンピングカー等)。また、宿泊でみられたように、フランスの旅行消費では、一般的なホテルに加えて既に家族・友人宅などが多く利用されている。そうした分野をビジネスにしていることも重要な視点になるだろう。その一方で、自分のための活動もある。例えば、自宅でデジタル系の商品を使って趣味の時間を楽しむ(コンピューター、ビデオゲーム、映画等)。また、くつろぎの時間を過ごすことも想定される(バスアメニティ、美容トリートメント、メガネ等)。自分の時間が必要なだけではなく、グループ活動や友人、家族、他の人と時間を過ごすことは文化的に重要なことである。それにより、この「社会的な」「グループ活動」の行動を念頭に置いたビジネスを展開することが重要である。例えば、シングルプレイヤーコンピュータゲームに加えて、グループで、他の人や友達も参加してできるゲームを提供していくのが良いと考えられる。
上記の分野の商品・サービスで消費需要が拡大しうるため、労働時間を短縮する法律が導入されれば、新しいビジネス領域として、これらの分野に成長の可能性が広がるだろう。
現在、日本でも生産性革命とともに働き方改革が進んでいる。その一方で、第4次産業革命などの技術進歩もあり、経済・社会が大きく変化している。そうした中で、フランスの経験から得られることは、日本企業にとっても有用な示唆になると考えられる。
以上
記事のご利用について:当記事は、住友商事グローバルリサーチ株式会社(以下、「当社」)が信頼できると判断した情報に基づいて作成しており、作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、当社及び住友商事グループは、その情報の正確性、完全性、信頼性、安全性等において、いかなる保証もいたしません。当記事は、情報提供を目的として作成されたものであり、投資その他何らかの行動を勧誘するものではありません。また、当記事は筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社及び住友商事グループの統一された見解ではありません。当記事の全部または一部を著作権法で認められる範囲を超えて無断で利用することはご遠慮ください。なお、当社は、予告なしに当記事の変更・削除等を行うことがあります。当サイト内の記事のご利用についての詳細は「サイトのご利用について」をご確認ください。
 レポート・コラム
レポート・コラム
 SCGRランキング
SCGRランキング
- 2025年7月4日(金)
日本国際平和構築委員会『7月研究会』に、当社シニアアナリスト 足立 正彦がパネリストとして登壇しました。 - 2025年6月27日(金)
日経QUICKニュース社の取材を受け、当社シニアエコノミスト 鈴木 将之のコメントが掲載されました。 - 2025年6月27日(金)
『日本経済新聞(電子版)』に、当社シニアエコノミスト 鈴木 将之のコメントが掲載されました。 - 2025年6月16日(月)
『時事通信』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行が寄稿しました。 - 2025年6月13日(金)
『日刊工業新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。

