「フランス、英国、カナダなどが9月にパレスチナを国家承認する意向」 中東フラッシュレポート(2025年7月号)
調査レポート
2025年08月21日
住友商事グローバルリサーチ 国際部
広瀬 真司
2025年8月8日執筆
1.パレスチナ:フランス、英国、カナダなどが9月にパレスチナを国家承認する意向
7月29日、フランス、カナダ、オーストラリアなどを含む15か国は、9月に開催予定の第80回国連総会(UNGA 80)に向けて、パレスチナ国家を未承認の国々に対し承認を呼びかける共同声明を発表した。声明には、2024年にパレスチナを国家として承認したスペイン、ノルウェー、アイルランドも名を連ねている。共同声明では、イスラエルとパレスチナの二国家が共存する「二国家解決」への揺るぎない支持が再確認されており、イスラエルと国交を持たない国々に対しては国交の樹立を促す内容も盛り込まれている。
7月下旬以降、フランス、英国、カナダ、ポルトガルなどがUNGA 80においてパレスチナ国家を承認する方向で検討・調整を進めていると報じられている。すでに国連加盟国の140か国以上がパレスチナを国家として承認しているため、仮に数か国が新たに承認に加わっても、現状が劇的に変化するわけではない。しかし、フランスと英国はいずれも国連安全保障理事会(UNSC)の常任理事国であり、カナダも含めた3か国はG7メンバーであることから、国際社会に与える影響力は小さくない。UNSC常任理事国のうち、中国とロシアはすでにパレスチナ国家を承認しており、今回の動きによって米国の孤立が一層際立つ格好となる。
なお、日本は依然としてパレスチナを国家承認しておらず、米国が強く反対していることもあり、現時点で本件に関する明確な立場を示していない。
2.パレスチナ:国際社会がガザの惨状に声を上げる
7月21日、日本、カナダ、英国、フランスを含む28か国の外相とEU委員は、ガザ地区における戦闘の即時終結を求める共同声明を発表した。声明では、イスラエル政府による現地での援助提供のモデルについて「危険であり、不安定さを助長し、ガザの人々から人間としての尊厳を奪っている」と強く非難した。また、イスラエル政府が国連機関や人道支援NGOによる従来の支援活動を妨害していると批判し、パレスチナ人に対する恒久的な強制移住の動きに対しても強い懸念を示したうえで、それが国際人道法に違反する可能性があると指摘した。さらに、東エルサレムおよびヨルダン川西岸におけるユダヤ人入植地の建設加速、ならびに入植者によるパレスチナ人への暴力の増加についても懸念を表明した。
これに対し、イスラエル外務省の報道官は「現実から乖離しており、ハマスに誤ったメッセージを送ることになる」、として声明に強く反発。ハッカビー駐イスラエル米国大使も「(声明は)残忍なハマスではなく、イスラエルに圧力をかけている」、「イスラエルを非難するのは理不尽だ」と述べ、共同声明を非難した。
3.シリア:南部スウェイダでのドルーズ派とベドウィン族衝突に政府軍とイスラエルが介入
7月13日、シリア南部スウェイダにおいて、ドルーズ派民兵組織とスンニ派ベドウィン部族との間で武力衝突が発生した。翌14日には、シリア暫定政権が治安部隊を派遣して事態の鎮静化を図ったが、戦闘は激化し、イスラエルがドルーズ派住民の保護を名目にシリア領内への越境空爆を実施。16日には、イスラエルはダマスカスの国防省および大統領官邸周辺を空爆し、3人が死亡、34人が負傷したと報じられている。
7月19日、バラック米シリア担当特使(兼駐トルコ大使)は、自身のSNSで「シリア軍とイスラエル軍の間で停戦が成立した」と発表した。同日、シリア暫定政府も停戦を宣言し、すべての関係当時者に対して対話と戦闘停止を呼びかけた。シリア人権監視団は、衝突による死者が1,000人を超えたとの見解を示している。
トランプ政権は、2024年末のアサド政権崩壊後に成立したシャラア暫定政権に対し、制裁の段階的解除などを通じて支援する意向を示している。一方、イスラエルは、かつてアルカイダ(Al-Qaeda)系組織に関与し、イスラム過激派の一員として活動していたシャラア氏が率いる新政権に対する警戒を緩めておらず、引き続きシリアへの軍事行動や一部地域の占領を継続している。これにより新政権の安定が損なわれ、地域全体の安全保障に悪影響を及ぼす懸念が高まっている。
2025年に入ってドルーズ派やアラウィー派との衝突、キリスト教会への攻撃が相次いでおり、シャラア政権にとってシリア国内での宗派間の暴力の抑制や少数派コミュニティの保護は喫緊の課題となっている。
4.米国:相互関税率の修正と中東・北アフリカ諸国
7月31日、トランプ米大統領は、2025年4月に発表した相互関税制度の修正を行う大統領令に署名し、米ホワイトハウスは米国への輸出品にかかる新たな関税率を発表した。新たな関税率は8月7日から適用される。中東・北アフリカ地域で、最低税率の10%より高い関税率が設定された国は、以下の8か国。
シリア:41%(4月発表時41%)、イラク:35%(同39%から引き下げ)、リビア:30%(同31%から引き下げ)、アルジェリア:30%(同30%)、チュニジア:25%(同28%から引き下げ)、ヨルダン:15%(同20%から引き下げ)、 イスラエル:15%(同17%から引き下げ)、トルコ:15%(同10%から引き上げ)。
最も高い税率が適用されたのはシリアであり、今回発表された全対象国の中で最高の税率である。トランプ政権はここ数か月、シリアの復興支援を助ける目的で対シリア制裁を段階的に解除する動きを見せてきたため、この動きとは矛盾するが、長期間制裁下にあったシリアと米国との貿易額は極めて小さく、シリアの全輸出に対する対米輸出の割合も低いため、実質的な影響は限定的と考えられる。同じく高い税率が適用されたイラクやリビアに関しては、原油や石油製品などエネルギー関連が米国への輸出の9割以上を占めており、それらは今回の相互関税の適用対象外であることから、これらの国に関しても経済的な影響は限定的とみられる。
5.米国・バーレーン:バーレーンのサルマン皇太子兼首相の米国訪問
7月16日、バーレーンのサルマン皇太子兼首相は米ホワイトハウスを訪れトランプ大統領と会談し、米国に総額170億ドル以上を投資する計画を発表した。主な契約として、約70億ドル規模と言われるバーレーン国営航空ガルフ・エアによるボーイング社製B787型機12機(6機の追加オプションあり)およびGE製エンジン40基の購入や、オラクルやシスコからのサーバー導入、アルミニウム生産、人工知能(AI)分野への投資などに関する合意がなされた。また両国は、民生用原子力協力覚書(NCMOU)にも署名した。滞在中、サルマン皇太子兼首相は、ヘグセス国防長官および米通商代表部(USTR)のグリア代表とも個別会談を行った。
バーレーンには米海軍第5艦隊が駐留しており、2020年にはイスラエルとの国交正常化(アブラハム合意)にも署名するなど、バーレーンは米国にとって地域の要の同盟国である。2025年末までには、バーレーンのハマド国王がワシントンを訪問する予定である。
6.イラク情勢
- 7月14~16日にかけて、クルディスタン自治区(KRI)内の油田に対して、親イラン民兵組織によるものとみられる攻撃が相次ぎ、人的被害は報告されていないものの、日量20万バレル(bpd)を超える石油の生産停止という深刻な被害が生じた。KRI内の米国企業が関与する油田は、米軍基地と同様に、従来から親イラン民兵組織の攻撃対象となってきた。また、イラク中央政府とクルディスタン自治政府(KRG)との間で、KRIで産出する石油に関する取り決めを巡る対立が続いており、KRGへの圧力を加える意図があったとの見方もある。
- 7月16日、イラク内閣はKRGとの暫定合意を承認した。合意内容によれば、KRIは28万bpdの石油を生産し、そのうち23万bpdをイラク国営石油販売会社(SOMO)に供給する。その見返りとして、中央政府はKRGに1バレル当たり16米ドルを支払い、石油輸出による収入はイラク財務省に預けられる。この合意により、同財務省はKRGの公務員給与支払いのための資金拠出が可能となった。
- 7月21日、トルコ政府はイラクのキルクークとトルコのジェイハンを結ぶ石油パイプライン(ITP)に関する二国間協定を終了すると発表した。ITPを巡っては、過去のKRIからの石油輸出に関し、トルコ政府が国際仲裁で賠償を命じられた問題があり、これを受けてトルコ側は2023年3月以降、当該パイプラインの運用を停止している。今回の協定終了通告は1年前通知に基づくものであり、2026年7月に正式に効力を失う見通しである。
- 6月のイラク原油輸出詳細:輸出額67.0億ドル、輸出量日量329.6万バレル、平均単価67.74ドル/バレル。
7.リビア情勢
- 7月7日、石油大手BPは、2025年第4四半期までにトリポリの事務所を再開しリビアでの事業を再開する計画であると発表。同日、シェルも油田開発に関する技術的・経済的実現可能性調査の実施に合意と発表。
- 7月22日、東部リビアを実効支配するハフタル将軍の息子で後継者候補とされるサダム・ハフタル氏がトルコを訪問し、ギュレル国防相と会談した。同氏は4月にもトルコを訪れている。トルコはこれまで、ハフタル将軍と対立する西部の国民統一政府(GNU)と強固な関係を維持してきたが、近年、国内におけるGNUへの支持の低下やハフタル勢力の拡大を受け、東部政府との関係構築にも乗り出している。
- 7月23日、ブーロス米アフリカ担当特使がトリポリを訪問し、ドゥベイバGNU首相、メンフィー大統領評議会議長ら政府高官と会談し、二国間の戦略的協力の強化やパレスチナ問題などについて意見を交わした。ブーロス特使はリビア東部のベンガジも訪れ、ハフタル将軍とも会談を行った。
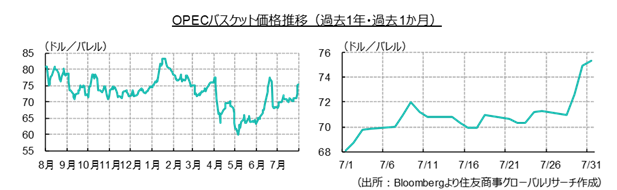
以上
記事のご利用について:当記事は、住友商事グローバルリサーチ株式会社(以下、「当社」)が信頼できると判断した情報に基づいて作成しており、作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、当社及び住友商事グループは、その情報の正確性、完全性、信頼性、安全性等において、いかなる保証もいたしません。当記事は、情報提供を目的として作成されたものであり、投資その他何らかの行動を勧誘するものではありません。また、当記事は筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社及び住友商事グループの統一された見解ではありません。当記事の全部または一部を著作権法で認められる範囲を超えて無断で利用することはご遠慮ください。なお、当社は、予告なしに当記事の変更・削除等を行うことがあります。当サイト内の記事のご利用についての詳細は「サイトのご利用について」をご確認ください。
 レポート・コラム
レポート・コラム
 SCGRランキング
SCGRランキング
- 2026年1月7日(水)
『ブレーンズ』2026年1月7日・1月14日合併号(No.2608)に、当社社長 横濱 雅彦が開催した『2026年の世界情勢・経済見通し』説明会の内容が掲載されました。 - 2026年1月6日(火)
『日本経済新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2025年12月27日(土)
『日経ヴェリタス』に、当社シニアアナリスト 鈴木 直美のコメントが掲載されました。 - 2025年12月25日(木)
『鉄鋼新聞』に、当社社長 横濱 雅彦が開催した『2026年の世界情勢・経済見通し』説明会の内容が掲載されました。 - 2025年12月24日(水)
『日本経済新聞(夕刊)』に、米州住友商事会社ワシントン事務所長 文室 慈子が寄稿しました。

