「オーストラリアとニュージーランドもパレスチナの国家承認に言及」 中東フラッシュレポート(2025年8月前半号)
調査レポート
2025年08月22日
住友商事グローバルリサーチ 国際部
広瀬 真司
2025年8月19日執筆
1.イスラエル:退役軍高官らがトランプ米大統領宛の公開書簡を発表
8月4日、「イスラエルの安全保障のための司令官たち(CIS)」は、ネタニヤフ首相に対してガザ戦争の終結への圧力をかけるよう、トランプ米大統領に求める公開書簡を発表した。署名したのは、イスラエルの諜報機関であるモサドおよびシンベトの元長官(3人の元モサド長官と5人の元シンベト長官)、元イスラエル軍参謀総長3人(うち1人は元首相、1人は元国防相)など、退役した国防・外交当局の高官を含む550人以上である。
書簡では、ガザのイスラム主義組織ハマスはもはやイスラエルにとって戦略的脅威ではなく、軍事的手段で達成可能な二つの目標(ハマスの軍事部門と統治機構の解体)はすでに達成済みであると指摘している。さらに、最も重要な三つ目の目標である「人質全員の解放」は軍事力ではなく合意によってのみ実現可能であり、残存するハマス幹部の追跡よりも、一刻を争う人質救出を優先すべきだと主張している。
その上で、トランプ大統領に対し、戦争終結、人質全員の解放、そしてガザおよびパレスチナ全体に苦難をもたらす事態の収束を求めた。また、戦後には改革されたパレスチナ自治政府がハマスに代わる現実的選択肢を住民に提供できるよう、地域的・国際的枠組みの構築を呼びかけた。
2.イスラエル:政府がガザ市の制圧計画を承認
8月8日、イスラエル政府はガザ地区の中心都市であるガザ市を制圧する計画を承認した。ネタニヤフ首相はその目的を「ガザをハマスから解放するため」と説明し、記者会見で「戦争終結のための5原則」を提示した。その内容は、①ハマスの武装解除、②人質全員の帰還(生死を問わず)、③ガザの非武装化、④イスラエルによる治安管理、⑤非ハマス・非パレスチナ自治政府の文民政府の設置である。イスラエルによる直接統治の可能性は否定した。
しかし、ガザにおける戦線拡大は人質の命を危険にさらす可能性があるとして、軍幹部や人質家族の間で反対の声が強まっている。イスラエル軍のザミール参謀総長も作戦に反対の意向を示した。周辺アラブ諸国も反発を表明し、英国のスターマー首相はネタニヤフ首相に対し「再考を強く求める」と非難。さらにドイツのメルツ首相は、ガザで使用される可能性のある軍事装備品の対イスラエル輸出を当面停止すると表明するなど、イスラエルは国内外から強い批判に直面している。
3.パレスチナ:オーストラリアとニュージーランドも国家承認に言及
8月11日、オーストラリアのアルバニージー首相は、9月の第80回国連総会においてパレスチナを国家承認すると発表した。7月にはフランス、英国、カナダなど主要国が相次いで同総会でのパレスチナ国家承認方針を表明しており、今回の動きはそれに続くものである。背景には、ガザにおける人道危機への国際的批判の高まりがあり、ネタニヤフ政権への圧力強化が狙いとみられる。同日、隣国ニュージーランドのピーターズ外相もパレスチナの国家承認を検討していると述べた。
すでに国連加盟国の約4分の3にあたる145か国以上がパレスチナを国家承認しているが、G7を含む主要西側諸国はこれまで承認を保留してきた経緯がある。ただし、主要国がパレスチナ承認を表明しても、それが直ちに現地の状況を大きく変えるわけではない。パレスチナには自治政府が存在するが、ガザでの影響力はほとんどなく、ヨルダン川西岸地区においても国境はすべてイスラエルが管理し、空港も軍隊も通貨も持たない。現実にはイスラエルが大半の地域を軍事的に占領しており、国家運営の基盤は極めて脆弱である。今回の承認方針は「二国家解決」を否定するネタニヤフ政権への政治的圧力の意味合いが強いが、その実効性については不透明である。
4.エジプト:上院議員選挙の実施
8月4~5日、エジプトで上院議員選挙の投票が行われた。有権者数は約6,933万人。上院は任期5年・定数300議席で構成され、そのうち100議席は大統領任命、100議席は小選挙区制、残り100議席は比例代表制で選出される。比例代表枠については、与党中心の「国民統一リスト」のみが候補者リストを提出し、対立リストはなかったため、リスト掲載の100人が全員当選した。この結果、次期上院も政府支持派が圧倒的多数を占める見込みとなった。
エジプトの上院は2019年の憲法改正で設置された諮問機関であり、立法権は下院に属するため、選挙自体への注目度は高くなかった。投票率は17.1%と低水準だったが、前回(14.2%)からは約3ポイント上昇しており、特に若年層の投票率が上がったことが一因とされる。
5.イラン:4桁のデノミを計画
8月3日、イラン議会の経済委員会は、通貨リアルの額面を4桁切り下げるデノミネーション計画を支持した。この計画が議会で可決され、さらに護憲評議会で承認されれば、現在の1万リアルは1リアルに変更される。リアルは過去10年で、1ドル≒3万リアルから100万リアルへと急落しており、この措置によりリアル建て取引の簡素化が期待されている。デノミ計画は、第1期トランプ政権が対イラン制裁の再発動を発表した2018年の翌年、2019年に提案されたが、その後棚上げされていた。過去には、トルコが長年のインフレを経て2005年に自国通貨リラの6桁のゼロを削除し、100万トルコ・リラを1新トルコ・リラに切り替えた例がある。
6.英国・フランス・ドイツ:対イラン制裁の再発動を検討
8月8日、英国、フランス、ドイツ(E3)の外相は、8月末までにイランが核問題の外交的解決に応じない場合、あるいはE3が提案するスナップバック期限の延長に同意しない場合には、国連制裁を再発動する「スナップバック」を実施する用意があるとして、グテーレス国連事務総長および国連安全保障理事会に共同書簡を送付した。「スナップバック」とは、イランが2015年に米国、英国、フランス、中国、ロシア+ドイツ(P5+1)と結んだ核合意(JCPOA)の重大違反を犯した場合、合意に基づいて解除された国連制裁を自動的に再発動する仕組みであり、常任理事国の拒否権が行使できない点が特徴である。
E3の共同書簡に対し、イランの元外相のモッタキ議員(駐日大使経験があり、2017年に旭日大綬章を受賞)は、もしスナップバックが発動され国連制裁が再開された場合、イラン議会はJCPOAからの離脱および核不拡散条約(NPT)からの脱退を検討する可能性があると警告した。
7.イラク情勢
- 8月2日、当局はイラク国内の現金の約92%が銀行システム外に存在していると発表した。専門家は、長年にわたる政情不安、国際制裁、経済不安、銀行破綻や資産差し押さえなどの影響で、国民が金融機関を信頼していないことが主因だと分析している。加えて、非効率性やデジタルインフラの欠如も、この傾向を一層強める要因となっている。
- 8月9日、イスラム教シーア派の聖地ナジャフとカルバラを結ぶ道路で水処理施設から塩素ガスが漏洩し、巡礼者600人以上が一時的に病院へ搬送された。イラクでは老朽化したインフラ施設が多く、安全基準が十分に守られていないため、大規模な死傷事故が散発的に発生している。
- 8月11日、イラク政府は「現地の気候・環境条件に適していない」として、中国製のトヨタ車の輸入を禁止した。
- 8月13日、サウジのジャミール・モーターズが、中国・奇瑞汽車傘下ブランド「OMODA & JAECOO」とイラクにおける販路拡大契約を締結した。両社にとってイラク市場への初進出となる。イラクでは、若年層やテクノロジーに精通した消費者を中心に、新エネルギー車(NEV)の需要が急速に拡大しており、販売は2025年第4四半期から開始される予定である。
- イラク財務省の発表によれば、2025年上半期の総収入のうち89%が石油収入で占められており、その依存度は依然として極めて高い。イラク南部のバスラ港から輸出される原油の75%は中国とインド向けである。
8.リビア情勢
- 8月1日、国民統一政府(GNU)のドゥベイバ首相はトルコを訪れ、エルドアン大統領およびイタリアのメローニ首相との3か国首脳会談を実施した。協議では、地中海地域の安全保障・エネルギー協力、不法移民問題、経済統合などが議題となり、ドゥベイバ氏はこの3か国にカタールを加えた4か国協議の開催を提案した。
- 8月9日、リビア東部に拠点を置く「リビア国民軍(LNA)」のハフタル司令官は、ベンガジで行われたリビア軍創設85周年記念式典において、LNAの再編と近代化を目指す「Vision 2030」を発表した。
- 8月11日、近年健康不安が伝えられるハフタル司令官(81歳)は、末息子で後継者候補と目されてきたサダム・ハフタル中将(34歳)をLNA副司令官に任命した。これに対し、LNAと同じく東部に拠点を置く代表議会(HoR)のサーレハ議長や、国家安定政府(GNS)のハマド首相は祝意を表した。
- サダム・ハフタル氏は1991年ベンガジ生まれで、7人兄弟の末息子。米国とリビアの二重国籍を持ち、父親(ハフタル司令官)が米国に亡命していた間、ベンガジで母親に育てられた。「サダム」という名はイラクのサダム・フセイン大統領にちなんで命名された。同氏はLNA内で最大かつ最も影響力のある武装集団の一つ「ターリク・ビン・ジヤード旅団(TBZ)」を率いてきたが、同旅団は殺害、拷問、虐待、強姦などの残虐行為でアムネスティー・インターナショナルから非難されている。また、麻薬密輸、人身売買、拉致・誘拐などへの関与疑惑も報じられている。
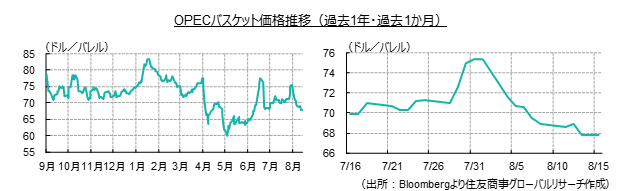
以上
記事のご利用について:当記事は、住友商事グローバルリサーチ株式会社(以下、「当社」)が信頼できると判断した情報に基づいて作成しており、作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、当社及び住友商事グループは、その情報の正確性、完全性、信頼性、安全性等において、いかなる保証もいたしません。当記事は、情報提供を目的として作成されたものであり、投資その他何らかの行動を勧誘するものではありません。また、当記事は筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社及び住友商事グループの統一された見解ではありません。当記事の全部または一部を著作権法で認められる範囲を超えて無断で利用することはご遠慮ください。なお、当社は、予告なしに当記事の変更・削除等を行うことがあります。当サイト内の記事のご利用についての詳細は「サイトのご利用について」をご確認ください。
 レポート・コラム
レポート・コラム
 SCGRランキング
SCGRランキング
- 2026年2月9日(月)
『時事通信』に、当社シニアアナリスト 鈴木 直美のコメントが掲載されました。 - 2026年2月7日(土)
『日本経済新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2026年1月31日(土)
『日本経済新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2026年1月21日(水)
『日経ヴェリタス』に、当社シニアアナリスト 鈴木 直美が寄稿しました。 - 2026年1月15日(木)
『朝日新聞デジタル』に、米州住友商事会社ワシントン事務所調査部長 渡辺 亮司のインタビュー記事が掲載されました。

