長短金利操作付き量的・質的金融緩和の導入から1年
概要
長短金利操作付き量的・質的金融緩和(YCC)の導入決定から約1年が経ち、そろそろ緩和策の効果が評価される時期になった。現状では、景気回復への貢献は評価できる一方で、足元ではデフレマインドの払拭が思うように進んでおらず、インフレ目標の達成は道半ば。9月初めには地政学リスクの高まりから長期金利が低下、YCCが長期金利の下限を意識させ、日米金利差の縮小を通じた円高圧力を高めるなど、デメリットが改めて認識された。金融政策の手詰まり感も見えはじめており、2%のインフレ目標未達でも金融引き締め方向に動く欧米の金融政策の転換が参考になる。ただし、足元のインフレ圧力の弱さが政策見直しの足かせになっており、国内要因よりも海外要因に左右されやすい状況が続くだろう。
1. 物価目標は道半ば
YCCの導入後、日本の景気は堅調に推移してきた。実質GDPは2017年4~6月期まで6四半期連続のプラス成長を記録、内閣府や日本銀行の試算による潜在成長率(0.75~1.0%)を上回るペースでの成長が続いてきた。名目GDPは過去最高水準で、企業業績も改善しており、総じて景気は良いといえる。
また、雇用環境も良好な状態にある。7月の完全失業率は2.8%と、1994年6月以来の低水準となった。有効求人倍率も1.52倍と、1974年2月以来の高水準となり、人手不足感が強まっている。
ただし、相変わらず賃金や物価の伸びは勢いを欠いている。名目賃金の前年比は、13か月連続プラスを保ったものの、0%台にとどまっている。消費者物価指数は、2016年末から前年比プラス圏に顔を出したものの、インフレ目標2%には遠く及ばないのが現状だ。
しかも、内訳をみると、今後物価の上昇ペースが鈍化しうる懸念材料もある。サービスの価格が6、7月の2か月間、前年比マイナスに転じた。この状態が定着すれば、デフレ脱却が遠のく。それは過去のインフレ期を振り返ると、テレビなどのように技術進歩によって財の価格が低下する傾向がある一方で、物価を押し上げていたのがサービス価格だったからだ。そのサービス価格は、賃金と密接な関係があり、賃金と物価の弱さが相互に影響しあい、物価目標の達成を後ずれさせるとみられる。
このように、現時点でのYCCの評価は、景気が堅調に推移してきたという点で効果的であったものの、インフレ目標達成という点では道半ばといえる。
2. 根強い消費者のデフレマインド
YCCの導入によっても、消費者のデフレマインドの払拭はなかなか進んでいない。
欧米とは異なり、日本では消費者の将来の物価見通し(インフレ期待)は、過去の物価動向の影響を受けやすいことが知られている。そこで、図表①で示される物価動向をみると、物価上昇率が2016年末にようやくマイナス圏から抜け出し、これまで緩やかに上昇幅が拡大してきたことが確認できる。
しかし、上昇ペースの勢いが欠けていることもあり、肝心のインフレ期待はあまり高まっていない。内閣府『消費動向調査』の「消費者の1年後の物価上昇の見通し」では、8月の「上昇」の回答割合が76.1%と4月以降、足踏み状態が続いている。デフレマインドが残る中で、商品の一斉値下げを発表する小売店の動きが報道されるなど、値上げに躊躇する企業の動きもみられる。
デフレマインドが根強い中では、物価上昇が勢いを欠くため、金融緩和の長期化が避けられそうにない。YCC導入の一つの動機が、当時高まっていた金融緩和の限界への懸念を払拭することだっただけに、再び金融緩和の限界論が意識されるようになるだろう。
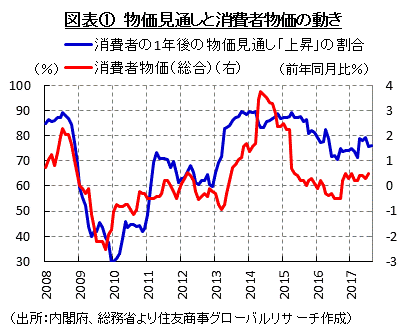
3. 低下してきた長期金利
長期金利は7月に比べて低下した。YCC導入の一つの狙いは、マイナス金利政策が効いて下がりすぎた長期・超長期金利を引き上げて、フラット化していたイールドカーブ(利回り曲線)を立てることであった。イールドカーブのフラット化によって、金融機関の経営や年金の運営、金融仲介機能に悪影響が及ぶとの懸念が大きかったことへの対応策だった。また、「量」から「金利」に政策のターゲットを切り替えることで、金融緩和の持続性を担保しようという狙いもあった。
図表②のように、8月になると、米国政治の不安定化や北朝鮮などの地政学的リスクの高まりなどから、安全資産としての国債に投資マネーが流入したことで、長期金利が低下した。9月には、新発10年物国債利回りが約10か月ぶりにマイナス圏に突入し、イールドカーブも全体的に下方シフトした。YCCの長期金利ターゲットがゼロ%程度を下限とするデメリットが改めて認識された。米国では利上げ観測が後退し、米国長期金利が低下した一方で、日本ではYCCによって長期金利の下限が意識され、結果的に日米金利差が縮小し、円高・ドル安に振れやすかったためだ。
このように、海外経済の動向によって、YCCのデメリットが注目されるなど、政策自体の問題点も改めて認識されるようになった。
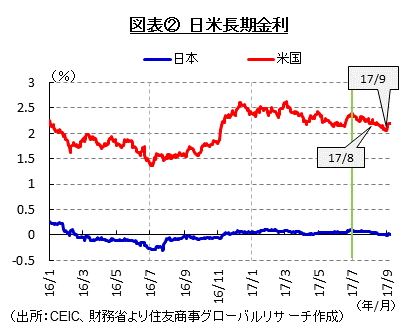
4. 欧米は低インフレ下で引き締めへ
持久戦が続く日本に対して、一足先に欧米の金融政策は転換点を迎えている。その中で注目されるのは、景気が良くても、物価上昇が勢いを欠くという先進国共通の現象である。
米国では、トランプ政権発足時の政策期待が剥落したものの、経済成長が続き、雇用が増えてきたことで、むしろ米国経済の底堅さが確認できた。欧州では、年初に懸念された選挙などが大きな混乱なく過ぎており、17四半期連続でプラス成長となるなど経済の堅調さが保たれてきた。
この中で、欧米ともにインフレ目標には到達していない中で、金融引き締め方向へ舵を切ることになった。7月の米国の個人消費支出(PCE)デフレータは前年同月比1.4%、8月のユーロ圏の消費者物価指数(HICP)も同1.5%と、インフレ目標2%を下回った状態が続いている。
こうした状況でも、FRBは9月にバランスシートの縮小という次の段階に引き締め策を進める。また、ECBは10月に量的緩和の今後の縮小スケジュールを明らかにする見通しとなっている。緩和から引き締め方向に進む欧米に対して、緩和を突き進む日本という構図がより鮮明になりつつある。
5. 海外動向に脆弱な日本経済
緩和を進める中で、金融緩和の限界が議論になり、金融政策の仕切り直しも視野に入ってくる。欧米の金融政策を参考に、例えば、中長期的に2%目標を掲げたままで、短期的にはそれに達しなくとも緩和の出口を探ることが現実的な選択肢の一つだろう。
その理由として、インフレ目標の本質的な課題はデフレ脱却であり、2%達成ではないことがあげられる。2%目標は、他の先進国のインフレ実績やインフレ目標を勘案して設定された。仮に、欧米と遜色ないインフレ率を保てれば、内外価格差から為替レートへ円高圧力、円高からのデフレ圧力はあまり高まらないと考えられる。そのため、中長期的に欧米同様の2%目標の旗は降ろせないものの、短期的に2%を達成する必要性はあまり高くない。
また、金融緩和状態を生み出す上で重要なことが、景気や物価などを加熱も冷却もしない自然利子率(中立金利)より、物価変動を調整した実質金利を下げることである点もあげられる。このまま景気が良い状態が続き、潜在成長率が高まっていけば、それに連動する自然利子率も上昇するので、これまでのような低金利は必要なくなり、YCCを見直すこともできる。
今後の焦点は、インフレ率が少なくとも欧米並みの水準に到達できるかどうかだ。それには、現状から1%ポイント近い上昇が必要な計算で、現状を踏まえれば、相応の時間が必要とみられる。
そうなると、今後のリスク要因は、金融緩和の限界や金融緩和の手詰まり感とそこから派生する悪影響である。YCC導入によってターゲットを金利に変更したことで、国債買入額を年80兆円ペースから60兆円へと減額、時間稼ぎをしつつ、緩和効果を演出してきた。その買入額を戻すことのほかに、追加的な緩和の手段として、YCC導入時には短期金利の引き下げや長期金利のターゲットの引き下げなどが示されていた。しかし、マイナス金利の深掘りなどは、金融機関の経営等への悪影響の方がむしろ大きい上、そもそも景気が良い現状では、金融緩和に踏み切る理由はあまりない。国内金融政策が積極的に動かない中で、海外政治・経済動向の影響力が相対的に大きくなり、海外動向に脆弱な日本経済という構図が当面続くと考えられる。
以上
記事のご利用について:当記事は、住友商事グローバルリサーチ株式会社(以下、「当社」)が信頼できると判断した情報に基づいて作成しており、作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、当社及び住友商事グループは、その情報の正確性、完全性、信頼性、安全性等において、いかなる保証もいたしません。当記事は、情報提供を目的として作成されたものであり、投資その他何らかの行動を勧誘するものではありません。また、当記事は筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社及び住友商事グループの統一された見解ではありません。当記事の全部または一部を著作権法で認められる範囲を超えて無断で利用することはご遠慮ください。なお、当社は、予告なしに当記事の変更・削除等を行うことがあります。当サイト内の記事のご利用についての詳細は「サイトのご利用について」をご確認ください。
 レポート・コラム
レポート・コラム
 SCGRランキング
SCGRランキング
- 2025年6月27日(金)
日経QUICKニュース社の取材を受け、当社シニアエコノミスト 鈴木 将之のコメントが掲載されました。 - 2025年6月27日(金)
『日本経済新聞(電子版)』に、当社シニアエコノミスト 鈴木 将之のコメントが掲載されました。 - 2025年6月16日(月)
『時事通信』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行が寄稿しました。 - 2025年6月13日(金)
『日刊工業新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2025年6月13日(金)
『日刊工業新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。

