伸び悩む賃金と投資不足
2017年12月15日
住友商事グローバルリサーチ 経済部
鈴木 将之
概要
世界同時好況の中で懸念されているのは、伸び悩む賃金だ。景気回復が続く中で、雇用環境が改善してきたにもかかわらず、賃金の上昇ペースは相変わらず加速していない。これは、日米欧で共通の現象だ。その一因として、構造変化とともに、リーマンショック後などの不況期に、研究開発投資や設備投資が控えられたという循環的な要因があげられる。例えば、設備投資の抑制を通じて、労働生産性の向上ペースが鈍化した結果、賃金が上昇しにくい状況となった。足元の経済が堅調に推移する一方で、先の読めない政治リスクや、金融緩和の中での適温相場に隠れたリスクなどがある。そのため、再び賃金の上昇ペースを加速させるためには、企業が成長戦略を本格化させて、積極的に投資を増やすまでの時間が必要だと考えられる。
1. 伸び悩む賃金
世界経済が成長する中で、課題になっているのが賃金の伸び悩みだ。日本以外の先進国では、金融政策が引き締め方向に舵を切っていることもあり、緩和マネーに頼らずに成長するためには、「賃金の上昇→消費の増加→生産の拡大→賃金の上昇→…」という内需の好循環が欠かせない。日本も、経済成長のために消費の底上げが課題でありつづけている。その中で、賃金の役割が大きいだけに、伸び悩む現状は好ましくない。
賃金の伸び悩みは、図表①が示すように、名目賃金と失業率の関係(フィリップス曲線)の変化から読み取れる。日本では、完全失業率が上方シフトした1990年代末の金融危機を踏まえて、期間を分けてみると、2000年代にかけて失業率が低下しても賃金が上昇しにくい状態になったことが確認できる。その一方で、米国では、リーマンショック後に日本と同じように賃金が伸びにくい状態になった。欧州についても、賃金の代理変数として単位労働コストを用いると、米国と同じように不況期を境に、賃金が伸びにくくなっている。
このように、日本では1990年代末の金融危機、欧米ではリーマンショックなど、不況期を境にして賃金と失業率の関係に変化がみられる。
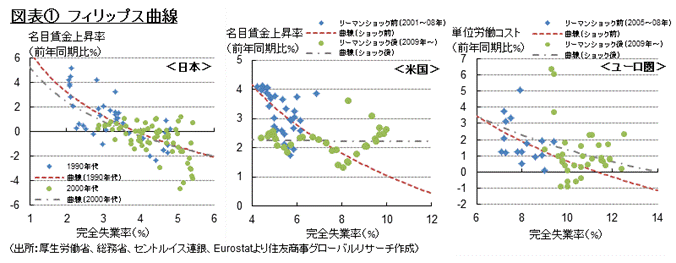
2. 雇用ミスマッチが原因か
何らかの構造変化が生じているのであれば、それは失業率に表れているはずだ。労働市場の需給バランスをみるUV曲線を用いて、その可能性を探ってみる。UV曲線とは、図表②のように、縦軸に失業率(U:Unemployment)、横軸に欠員率(V:Vacancy)をとった図である。なお、ここで図示するUV曲線は、労働政策研究・研修機構『ユースフル労働統計2016』(8章「UV分析関連指標」)の方法を参考に計算したものである。
例えば、日本の2009年第1四半期(Q1)から2017年Q3にかけての左上から右下への動きは、失業率が低下する一方で、欠員率が上昇してきたことを表しており、需要不足失業の減少と解釈できる。この需要不足失業とは、不況期に労働需要の減少によって需給バランスが悪化したことで、増加した失業である。
また、この曲線自体のシフト、例えば1990年代から2000年代にかけて左下から右上への曲線自体のシフトは、構造的失業の増加と解釈される。失業率と欠員率でみた需給バランスが変わらない下でも失業率が上昇するので、需要不足以外の要因、すなわち主に技能や年齢などの雇用ミスマッチによる構造的失業が増えたと解釈できる。
このUV曲線から、日米では需要不足失業がほぼ解消されていることが読み取れる。欧州では、需要不足失業は残っているものの、減少している様子がうかがえる。日米のように、需要不足失業が減少して雇用環境が改善すれば、一般的に賃金は上昇すると考えられる。実際、現在と同水準まで失業率が低下していた1990年初頭の日本や、リーマンショック以前の米国では、賃金上昇率は高かった。しかし、現在の賃金は、伸び悩んでいる。
そうなると、構造的失業が悪影響を及ぼしている可能性がある。米国のUV曲線上では、曲線自体が右上へシフトしていないので、構造的失業の増加はみられない。日本では足元の景気回復によって1990年代のUV曲線上に戻るような動きにもみえる。これを踏まえると、構造的失業が賃金の伸び悩みの一因である可能性は否定できないものの、改善傾向がみられるため、他の要因を検討する必要があるだろう。一方で、欧州では、構造的失業は高止まりしたままであり、雇用ミスマッチの拡大など、構造的変化が伸び悩みに影響しているとみられる。
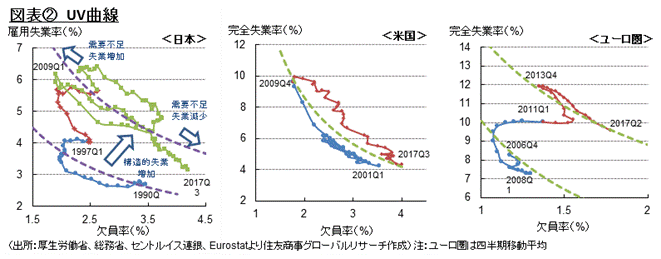
3. 不況期の投資不足
不況を境に鈍化している賃金上昇率について、企業の生産サイドから考えてみる。
一定の仮定の下で、物価の変動の影響を除いた賃金上昇率は、技術進歩などを含む生産性の変化率と、資本装備率(就業者1人当たりの機械設備などの資本ストック)の変化率の2つの要因に分解されることが知られている。そこで、以下ではそれぞれの要因を検討してみる。
まず、生産性について、技術進歩などを含む広義の生産性を表す全要素生産性をみると、図表③のように、欧米の生産性の上昇ペースはリーマンショックを境に、日本も2012年にかけて鈍化していた。一般的に、研究開発投資などによって生産性は向上するので、不況期にそれらが抑制された結果、賃金が伸び悩んでいるとみられる。
日本の場合では、総務省『科学技術研究調査』によると、科学技術研究費は、2007年度の18.9兆円から2010年度の17.1兆円まで減少した。しかし、科学技術研究費は2014年度に19.0兆円まで回復し、リーマンショック以前の水準を上回っている。少なくとも日本において、研究開発費は長期的に低下しているわけではないので、生産性のみが原因とは言い難い。
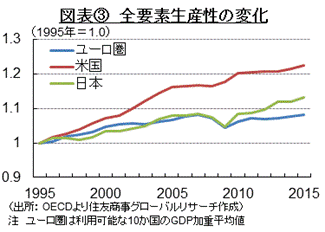
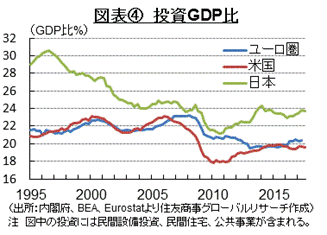
次に、資本装備率は、分母の就業者数と、分子の機械設備などの資本ストックに分けられる。景気回復の中で、各国とも就業者数は増えており、資本装備率の押し下げ要因になっている。
ただし、就業者数が減った以上に資本ストックが増えれば、資本装備率は上昇するので、資本ストックの動向が重要になる。資本ストックは、減価償却分を除くと、過去の設備投資の蓄積として表される。そこで、経済規模(GDP)対比でみた投資(民間設備投資、民間住宅、公共事業の合計)をみると、図表④のように、各国ともリーマンショック後に、投資GDP比率が低下しており、それ以前の水準を回復できていない様子が確認できる。
例えば、ここ数年の日本では、1990年代後半からの低下トレンドがようやく下げ止まった段階であり、明確な上昇トレンドはみられていない。この理由としては、まず、先行きが読みにくくなったことがあげられる。景気は回復していても、内需が弱かったり、頼みの綱の外需でも海外経済にリスクがあったりする。そうした中で、国内投資を手控えてきた企業の姿がうかがえる。
それに加えて、企業の事業戦略の変化も、理由としてあげられる。1990年代後半以降の日本では、アジアを中心に、生産拠点の海外移転を進めて、国内生産能力を削減してきた。それに対して、リーマンショック以降、現地の経済成長と人件費などのビジネスコストの上昇が目立ちはじめ、生産拠点から販売市場としての性格が強くなった。地産地消を軸にしたサプライチェーンを構築するなど、企業の事業戦略は変化しつつある。
以上のように、研究開発投資や設備投資などが抑えられてきたことで、結果的に賃金が伸び悩んでいる一面があると考えられる。
4 賃金上昇には時間が必要に
こうしたことを踏まえると、国内投資の回復には、企業が成長戦略を本格化させるまでの時間が必要だろう。
その理由として、金融緩和によって金利が低下し、資本コストが下がったことは、投資の追い風になった一方で、先行き不透明感やこれまでの経済成長の見通しの引き下げが、企業に投資を躊躇させてきたことがあげられる。
そうしたリスクとともに、将来の成長期待の鈍化によって、予想収益性が低下している可能性もある。もちろん、今後の成長期待を高めるような、包括的及び先進的なTPP(CPTPP)の大筋合意や日EU・EPAの妥結など、明るい材料がある。しかし、それらが発効するのは2019年とみられており、具体的な内容を見極める必要がある。さらに、欧米の政治情勢については、引き続き先の読めないリスクがあることに変わりない。
また、金融政策の手詰まり感も、企業の投資意欲を委縮させている可能性がある。日米欧ともに、いつ景気が減速してもおかしくないくらいに、景気拡張局面が長期化してきた。その中で、引き締め方向に進む金融政策が、今後、景気後退のトリガーを引く恐れがある。それらの引き締めがある臨界点を超えて、景気を押し下げる方向に働きはじめたとき、緩和しきった金融政策には追加対策の余地が乏しく、有効策を打てないという手詰まり感が意識されやすくなっている。このような適温相場に隠れたリスクも、企業の投資行動を慎重なものにさせている一面もあるだろう。
その一方で、リスクを取らなければリターンがないことも事実だ。現在、AIやIoTなど新しい技術の導入や、人口動態の変化に応じた省力化・効率化投資が求められており、研究開発投資や設備投資が動き始めている兆しもみられる。リスクを踏まえた慎重な見方と、成長を見据えた積極的な見方の間に挟まれている。このように、再び賃金の上昇ペースを加速させるような積極的な投資が増えるためには、企業が成長戦略を本格化させるまでの時間が必要だと考えられる。
参考文献
労働政策研究・研修機構(2017)『ユースフル労働統計2016』
以上
記事のご利用について:当記事は、住友商事グローバルリサーチ株式会社(以下、「当社」)が信頼できると判断した情報に基づいて作成しており、作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、当社及び住友商事グループは、その情報の正確性、完全性、信頼性、安全性等において、いかなる保証もいたしません。当記事は、情報提供を目的として作成されたものであり、投資その他何らかの行動を勧誘するものではありません。また、当記事は筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社及び住友商事グループの統一された見解ではありません。当記事の全部または一部を著作権法で認められる範囲を超えて無断で利用することはご遠慮ください。なお、当社は、予告なしに当記事の変更・削除等を行うことがあります。当サイト内の記事のご利用についての詳細は「サイトのご利用について」をご確認ください。
 レポート・コラム
レポート・コラム
 SCGRランキング
SCGRランキング
- 2025年7月10日(木)
19:00~、NHK『NHKニュース7』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行へのインタビューが放映されました。 - 2025年7月4日(金)
日本国際平和構築委員会『7月研究会』に、当社シニアアナリスト 足立 正彦がパネリストとして登壇しました。 - 2025年6月27日(金)
日経QUICKニュース社の取材を受け、当社シニアエコノミスト 鈴木 将之のコメントが掲載されました。 - 2025年6月27日(金)
『日本経済新聞(電子版)』に、当社シニアエコノミスト 鈴木 将之のコメントが掲載されました。 - 2025年6月22日(日)
雑誌『経済界』2025年8月号に、米州住友商事会社ワシントン事務所調査部長 渡辺 亮司が寄稿しました。

