デフレ脱却4条件の日米欧比較
2017年12月21日
住友商事グローバルリサーチ 経済部
鈴木 将之
概要
2017年7-9月期に、デフレ脱却の4条件が25年ぶりにすべてプラスになった。デフレ脱却宣言が近づいている一方で、その道のりには険しさも残っている。欧米でも、GDPギャップがマイナスになっているなど必ずしも条件が整っていない中でも、物価が上昇してきたのは、期待インフレ率が安定してきたからだった。四半世紀にわたるデフレから脱却できるか、今後の動向が注目される。
1. デフレではない
日米欧では、景気回復が続く一方で、物価上昇率は2%目標に達していない。それでも、日本は、「デフレではない」といえる状況まで好転しており、残すは「デフレ脱却」宣言のみとなった。
内閣府によると、デフレ脱却とは「物価が持続的に下落する状況を脱し、再びそうした状況に戻る見込みがないこと」と定義されている。実際、消費者物価指数を年平均でみると、2012~15年にかけて前年比0.0%、0.4%、2.7%、0.8%とプラスが続いており、2016年通年では同▲0.1%とマイナスに転じたものの、同年10月以降は前年同月比プラスが続いており、持続的に物価が下落する状況とはいえなくなっている。
ただし、「再びそうした状況に戻る見込みがないこと」という条件が厳しい。内閣府は、消費者物価指数やGDPデフレータなどの物価の基調とともに、その「背景」を総合的に考慮するとしている。その「背景」とは、需給ギャップ(GDPギャップ)や単位労働費用などが例示されている。そのため、内閣府が条件と明示しているわけではないものの、一般的に、消費者物価指数やGDPデフレータ、GDPギャップ、単位労働費用の4つが、デフレ脱却の4条件と認識されている。
その4条件が2017年7-9月期に、すべてプラスになった。それは、1992年第2四半期以来25年ぶりのことであり、内閣府は現状を「局面変化」と表現している。しかし、プラスといってもわずかにゼロを上回ったところであり、更なるプラス幅の拡大と持続性が確かめられなければ、デフレ脱却宣言は難しいだろう。そこで、4条件について、物価上昇が続く米欧と比べながら、今後のデフレ脱却を考えてみる。
2. デフレ脱却4条件の国際比較
まず、図表①のように、消費者物価指数(米国はPCEデフレータ)をみると、各国の中央銀行がインフレ目標として掲げている2%には達していない様子が確認できる。ただし、日本とは異なり、欧米ではリーマンショック以前には2%を超えていた。
日本ではこの20年で、消費者物価指数の変化率がプラス圏に顔を出したのは、1997年の消費税率引き上げ時や2000年代の資源エネルギー価格の高騰時などに限られていた。2014年の消費税率引き上げ前には、金融緩和期待による円安効果もあって物価の基調は上向いたものの、その後勢いが削がれてしまった。デフレではない状況になったとはいえ、欧米に比べて約1%ポイントも下回るなど、物価上昇ペースは鈍い。
図表②のGDPデフレータでも、消費者物価指数と同じような傾向がみられる。GDPデフレータは、個人消費や設備投資など、GDP構成項目を総合的に捉えた物価指数といえる。米国では前年同期比2%に戻りつつある一方で、ユーロ圏ではリーマンショック前から約1%ポイント水準を下げており、回復途中にある。それに対して、日本のGDPデフレータは、ようやくプラス圏に顔を出した段階だ。このように、日本の物価の基調は、欧米に比べてかなり弱い状態にある。
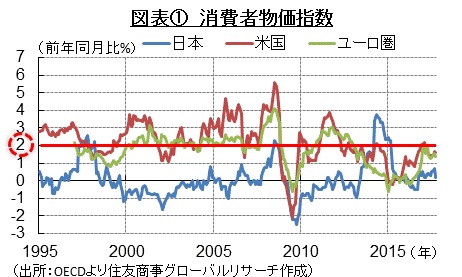
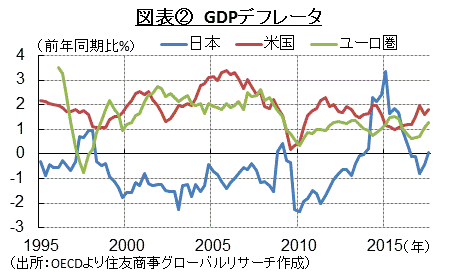
図表③のように、マクロ経済全体の需給バランスを表すGDPギャップの共通点として、リーマンショック後にマイナスに転じ、需要不足の状態になったことがあげられる。しかし、その後の回復ペースには、大きな相違があり、日本は、米欧に先駆けてプラス圏に顔を出し、需要超過の状態になった。人手不足に代表されるように供給制約が強まる一方で、景気回復によって需要が拡大したことで、需給がひっ迫したためだ。GDPギャップがプラス、すなわち需要超過となれば、物価に上昇圧力がかかりやすくなる。このように、欧米に比べて、日本では需要側からの物価押し上げ圧力が強まっている。
その一方で、日本では、供給側からの物価押し上げ圧力が弱い。図表④の供給サイドの物価圧力である単位労働費用(Unit Labor Cost:ULC)は、名目雇用者報酬を実質GDPで割ったものであり、1単位のGDPを生産するための労働コストと解釈できる。また、賃金と労働生産性の逆数の掛け算で表され、マクロ経済全体の労働コスト、すなわちコストプッシュ型の物価上昇圧力といえる。賃金の伸び悩みを反映して、各国とも単位労働費用の伸び率は、リーマンショック前に比べて縮小している。ただし、欧米ではこれまでプラス圏を推移してきたことで、供給側からの物価上昇圧力が高い傾向にあった。それに対して、マイナス圏を推移してきた日本では、供給側からの物価上昇圧力の弱さが目立っている。
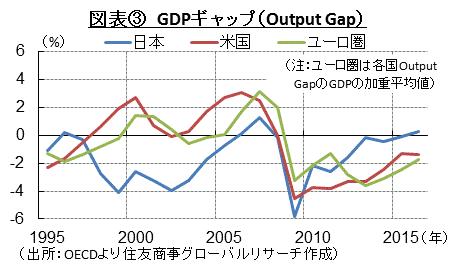
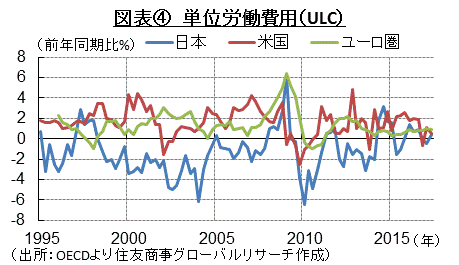
3. 四半世紀ぶりのチャンス
以上のように、欧米でも必ずしも4条件が満たされているわけではない。その中で、物価上昇が続く一因として、物価のアンカーとなる消費者の将来の物価見通し(期待インフレ率)の存在があげられる。
図表⑤のように、日本では、1997年の消費税率引き上げや2000年代前半の資源エネルギー価格の高騰時以外では、アベノミクスが始まるまで、物価見通しで相対的に「上昇」の割合は、なかなか高まらなかった。特に1997~2005年の長期間にわたって、物価見通しが平均値(1995~2017年)を下回り、デフレマインドが形成されたとみられる。それに対して、欧州では物価見通しが低下しても、すぐに持ち直しており、図表⑥のように、米国では期待インフレ率が2%を超えているなど、デフレマインドはない。
こうした中、日本では、物価上昇見通しに改善の兆しが見えはじめている。そこで注目されるのは、改善が今後も続くかだ。物価見通しが、過去の物価上昇の経験に影響を強く受けるため、上記の4条件の持続力が問われることになる。
まず、需給面については、今後も景気回復が続くと予想されるので、GDPギャップのプラス幅が拡大し、次第に物価上昇圧力が高まるとみられる。それは、輸入物価を通じた物価の押し上げ効果も期待できる。欧米で物価が上昇すれば、金融政策はもう一段引き締め方向に進み、緩和姿勢をとる日本の金融政策との相違がより大きくなるからだ。それが円安要因となり、日本の物価の押し上げにつながるだろう。
物価上昇を持続的なものにするためには、供給側からの物価押し上げも欠かせない。足もとでは、企業業績の改善とともに政労使三者協議からの賃上げ圧力や、深刻な状態が続く人手不足があり、賃金の上昇ペースが加速する素地は整いつつある。長期的には、AIやIoTなど生産性向上もあって、賃金と労働生産性の好循環が続く方向に向かうことも想定される。
このように、当面、需給両面からの物価上昇圧力は高まるとみられる。それらによる物価上昇の経験を通じてデフレマインドが払拭されれば、欧米のように、次第にインフレ期待は高まるだろう。デフレ脱却とその先の出口にいろいろと課題が待ち構えている中で、日本は四半世紀にわたるデフレから脱却できるか、今後の動向が注目される。
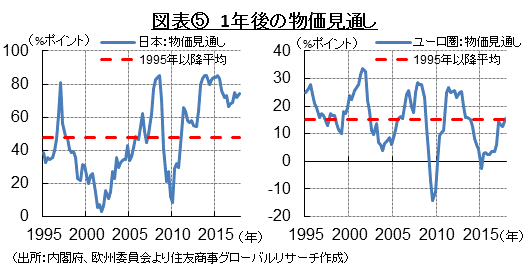
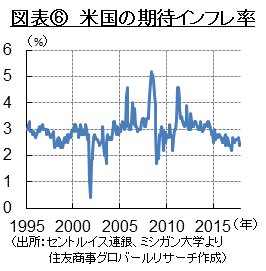
以上
記事のご利用について:当記事は、住友商事グローバルリサーチ株式会社(以下、「当社」)が信頼できると判断した情報に基づいて作成しており、作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、当社及び住友商事グループは、その情報の正確性、完全性、信頼性、安全性等において、いかなる保証もいたしません。当記事は、情報提供を目的として作成されたものであり、投資その他何らかの行動を勧誘するものではありません。また、当記事は筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社及び住友商事グループの統一された見解ではありません。当記事の全部または一部を著作権法で認められる範囲を超えて無断で利用することはご遠慮ください。なお、当社は、予告なしに当記事の変更・削除等を行うことがあります。当サイト内の記事のご利用についての詳細は「サイトのご利用について」をご確認ください。
 レポート・コラム
レポート・コラム
 SCGRランキング
SCGRランキング
- 2025年7月4日(金)
日本国際平和構築委員会『7月研究会』に、当社シニアアナリスト 足立 正彦がパネリストとして登壇しました。 - 2025年6月27日(金)
日経QUICKニュース社の取材を受け、当社シニアエコノミスト 鈴木 将之のコメントが掲載されました。 - 2025年6月27日(金)
『日本経済新聞(電子版)』に、当社シニアエコノミスト 鈴木 将之のコメントが掲載されました。 - 2025年6月16日(月)
『時事通信』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行が寄稿しました。 - 2025年6月13日(金)
『日刊工業新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。

