平成をふりかえる②~多様化した投資が歩んだ30年
2019年01月11日
住友商事グローバルリサーチ経済部
鈴木 将之
概要
終わりを告げようとしている平成について、「投資」という視点から振り返ってみる。はじまりはバブル絶頂期で力強さをみせていた平成の設備投資は、バブル崩壊後、過剰設備の問題などが重石となり伸び悩んだ。設備投資は抑制された一方で、将来の収益源の獲得を狙って、海外投資や研究開発投資など、日本企業は投資を多様化させてきた。足もとで過去最高を更新する経常利益は、こうした過去の投資の賜物といえる。平成が終わりを迎える今こそ、次なる成長のための投資を拡大する好機といえる。原資となる企業収益が改善している上、第4次産業革命など新しい経済・社会の姿も見えつつある。設備投資や海外投資など、どのような形態をとるにせよ、新しい事業機会に投資していくことの重要性を、平成という時代が示しているようだ。
1. 投資から平成をふりかえる
日本経済がバブル絶頂に向かう中ではじまった平成の初め、企業の設備投資意欲は旺盛だった。図表①のように、民間企業設備投資は、現在のGDP基準(研究開発投資などを含む)で、1991年には年100兆円規模だった。しかし、バブルが崩壊し、状況は一変した。問題になった過剰な設備は「失われた20年」の代名詞の1つになってしまった。その後の金融危機などもあり、図表②のように、1998年度以降、設備投資額は減価償却費を下回るようになった。
こうした中で、次第に国内で、企業が設備投資を行わなくなったことが、問題として取り上げられるようになった。この背景には、バブル崩壊後、過剰な設備や債務が企業の重石になったことや、その後の貸し剥がしなどが、企業に設備投資を躊躇させたことがある。「失われた20年」といわれるように低迷していたこともあって、企業のリスク回避の動きが強まったようだ。
その一方で、海外で積極的な動きがみられた。生産拠点を国内から海外に移転するなど、製造業を中心に海外進出が加速して、国内よりも海外への投資が注目を集めた。ちょうど、中国をはじめとするアジア諸国の経済成長が目立ちはじめ、存在感が高まってきた時期と重なったことも、企業にとって追い風に感じられた。このような外部環境の変化から、「成長が期待できない国内より、成長の恩恵を享受できる海外」という考えが広く浸透していった。
しかし、平成が終わりに近づくにつれて、そうした動きに変化がみられるようになった。2013年度になると、再び設備投資額が減価償却費を上回るようになった。2018年第3四半期の企業設備投資額は90兆円超と、バブル崩壊後のピークだった1997年を上回っている。国内の景気回復の中で、企業収益が向上しつつあることも、国内投資の後押しとなった。これまで抑えられてきた維持・更新投資の需要が顕在化した。その後も設備投資は堅調に推移しており、設備投資から見る限り、いわゆる「失われた20年」を取り戻したともいえるだろう。
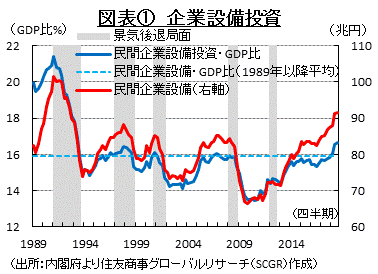
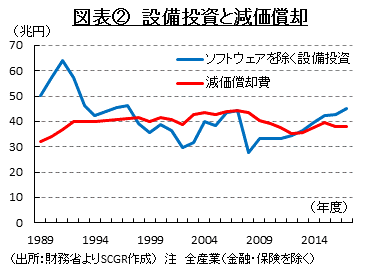
また、特にアジア諸国の経済成長率は日本よりも高いものの、賃金も上昇しており、安価な労働力を期待した生産体制は通用しにくくなった。そうした動きはこれまでもみられ、「チャイナ+1」に代表されるように、日本企業は中国から東南アジア、南アジアへと生産拠点を移してきたが、規制や税制、社会インフラの整備状況などを含めたビジネスコストを勘案すれば、アジア諸国の優位性は必ずしも魅力的とは言えない一面も再認識されてきた。もちろん、アジアの経済成長率は依然として高いため、販売市場としての魅力は損なわれていない。そのため、日本企業にとって、アジア諸国は生産拠点と販売市場の両面を持ち合わせるようになっており、日本は生産拠点と販売市場を結びつけるサプライチェーンを構築する役割を果たしているという認識になっている。
ここで、平成の設備投資に絞ってみると、いくつかの局面に分けられる。まず、①設備投資が拡大していた1989~92年度ごろのバブル期、②設備投資が減少したとはいえ、減価償却費を上回っていた1993~1997年度ごろのポストバブル期、③過剰な設備が問題となり、設備投資が減価償却費を下回るようになった1998~2012年度の失われた10~20年の時期、そして、④2013年度以降の再び設備投資が加速しはじめたアベノミクス景気の時期である。
また、重要な点は、企業にとって「投資とは何か」ということだ。上記のように、設備投資が伸び悩んだ中で、他の形態の投資が増えていたことが注目される。企業にとって、投資とは将来の収益源を育てるために現在支払う費用である。そのため、将来の収益源を考えたときに、設備投資以外にも、投資には様々な形態があり、外部環境に合わせて事業戦略を柔軟に変更していくことも重要といえる。後述するように、日本企業が選択したものは、海外投資や研究開発投資などであった。
幅広い投資という視点から平成をふりかえるとき、企業が失われた20年を乗り越えて国内設備投資を回復させつつあることは、「投資の多様化」という文脈でとらえられる。結論を先取りすれば、将来の収益源を模索する投資という試行錯誤が、平成という時代の一つの側面だったのだろう。
2. 回復基調に転じはじめた設備投資の収益性
まず、企業の投資のうち、設備投資に焦点をあてる。設備投資の状況について、図表③のように、上記の設備投資の局面に合わせて資本ストック循環図を描いてみた。これは、景気が良いと設備投資が増えて、設備投資・資本ストック比率も上昇する一方で、景気が悪いと設備投資が減って、設備投資・資本ストック比率は低下するという循環を描いたもので、時計回りの軌跡が描かれることになる。
この軌跡から、まず、1980年代からのバブル期にかけて拡大した設備投資が、バブル崩壊によって大きく減速したことがわかる。1993年度から1997年度にかけて設備投資が持ち直しに向かったものの、金融危機やアジア通貨危機が重なった不況期から再び減速に転じた。ITバブル期に向けて回復傾向をみせたものの、その崩壊で再度減速、2000年代の回復は緩やかなものにとどまった。
1990年代初頭までの時期とそれ以降の時期を比べると、資本ストックに対して設備投資の規模が縮小していることがわかる。過剰な設備が問題になっていたこともあり、いかに効率化するかが企業にとっての課題だったためだ。また、2000年代の景気回復局面では、過剰な設備の問題にようやく一服感がみえはじめたことで、1990年代後半以上に設備投資が行われつつあったものの、リーマンショック後の世界同時不況によって再び投資が減速した。
2013年以降になると、設備投資の増加幅は緩やかであるものの、着実に伸びてきた。その背景には、企業業績が改善する中で、それまで先延ばしにしてきた更新投資を行う必要に迫られたことがある。また、足もとでは、2012年以降にいわゆる「団塊の世代」が定年を迎えるなど、労働供給が先細りする中で、景気回復によって労働需要が拡大した結果、人手不足が深刻な問題になった。そのため、省力化投資が、企業にとっては切実な課題となった。
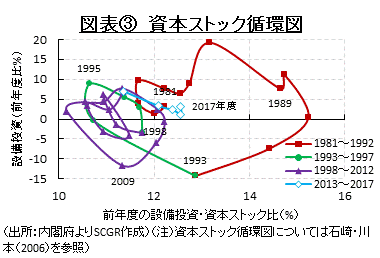
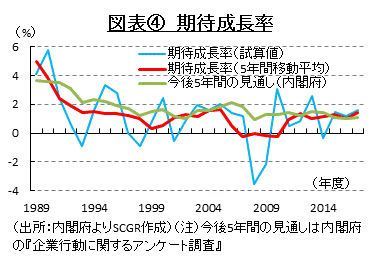
循環の円軌道の大きさをみると、1980年代から1990年代にかけてのものに比べて、2000年代は小さなものになっている。それだけ、企業の設備投資意欲が縮小していたといえる。しかし、2013年以降になると、設備投資・資本ストック比が2000年以降で最大の大きさになっている。仮に、このペースが維持されれば、循環の軌道が、2000年代よりも大きくなり、設備投資の復活の印象が強まるかもしれない。
その復活の鍵を握るのが、企業からみた期待収益率だろう。これまで、金融緩和政策による低金利で、資本コストは引き下げられてきた。しかし、収益性が十分確保されないとの見通しから、企業が設備投資に二の足を踏んできたためだ。
そこで、図表④のように、資本ストック循環図から作成した期待成長率と内閣府アンケート調査による期待成長率を比べてみた。これによると、企業にとっての国内の期待成長率は、バブル崩壊後に大きく低下してから、その後低水準にとどまっており、企業が設備投資を行う環境ではなかったようにみえる。
しかし、バブル崩壊後に1%強の水準まで大きく低下した期待成長率は、さらにそこから低下しつづけたわけではない。均してみれば、期待成長率は1%程度で横ばい圏を推移していた。そのトレンド(移動平均)は足もとにかけて緩やかに改善しているように見え、投資環境は整いつつあるようだ。また、アベノミクスが始まってから、日本経済はデフレではない状況になり、名目GDPが1997年を上回り、過去最高になるなど、外部環境が大きく改善していることも、設備投資の後押しになっているのだろう。
こうしたことを踏まえて、設備投資の背景について確認しておく。図表⑤のように、設備投資を収益性要因や土地要因、貯蓄要因、不確実性要因で説明する関数を推計して、要因分解してみた。
この結果をみると、平成が始まった頃、収益性要因や土地要因などが設備投資の押し上げ要因だった。これは、景気が良く設備投資による高い収益性が見込まれたこと、また当時は土地神話の中で地価が上昇しており、それが企業のバランスシートを拡大させていたことと整合性があるだろう。しかし、バブル崩壊後、環境が一変した。景気後退の中で収益性が悪化し、また地価が大幅に下落したことで、それらが逆回転して設備投資の下押し要因となった。
1993年以降、景気が持ち直しはじめたことで、収益性要因の設備投資への下押し圧力は次第に緩和していった。企業収益の回復もあって、貯蓄要因が設備投資のけん引役として目立ちはじめた。その一方で、地価の下落が続き、企業にとっての土地の担保価値が低下する中、バランスシート調整が重石になった。それは過剰な債務の一因となり、その後の日本企業に重く圧し掛かることになった。そのため、土地要因は設備投資の下押し要因となり、その悪影響は2000年代前半まで続いた。
1998年以降でも同じように、貯蓄要因が唯一の牽引役ともいえる状況であった。しかし、国内外の金融危機やITバブルの崩壊の影響などが、企業貯蓄の拡大を阻んだことで、貯蓄要因は投資の押し上げ要因としては力不足だった。2000年代のリーマンショック前の好況期には、景気回復期間が長期に及んだことで、不確実性の低下が投資環境の整備に一役買ったものの、貯蓄要因などの押し上げ効果が持続しなかったため、設備投資の増加幅は限定的だった。
そうした状況が一変したのは、アベノミクス以降だった。貯蓄要因が安定的に設備投資を押し上げるようになった主因は、経済成長とともに企業業績が改善したことである。また、現在の景気拡張局面では、途中足踏みの時期を挟んだとはいえ、景気後退局面に転換しておらず、地価も底入れしている。それによって土地要因や不確実性要因の押し下げ効果も剥落しており、設備投資の足を引っ張る要因がかなり小さくなっている。
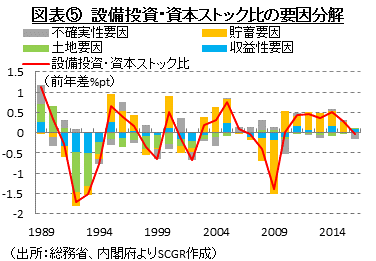
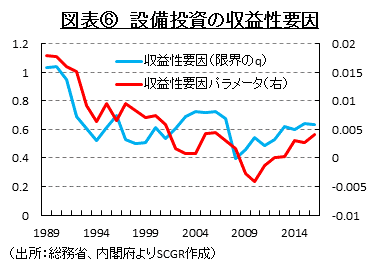
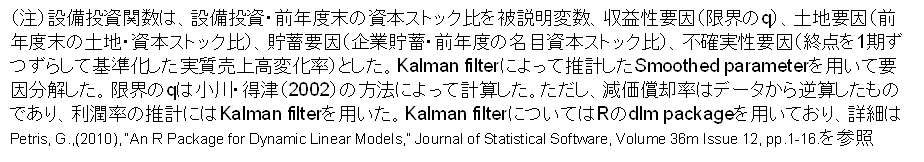
特に重要なことは、図表⑥のように、収益性要因の効果が一時期より改善しており、設備投資の増加を支えていることだ。設備投資の収益性要因は、平成になってから、ほぼ右肩下がりで低下していたものの、リーマンショック以降には反動増に続いて、回復傾向がみられる。また、収益性要因が設備投資を押し上げる効果(収益性要因パラメータ)も、一時の低下トレンドから上昇トレンドに転じている様子がうかがわれる。このパラメータの上昇は、収益性の向上がより設備投資の増加に結び付きやすくなっていることを表している。つまり、足もとにかけて、収益性の回復と、それが設備投資に結び付きやすくなっていることの2つの要因によって、設備投資が押し上げられやすくなりつつあるということだ。
このように、収益性という視点から見ると、平成も終わりに近づくにつれて、金融緩和による資本コストが低下している中で、収益性が改善することによって、設備投資が増加する環境が整い、企業が設備投資に積極的になりつつある姿がうかがえる。
3. 海外を目指す企業の投資
前述のように、企業にとっての投資とは、将来の収益源を育成するために現在費用をかけるものである。そのため、国内設備投資に限らず、海外での設備投資、M&Aや経営権を握るための直接投資、株式や債券などを運用する証券投資、それに加えて従業員などの人への投資、知的財産や研究開発投資など多岐にわたるものが、投資戦略の対象となる。
まず、海外現地法人の設備投資について注目してみよう。設備投資の前提となる海外生産は、これまで拡大してきた。その海外生産は、海外現地法人の売上高が国内・海外現地法人の売上高の和に占める割合として定義される国内全法人ベース(製造業)の海外生産比率で捉えられる(経済産業省『海外事業活動基本調査』)。比較可能な数値として海外生産比率は1989年度の5.7%から1998年度に13.1%へと上昇した。また、新基準でみると、1989年度の11.6%から2016年度の23.8%へと上昇している。こうした傾向は、海外進出企業ベース(製造業)でみても同様で、日本企業の海外生産の拡大が確認できる。
そうした中で、図表⑦のように、海外設備投資の国内外設備投資に占める割合である海外設備投資比率も、1989年度の6.3%から2016年度には20.7%と3倍近くまで拡大してきた。1990年代前半には横ばいの動きがみられるものの、後半になるにつれて上昇している。これは国内設備投資が減少する一方で、海外現地法人の設備投資が増加したためである。
また、アジア通貨危機以降、海外設備投資額は2~2.5兆円のレンジで横ばいの動きとなったものの、リーマンショック前のアジア経済の成長期に海外設備投資額は増加し、2007年には4.2兆円まで拡大した。当時、国内設備投資も増加したことで、海外設備投資比率は横ばいになっているものの、日本企業の海外投資意欲は旺盛だったといえる。こうした背景には、国内の生産拠点を海外に移転するとともに、国内外の生産の分業体制が深化していたこともある。
また、2012年度にかけて海外設備投資比率が急上昇した背景には、国内法人の設備投資額が減少していた一方で、海外設備投資額が2013~15年度にかけて4兆円台半ばまで増えていたことがある。その後、国内の景気回復、設備投資の増加によって、海外設備投資比率が低下しているとはいえ、トレンドをみれば海外設備投資比率は上昇傾向にある。このように、海外設備投資は、国内の代替・補完の関係の中で、成長してきた。
日本の製造業が海外に設備投資を行う理由は、その収益性の高さにある。図表⑧のように、売上高経常利益率をみると、1990年代末から2000年代にかけて国内法人に比べて、海外現地法人の方が高かった。もちろん、日本の経済成長率に比べて海外の成長率の方が高いため、収益性が高くなる傾向がある。そうした中、成長の機会を海外に見いだして、積極的に海外に進出していった企業の姿がうかがえる。足もとでは、国内景気の回復やコーポレートガバナンス改革などによって、収益性がこれまで以上に注目されていることもあって、国内法人の売上高経常利益率の方が高い傾向にある。しかし、中長期的にみた場合、アジア新興国などの経済成長率は日本よりも高い上、賃金上昇の半面、購買力が向上し、販売市場としての存在感を高めているので、海外投資という選択肢の魅力は損なわれていない。
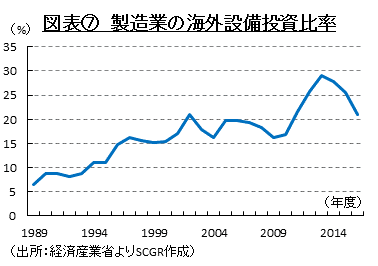
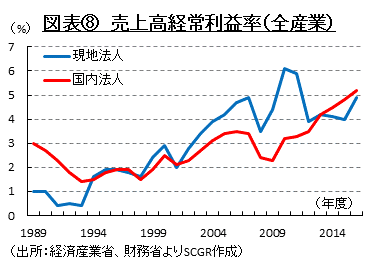
概念として前述の海外設備投資と重複するところはあるが、別の視点からの海外投資として、直接投資や証券投資などがあげられる。図表⑨のように、日本の直接・証券投資について、投資収益と投資残高(ストック)から計算した収益率をみると、2000年代の直接投資の収益率の高さが目立っている。再投資収益を除いたベースでみても、証券投資に比べて直接投資は2000年代半ばから4~6%程度と比較的高い水準を保ってきた。
こうした収益性の高さもあって、図表⑩のように、直接・証券投資のフロー(ネット)をみると、直接投資が2000年代に拡大してきた。比較可能な1996年と2017年を比べると、10.4兆円増加している金融収支のうち、直接投資が14.0兆円増と、牽引役だった。このうち、再投資収益が4.0兆円分あることを踏まえても、直接投資がこれまで着実に増加してきた姿がうかがえる。
また、直接投資に関係するところで、図表⑪のようにクロスボーダーM&A(購入・ネット)も、バブル期の1990年代初頭以上に、2000年代に拡大している様子がみられる。1990年代後半から2000年代はじめにかけて、クロスボーダーM&Aはゼロ近傍にあったものの、次第に拡大し、2016年には8兆円弱の規模にまで成長している。つまり、直接投資が、日本企業にとっても重要な成長戦略になっているといえる。
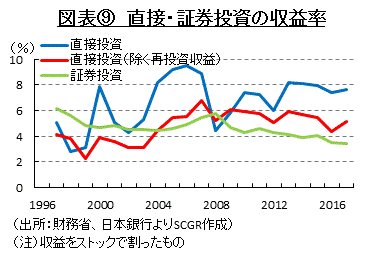
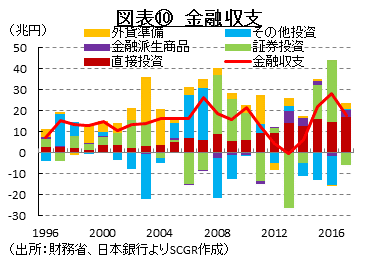
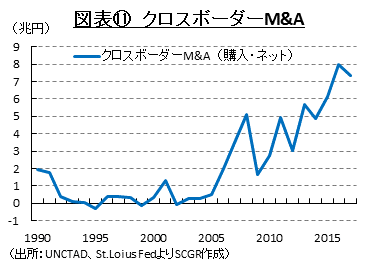
一方、証券投資の収益率は安定しているものの、低下傾向にある。これは、リーマンショック後の先進国を中心とした金融緩和政策もあって、金利が低下しているためだ。企業が証券投資に積極的になりにくい環境になったといえる。
ただし、収益額という点からみると、その金額は大きい。2017年の証券投資収益は10.3兆円と、直接投資収益の8.9兆円を上回っていた。しかし、直接投資収益が1996年の1.5兆円から2017年の8.9兆円へと5.8倍に、再投資収益を除いた直接投資収益が同期間に1.0兆円から4.4兆円へと4.3倍に拡大してきたのに対して、証券投資収益は4.4兆円から10.3兆円へと、2.4倍の拡大にとどまっていた。証券投資は安定的な収益源であったものの、成長性という点では直接投資に見劣りしていた。
このように、証券投資には金融機関の外債購入などが含まれているものの、日本企業という視点からみれば、証券投資とともに、いかに直接投資を拡大させるのかが、収益性を高める事業戦略の一つであったと考えられる。
こうした結果は、図表⑫のように、経常収支の構造変化に現れている。平成が始まってから10年おきにみると、日本の対世界計の経常収支のうち、1998年の稼ぎ頭が貿易収支の黒字であったものの、2017年には直接・証券投資収益などからなる第一次所得収支で受取超になっている。これは、輸出立国から投資立国への変化といえる。また、サービス収支の赤字の減少もみられる。これは、訪日観光客の増加に代表される旅行収支の黒字拡大が貢献している。また、日本企業の海外進出が進んだこともあり、海外現地法人からのロイヤリティなどの知的財産権等使用料の受け取りの拡大もある。実際、総務省『科学技術研究調査』によると、2017年度の技術輸出(特許、ノウハウなどの技術提供)の約75.3%が親子会社間であり、日本企業の海外進出の結果といえる。
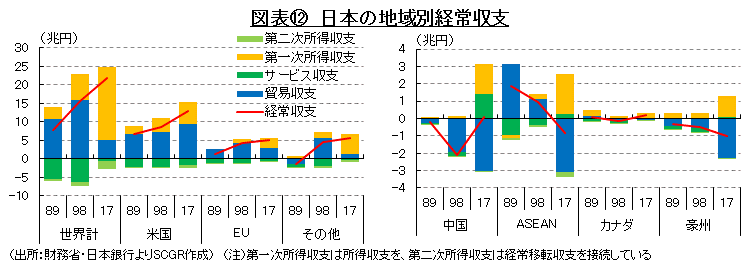
地域別にみると、対米国の経常収支では第一次所得収支の受取超が拡大している一方で、貿易収支の黒字が稼ぎ頭という構図が続いていた。それに対して、対EUや中国、ASEANの経常収支の構造は大きく変化してきた。対EU経常収支では、日本の経常黒字が続いている中で、多くが第一次所得収支の受取超になっている。対中国では、貿易赤字が拡大した一方で、旅行収支などを含むサービス収支と第一次所得収支の受取超が拡大しており、2017年には対中国経常収支が黒字だった。また、対ASEANでは、貿易収支が黒字から赤字に転じた一方で、第一次所得収支の受取超が拡大している。観光客数の増加による旅行収支や知的財産権等使用料収支の受け取りの増加などもあって、サービス収支も黒字になっている。
これらは、中国やASEANなどに日本企業が進出して、サプライチェーンを構築してきた結果であり、海外進出が海外現地法人からの直接投資収益や知的財産権等使用料の受け取りを拡大させた一面と、生産拠点の海外移転などによって輸入が増加したという変化を映している。
4. 多様化した企業の投資戦略
また、図表⑬のように、企業が積極的に投資してきたものとして、研究・開発(R&D)、コンピュータソフトウェア、鉱物探査・評価からなる「知的財産生産物」がある。全体の設備投資(含む知的財産生産物)が1996年の約160兆円をピークに2009年の約109兆円まで低下した期間でも、知的財産生産物への投資は拡大していた。比較可能な1994年と2017年を比べると、総固定資本形成(設備投資全体)は18兆円減ったのに対して、知的財産生産物は11兆円増えた。リーマンショック後には一旦減速したものの、その後回復し、過去最高額を更新するまでになった。企業の設備投資には、いくつかの局面で変化がみられた一方で、知的財産生産物にはリーマンショック後の落ち込みを除いて、大きな変動はみられない。言い換えれば、企業が一貫して知的財産への投資を拡大してきた姿が反映されていることになるだろう。
こうした背景には、国内工場の役割の変化があるのだろう。平成は、国内の低迷とともに、アジア新興国の成長の時代だった。海外進出の主な目的は当初、国内に比べて廉価な労働力を活用することであったものの、次第に現地市場での販売に移ってきた。なぜなら、アジア新興国の経済が成長するにつれて、賃金も上昇し、コスト競争力が低下した一方で、それは消費者の購買力の向上を意味しており、人口の増加もあって、販売市場としての魅力を高めてきたためだ。
そうした変化の中で、国内工場の役割は、高付加価値な部品や資本財の供給基地とともに、R&Dを行うマザー工場も兼ねるようになってきた。また、情報通信技術(ICT)が普及するにつれて、工場のスマート化も重要な戦略になってきたこともある。このように企業が、R&Dやソフトウェアなど知的財産への投資を重視してきた背景が確認できる。
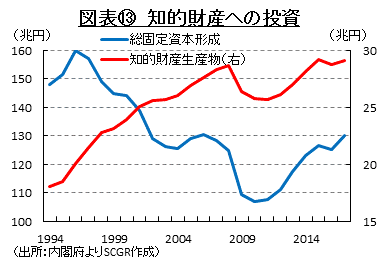
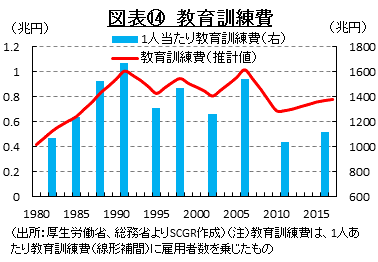
一方で、他の投資に比べて伸び悩んだものに、人への投資がある。図表⑭は、1人当たり教育訓練費と雇用者数から、教育訓練費総額を試算したものである。1人当たり教育訓練費をみると、バブル崩壊後に減少し、その後一旦持ち直したものの、金融危機、ITバブルを経て再び減少した。2000年代後半に向けて再びバブル期の水準をうかがう水準まで回復していたものの、リーマンショックを期に大幅に減少した。足もとにかけて、持ち直す動きがみられるものの、水準はかなり低いところにとどまっている。
1人当たり教育訓練費が伸び悩んだ原因として、企業業績があまり良くない状況では教育訓練費に回す余裕が十分になかったこと、非正規労働者比率が1989年2月の19.1%から2018年第1四半期の38.2%まで上昇しているように(総務省『労働力調査』)、人件費をかけないような企業経営に変化してきたことがあるだろう。
こうした中で、第4次産業革命など経済・社会が大きく変化しつつある。現在の景気回復局面では人数ベースでの人手不足が注目されている。その一方で、それらの新しい技術を使いこなす人材への需要が拡大しており、質の面での人手不足も生じている。また、先端技術の開発分野に加えて、その運用分野でも、数多くの人が新しい機械やシステムの導入に直面するため、教育訓練がますます求められるようになっている。将来の収益を生み出す源泉として、人もまた重要な要素であるため、人への投資をいかに進めていくのかが課題として残っている。
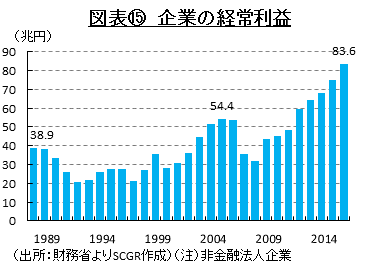
5. 次なる投資の機会へ
以上のように、平成の投資を振り返ると、多様性という一面がみえてくる。日本企業は、これまで国内設備投資には慎重な一方で、海外設備投資、直接投資、知的財産などへの投資には積極的な姿勢を崩していなかったといえる。もちろん、人への投資という課題は残っているものの、これまで企業は将来の収益源を模索して、投資を進めてきたのだろう。
その成果の一部は、企業収益の改善にあらわれている。図表⑮のように、2017年度の企業の経常利益は83.6兆円と、1989年度の38.9兆円、2006年度の54.4兆円を上回って過去最高を更新している。現在の企業業績の向上は、株主への配当を増やす一方で、緩やかながらも賃金を引き上げ、投資を拡大させながら、実現しているものである。これは、平成を通じて企業が多様な投資を行ってきたからこそ、実現した利益である。
今後の投資戦略という視点から考えると、国内の重要性も再認識される。日本経済・社会では、少子化・高齢化が進んでおり、人手不足も深刻化しているなど、課題が山積している。しかし、これらは遅かれ早かれ、欧州などの先進国やアジアの国々も直面する課題でもある。そのため、課題解決のためのビジネスを発展させることができれば、その需要は国内にとどまらない。いわば、日本は社会実験の場である。
また、日本の人口が減少するといっても、当面1億人という規模を維持する。しかも、経済は成熟しており、所得水準も高い。量的・質的な視点からみれば、世界の中で消費マーケットとしての存在感が損なわれるものではない。そうした日本を通じて、世界に応用できる次なる成長源を模索することが、重要な視点なのだろう。これらを踏まえると、日本企業が更なる成長を遂げるためには、次なる収益源の獲得に向けた投資が欠かせないと考えられる。
そして、平成が終わりを迎える今こそ、成長のための投資を拡大させる好機と言える。なぜなら、投資の原資となる企業収益は増加しており、投資余力も拡大しているからだ。外部環境も大きく変化しており、特に、日本経済・社会の関心が、第4次産業革命やデジタル革命など、次なる成長分野に向きはじめている。また、第4次産業革命など、変化のスピードが速まっている中で、中国などをはじめとした海外企業は、試行錯誤を繰り返しながら新たな領域に投資している。
そうした環境の中で、研究開発などを通じて次の収益源を探りながら、果敢に新しい事業機会に投資していくことが欠かせない。設備投資や海外投資など、どのような形態をとるにせよ、新しい事業機会に投資していくことの重要性を、平成という時代は示しているようだ。
<参考文献>
石崎寛憲・川本卓司(2006)「近年の製造業の設備投資増加について」日銀レビュー2006-J-17.
小川一夫・得津一郎(2002)『日本経済:実証分析のすすめ』有斐閣.
内閣府(2007)『経済財政白書(平成19年度)』
Petris, G.,(2010), "An R Package for Dynamic Linear Models," Journal of Statistical Software, Volume 36, Issue 12, pp.1-16.
以上
記事のご利用について:当記事は、住友商事グローバルリサーチ株式会社(以下、「当社」)が信頼できると判断した情報に基づいて作成しており、作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、当社及び住友商事グループは、その情報の正確性、完全性、信頼性、安全性等において、いかなる保証もいたしません。当記事は、情報提供を目的として作成されたものであり、投資その他何らかの行動を勧誘するものではありません。また、当記事は筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社及び住友商事グループの統一された見解ではありません。当記事の全部または一部を著作権法で認められる範囲を超えて無断で利用することはご遠慮ください。なお、当社は、予告なしに当記事の変更・削除等を行うことがあります。当サイト内の記事のご利用についての詳細は「サイトのご利用について」をご確認ください。
 レポート・コラム
レポート・コラム
 SCGRランキング
SCGRランキング
- 2025年7月4日(金)
日本国際平和構築委員会『7月研究会』に、当社シニアアナリスト 足立 正彦がパネリストとして登壇しました。 - 2025年6月27日(金)
日経QUICKニュース社の取材を受け、当社シニアエコノミスト 鈴木 将之のコメントが掲載されました。 - 2025年6月27日(金)
『日本経済新聞(電子版)』に、当社シニアエコノミスト 鈴木 将之のコメントが掲載されました。 - 2025年6月16日(月)
『時事通信』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行が寄稿しました。 - 2025年6月13日(金)
『日刊工業新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。

