世界景気の変調とドル円レート
2019年03月18日
住友商事グローバルリサーチ 経済部
鈴木 将之
概要
円が急騰して始まった2019年も、これまでのところドル円レートは安定的に推移してきた。その一方で、2018年の安定したドル円レートの背景にあった、堅調な米国景気と米中貿易戦争などのリスクとの綱引きという関係が崩れつつあり、実体経済を巡る先行き懸念がますます大きくなっている。主要国の景気減速など、経済の局面が変わったとみられ、各国の金融政策当局の姿勢は引き締めから緩和的な方向に舵を切りつつある。景気減速の中で、米中貿易戦争に続いて、日米・米欧協議も控えているなど、先行き不透明感が払しょくできず、円高リスクを警戒せざるを得ない中で、為替レートの先行きが読み難くなっている。
1. 世界景気の局面変化
日本市場が休場だった1月3日にドル円レートが1ドル=108円台前半から104円10銭まで急騰するショックで幕を開けた2019年は、波乱への懸念があったものの、足もとにかけて為替市場は比較的落ち着いて推移してきた。図表①のように、ドル円、ユーロ円レートともに2018年末の円高から円安方向に回復する動きが緩やかに続いており、円高傾向が修正されつつあるようにみえる。
その一方で、実体経済の先行き懸念は、年初よりも大きくなっている。2018年秋には、IMFの世界経済見通しが下方修正され、景気減速への市場の関心が高まった。米中貿易戦争の激化や英国のEU離脱交渉など懸念材料が山積し、先行きが読みにくい中、企業が慎重な姿勢をとったことで設備投資を抑制させたり、2018年前半に中国が不良債権の削減を狙って「影の銀行」規制を強めたりした影響が、経済成長の鈍化として現れはじめた。
実際、図表②のように、中国の経済成長率は2018年第4四半期(以下Q4)に前期比+1.5%(前期比年率+6.1%)となり、Q2(+1.7%)やQ3(+1.6%)に比べて緩やかに減速している。また、ユーロ圏の経済成長率は2018年Q4に前期比+0.2%(前期比年率+0.8%)となり、Q3(+0.2%)から伸び率は変わらず、2018年は成長ペースの減速が目立つ結果となった。特に、2018年下半期に景気後退局面入りしたイタリアに加えて、Q3にマイナス成長となったドイツがQ4は0%成長と回復が不十分だった。
一方、底堅さが目立っていた米国も、決して楽観視できない状況になりつつある。2018年Q4の経済成長率は前期比年率+2.6%と、巡航速度といわれる潜在成長率を上回った。しかし、Q2(+4.2%)をピークに米国経済の成長は減速している。先行きについても、減税効果の剥落に加えて、予算協議の結果次第では、米国経済に「財政の崖」が出現する恐れもあるなど、下振れリスクがくすぶっている。
また、世界景気の減速感が強まる中では、日本経済もその影響を受けざるを得ない。経済成長率はQ4に前期比年率+1.9%と潜在成長率を上回る成長になったものの、Q3が▲2.4%のマイナス成長であった反動でかさ上げされている。2018年通年では前年比+0.8%と、潜在成長率並みからやや下回る程度の成長を維持できたものの、前期比成長率はQ1とQ3がマイナス、Q2とQ4がプラスと、一進一退の中で結果的に成長したというのが実際のところだった。
このように、日米欧中では経済成長が続いているものの、成長ペースの減速が目立っている。また、今後更なる鈍化が懸念されている。こうした先行き懸念が実体経済の下振れをもたらす局面へと変化しつつある中では、為替レートの先行きも読み難くなっている。
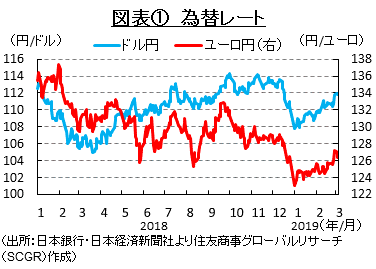
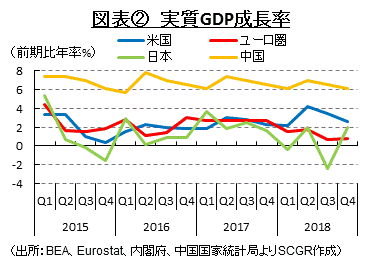
2. 金融政策のスタンスの変化
このように局面が変わりつつある中で、各国の金融政策当局の姿勢にも変化がみられるようになった。
1月下旬(1/29~30)のFOMCでは、「米経済は良好であり、労働市場の動向は力強い」という現状判断を行いながらも、利上げについては「『忍耐強い』姿勢が正当化される」と、事実上利上げの先送りを表明した。また、その後のパウエル議長の発言やFOMC議事要旨からは、保有資産の縮小を年内に終了する方針も明らかになっている。つまり、当初想定されていたよりも早く、金融引き締めサイクルが終わる可能性が高まっている。
また、3月7日のECB理事会後、政策金利を据え置く時期について、従来の「少なくとも2019年夏まで」から「2019年末まで」に延長すること、新しい貸出条件付き長期資金供給オペ(TLTRO3)を9月から実施することを発表した。この背景には、2019年の経済成長率の見通しが前回の1.7%から1.1%に下方修正されるなど、景気回復の遅れが物価上昇に悪影響を及ぼしているとの認識がある。また、2016~17年に実施されたTLTRO2の満期が2020年6月に近づいており、円滑な資金調達を下支えする目的もあった。イタリアの金融機関などの資金繰りに不安感が残っており、先手を打たねばならないほど、金融環境は脆弱な状況にあることを表している。
中国では、構造改革から景気下支えに政策の舵が切られている。2018年秋から所得税減税や増値税(付加価値税)減税、インフラ投資などの経済対策が発表されている。また、金融政策の姿勢も「穏健」と、「中立」という表現が削除されて、より緩和的なものになっている。こうした背景には、2018年まで続けてきた「影の銀行」や不良債権対策によって、民間中小企業などへの貸し出しに資金が回らなくなったことで、想定以上に景気に下押し圧力がかかったことがある。その状況下、米国との貿易戦争が激化している。そのため、景気の減速感が強まり、2019年1月には、預金準備率を1%ポイント引き下げるなど、金融緩和策に取り組みはじめている。
このように、足もとにかけて、主要国の金融政策が再び引き締めから緩和方向に変化しつつあり、実体経済の動向と合わせて、為替レートに影響を及ぼしている。
3. 為替レートの動向
為替レートが今後どのように変化していくのかを考える上で、足もとまでの動向を確認しておく。
まず、非伝統的金融政策という視点からマネタリーベースをみると、図表③のように、米国は減少、欧州は横ばい圏、日本は増加ペースの鈍化という状況である。これは、これまで米国が金融政策の引き締め、欧州は緩和拡大の停止、日本は緩和継続の状況を表している。
米国のFRBは保有資産の縮小を進めており、ピークの約4.5兆ドルから足もとまで約0.5兆ドル程度縮小している。年末までに縮小を終了する予定になっているものの、今後さらに約0.5兆ドル程度削減するとみられている。
また、ECBは2018年末に資産買い入れプログラムを終了した。現在は、国債などの償還分について再投資を行い、保有残高を維持している。緩和というアクセルを踏み込むことをやめたものの、アクセル自体は踏み続けている状態にある。
一方、日本銀行は国債買い入れペースが一時より鈍化しているとはいえ、欧米とは異なり、買い入れを継続している。そのため、日本だけが金融緩和を加速させている状態にある。
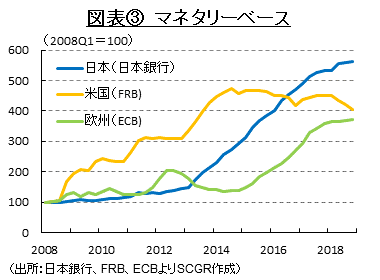
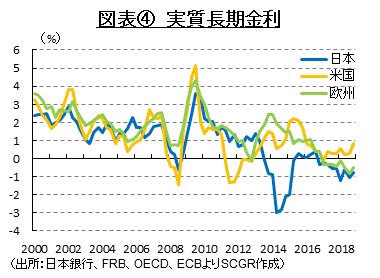
金融緩和が実体経済に及ぼしている影響を考える上で、図表④のように、実質長期金利の動きが参考になる。この実質長期金利は、消費者物価上昇率で名目長期金利を調整したものである。
米国の実質長期金利はプラス圏を推移する一方で、日欧はマイナス圏に沈んでいるという対比が鮮明になっている。米国ではこれまで進めてきた利上げによって名目長期金利が上昇した結果、実質長期金利も上昇してきた。それに対して、欧州や日本では、足もとでは名目長期金利自体がマイナス圏まで沈んだままになっている。
実体経済への影響を考える上では、景気を過熱も冷やしもしない「中立金利(自然利子率)」と実質金利の比較が注目される。中立金利について、潜在成長率を代理変数として用いれば、中立金利(米国約2%、欧州約1.5%、日本約1%)よりも、実質長期金利の方が低いため、各国とも緩和的な状況にあるといえる。こうした中で注意が必要なのは、FRBの保有資産が縮小されており、金利を押し下げてきた効果が剥落しつつあることだ。その上、物価上昇率も足もとにかけて鈍化しており、政策金利を据え置いても潜在的に実質長期金利への上昇圧力が高まっている。そのため、以前よりも実質長期金利の上昇が意識されやすい状況になりつつある。
図表⑤のように、ドル円レートの変化率(前年同月比)を要因分解してみた。2018年Q4の状況をみると、円安・ドル高圧力として、量的な金融緩和を進めていることを反映するマネタリーベース比要因、米国の継続的な利上げによって拡大した金利差を表す実質金利差要因があげられる。その一方で、日本の経常黒字によって拡大した対外資産に対して必要とされるリスクプレミアム要因が円高・ドル安圧力になっている。これらの要因を合わせてみると、2018年末時点でやや円高・ドル安圧力になっていた。12月になって、そうした状況に米中貿易戦争、米国の一部政府機関の閉鎖などのリスク要因が重なり、円高が進んだと考えられる。
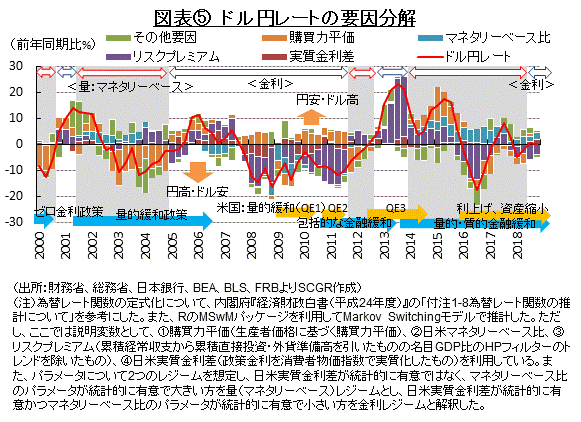
同様に、図表⑥のように、ユーロドルについても要因分解を行った。想定した2つのレジームにおいて、金融政策とともに、ユーロドルのトレンドも変化している。ドル円とは異なり、ここではユーロドルの説明変数としてトレンドを追加している。このトレンドは、購買力平価やマネタリーベース比などの要因で説明しきれない部分のうち、ユーロ高ドル安などのトレンドの変化を表している。この部分には、ユーロという単一通貨が用いられている19か国において、経済成長率や物価上昇率などをはじめとした経済環境の相違がユーロドルに及ぼしている影響が含まれていると考えられる。また、2008年以降のユーロ安ドル高トレンドが継続している期間には、欧州債務危機が含まれており、ユーロの脆弱性が反映されているとみられる。
リーマンショック後、ECBは利下げを行っていた一方で、FRBが量的緩和第1弾(QE1)を開始しており、金融政策において量的な側面が注目されるようになっていたと解釈できる。この時期、金利とともに「マネタリーベースという量」が、為替レートの変動において説明力を増していた。
また、2016年になると、再び「金利」が注目されるレジームに変化した。2015年12月に、すでに量的緩和第3弾(QE3)を終えていたFRBが利上げを始めたことに加えて、同月にECBが預金ファシリティ金利を▲0.3%に引き下げたことなどから、市場の目が再び金利に向かいはじめたことを表していると考えられる。
足もとにかけても、金利が重要なレジームになっている。ECBは資産買い入れプログラムについて2017年4月から月額購入額を減らしはじめ、2018年12月末で終了させた。その他の構造的な側面からは、欧州の経常黒字が拡大していることも、ユーロ高圧力を生み出す素地になっている。
2018年Q4のユーロドルの変動要因に注目すると、米国が利上げを進めてきたこともあって、米欧の実質金利差が拡大し、ユーロ安・ドル高圧力になっていた。その他のユーロ安・ドル高要因として、トレンドから下振れしていた累積経常収支(リスクプレミアム要因)もあった。2019年になると、FRBの利上げ打ち止めやECBの2020年以降の利上げ先送りなどもあって、先行き不透明感が漂う経済実体を踏まえた金融政策という点から、金利動向が読み難くなっている。
以上のような2018年Q4の状況を踏まえて、今後の為替レートは当面、ドル円レートで1ドル=104~114円、ユーロドルで1ユーロ=1.10~1.24ドルのレンジで推移すると想定される。ドル円について、日本では、足もとで景気の足踏み感が強まるものの、景気後退には陥らず、経済対策や駆け込み需要などもあって、消費税率引き上げまでは景気が底堅く推移すると想定される。その一方で、成長トレンドが継続するものの、減税効果の剥落に起因する今後の米景気減速や、夏場にかけての債務上限引き上げの難航などが米国経済の下押し圧力として注目される。それらがリスクとして大きくなれば、投機筋などの円売り・ドル買いのポジションが調整されて、円高が進む恐れがある。
ユーロ圏では、欧州景気の先行きが注目される。イタリア経済が景気後退局面から回復できるのか、またドイツ経済が復調するのかが、欧州景気にとって重要な点だろう。イタリア経済には金融機関の脆弱性に加えて、財政赤字削減など構造的な問題が残っている。ドイツでは、米中貿易戦争のあおりを受けた輸出や受注などが回復するのかが注目される。米中貿易戦争などが一段落すると、米欧間の貿易交渉が本格化する。そこで、仮に、欧州の自動車輸出について数量規制などが課されれば、ドイツ経済の成長にとって深刻な条件になりかねないなど、懸念材料は尽きない。
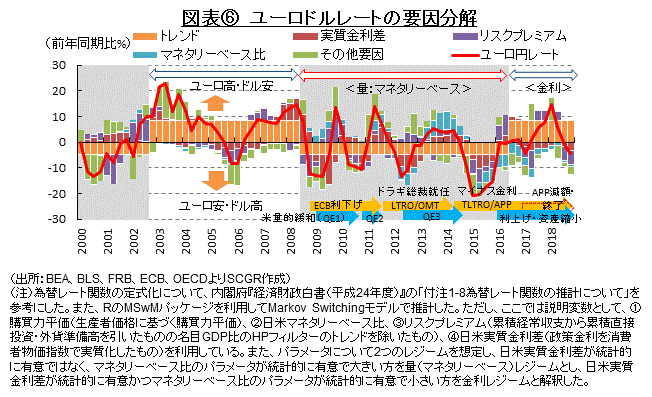
4. 市場はリスク回避的な姿勢に
世界景気の減速懸念が高まる中で、米中貿易戦争など先行き不透明感がさらに高まっている中では、市場はリスク回避的な姿勢になるだろう。
2018年の安定したドル円レートの背景にあった、堅調な米国景気と米中貿易戦争などのリスクとの綱引きという関係が崩れつつあり、実体経済を巡る先行き懸念がますます大きくなっている。主要国の景気減速など、経済の局面が変わったとみられ、各国の金融政策当局の姿勢は引き締めから緩和的な方向に舵を切りつつある。景気減速の中で、米中貿易戦争に続いて、日米・米欧協議も控えているなど、先行き不透明感が払しょくできず、円高リスクを警戒せざるを得ない中で、為替レートの先行きが読み難くなっている。
以上
記事のご利用について:当記事は、住友商事グローバルリサーチ株式会社(以下、「当社」)が信頼できると判断した情報に基づいて作成しており、作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、当社及び住友商事グループは、その情報の正確性、完全性、信頼性、安全性等において、いかなる保証もいたしません。当記事は、情報提供を目的として作成されたものであり、投資その他何らかの行動を勧誘するものではありません。また、当記事は筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社及び住友商事グループの統一された見解ではありません。当記事の全部または一部を著作権法で認められる範囲を超えて無断で利用することはご遠慮ください。なお、当社は、予告なしに当記事の変更・削除等を行うことがあります。当サイト内の記事のご利用についての詳細は「サイトのご利用について」をご確認ください。
 レポート・コラム
レポート・コラム
 SCGRランキング
SCGRランキング
- 2025年6月27日(金)
日経QUICKニュース社の取材を受け、当社シニアエコノミスト 鈴木 将之のコメントが掲載されました。 - 2025年6月27日(金)
『日本経済新聞(電子版)』に、当社シニアエコノミスト 鈴木 将之のコメントが掲載されました。 - 2025年6月16日(月)
『時事通信』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行が寄稿しました。 - 2025年6月13日(金)
『日刊工業新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2025年6月13日(金)
『日刊工業新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。

