不確実な世界で動けないドル円相場
調査レポート
2019年12月05日
住友商事グローバルリサーチ 経済部
鈴木 将之
概要
これまでのところ、ドル円相場は例年になく動いていない。その理由として、日米金利差が縮小していること、ドルと円が他通貨に対して買われていることに加えて、米中貿易戦争などの先行きが読めないという不確実性の高まりで、市場でも様子見ムードが強まっていることが考えられる。こうした中で、輸出需要が減退して製造業の景況感が悪化しても、底堅い雇用・所得環境に支えられた個人消費などによって、緩やかな成長トレンドは維持できるという見通しが、不確実な世界経済を下支えしている。米中貿易戦争などからの不確実性の中で、こうしたシナリオが維持されている間は、為替相場が動かない状況が続くのかもしれない。
1. ドル円動かず
図表①のように、ドル円相場は例年になく動いていない。『QUICK月次調査<外為>』(2019年11月調査)の問7は、なぜドル円相場が動かないのかを問う設問だった(問7(2)の質問文は「円相場の値幅縮小は何が最大の原因だと考えますか」)。一般的には、なぜドル円相場が動くのか、その要因は何かが関心事になる傾向がある。しかし、2019年は2018年以上にドル円相場が動いておらず、むしろその理由が注目されている。ちなみに、調査結果によると、「金利差の縮小」(43%)という回答が最も多く、それに「リスク回避先として円とドルが同時に選ばれるようになった」(31%)が続いた。
2019年を振り返ると、米中貿易戦争が大きな注目を集めてきた。世界1位、2位の両経済大国が貿易交渉で激突し、制裁関税を互いにかけあうなど、その悪影響は世界中に広がった。中国の経済成長が減速しているところに、米中貿易戦争の悪影響が重なったことで、影響がさらに大きくなった。
しかも、先行きが読めないという不確実性が大きいことが、企業の行動を慎重にさせた。図表②のように、世界の経済不確実性指数は2018年以降、上昇トレンドにあるため、不確実性が高まっている可能性が高い。100年に一度といわれるリーマンショック後の世界同時不況時には、昔のこととはいえ、世界恐慌が引き合いに出されるなど、参考になる先行事例があった。しかも、各国・地域の政府・金融政策当局は危機を乗り切るために、事態を改善させようと取り組んでいた。
しかし、現在の状況は異なっている。米中両国は報復関税合戦状態に陥っており、事態を収束させようと交渉しているものの、その落としどころは見えていない。米国は対中貿易赤字を減らそうという考えに立って行動している一面がある一方、中国製造2025の抑え込みや米企業などの知的財産権保護を目的とした覇権争いの様相をも帯びている。このため、適当な先行事例がなく、また事態を改善させる方向に進むか否かもよくわからない結果、不確実性が高まっている。
こうした中で、ドル円相場は年初からの値幅が10円にも満たず、過去最少の値幅になりそうなほど動いていない。2000年代半ばごろからの傾向のように、リスクオフの円買いが進んでも不思議ではなかった。しかし、先行きが読める、もしくは各シナリオの発生確率が想定できるリスクとは異なり、確率自体がわからない不確実性が広がる中では、状況は異なったようだ。
企業の事業計画という視点からみれば、ドル円相場の変動が小さいことで為替リスクが小さくなるなど、望ましい一面がある。その一方で、これまで動かなかった反動で今後大きく動くのか、それとも当面変動が小さいままで推移するのかという点が注目されるようになっている。そこで、以下では、経済のファンダメンタルズの動向などに注目しながら、為替レートの変動の背景について考えてみる。
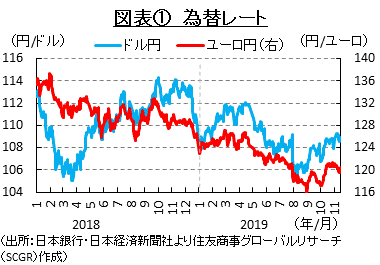
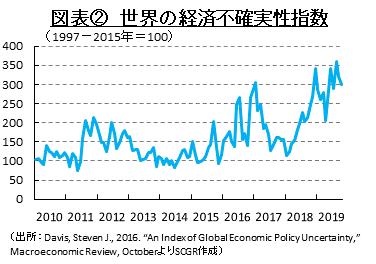
2. 緩和方向に舵を切る金融政策
2019年半ば以降、各国の中央銀行は金融緩和に舵を切っている。それまでは、図表③の欧米のマネタリーベースの動きに表れているように、緩やかな金融引き締め、もしくは緩和の停止を行っており、金融政策の非伝統的緩和から脱却させようとしていた。
しかし、状況は大きく変わった。10月末の連邦公開市場委員会(FOMC)まで3会合連続で利下げが実施された。FRB議長がグリーンスパン氏だった1990年代と同じ合計0.75%ptの利下げであり、「予防的」なものだった。10月末のFOMC以降、パウエルFRB議長は予防的な利下げは一旦終了し、経済の動きを見極める姿勢を鮮明にしている。また、クラリダ、クオールズ両副議長もパウエル議長と歩調を合わせた発言を行っている。
一方で、9月の欧州中央銀行(ECB)理事会後、ドラギ総裁は金融緩和を発表した。中銀貸出金利を▲0.5%に引き下げ、資産買い入れプログラムを11月から月額200億ユーロ規模で再開し、貸出条件付き長期資金供給オペ(TLTRO3)の条件を緩和、中銀当座預金に階層化構造を導入するなど、市場の予想を上回る金融緩和であった。それ以上に市場の予想と異なったのは、ECB理事会後の各国中銀総裁の発言だった。オランダやドイツなどの中銀総裁は利下げには同意したものの、資産買い入れプログラムの再開には反対し、ECB理事会後に資産買い入れプログラム再開を公然と批判した。これによって、ECB内が一枚岩ではないことが明らかになり、それ自体が新たなリスクとして市場で認識されるようになった。
欧米で金融緩和が実施された背景には、景気減速懸念があった。図表④のように、各主要国・地域の実質GDP成長率(経済成長率)は減速していた。また、国際通貨基金(IMF)の「世界経済見通し」(2019年10月)でも下方修正が続いており、先行きへの懸念が払しょくできない状況が続いている。
しかし、減速といっても、金融緩和するほどの減速とは言えないことも事実だろう。2019年第3四半期(Q3)の米国の実質GDP成長率は前期比年率+1.9%と、巡航速度とされる潜在成長率並みといえる。ユーロ圏は前期比年率+0.9%の成長と潜在成長率を下回るものの、26四半期連続でプラス成長を維持しており、インフレ目標を下回るとはいえ、デフレ懸念は今のところ大きくない。
日米欧の金融政策では、政策金利のフォワードガイダンスという文言の修正にとどまった日本銀行の対応の方が、予防的な金融緩和に踏み切った欧米に比べて、適切な対応にもみえる。その一方で、米中貿易戦争という不確実性の点からみると、米国はその当事国であり、欧州は中国向け輸出が不調なドイツの成長が減速しているなど、悪影響への懸念がより高かったとも考えられる。
また、今回の利下げによって、新興国での利下げも相次いでいることが注目される。景気が減速していた中で、自国通貨安を引き起こさずに金利を下げて、景気下支えが図れるためだ。しかし、本来取り組むべき不良債権処理などの問題を先送りしていることも事実である。そのため、新興国通貨に比べて安全通貨とされている米国ドルや日本円に対して潜在的な新興国通貨安の要因になっており、ドル円相場を動きにくくしている可能性がある。
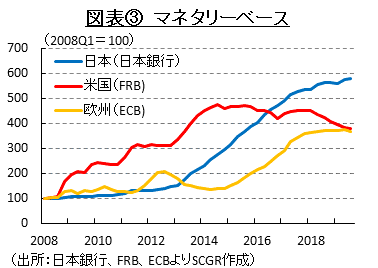
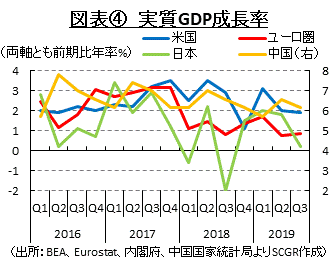
3. 経済のファンダメンタルズから乖離するドル円相場
足元のドル円相場の動きを把握するために、経済のファンダメンタルズに注目して要因分解を行った。図表⑤のように、足元にかけて、日本の金融緩和政策の継続や、物価動向を反映した購買力平価要因などから、円安・ドル高圧力がかかりやすい状況といえる。
しかし、実際のドル円相場の動きは、2018年に比べてむしろ円高方向に振れていた。しかも、その経済のファンダメンタルズで説明できるドル円相場の動きと実際の動きの乖離が、2019年に次第に大きくなっていた。言い換えると、経済のファンダメンタルズ要因は円安・ドル高方向にあった一方で、それを相殺するような要因があったために、ドル円相場は大きく動かなかったことになる。
そこで、その他要因が円高・ドル安圧力になっている背景について考えてみた。米中貿易戦争などの不確実性の高まりを踏まえると、図表⑥のように、その他要因を除いた理論値(経済のファンダメンタルズなどによって説明できるドル円レートの動き)と実績値の乖離と同じような動きをするものとして、投資家・投機筋(非商業部門)の動きと日本の政策不確実性指数が挙げられる。
まず、政策不確実性指数は、米中貿易戦争の激化に歩調を合わせるように2018年以降上昇トレンドにあり、不確実性が高まっていたことがうかがえる。次に、投資家・投機筋の取引動向をみると、2018年末から円売り・ドル買いポジションを解消して、9月末にかけて円買い・ドル売りを進めていた。そのため、ドル円レートには、円高・ドル安圧力がかかっていたと考えられる。これらから、米中貿易戦争などによって、先行きの不確実性が高まった中で生じた為替市場の調整が円高・ドル安圧力になったと解釈できる。
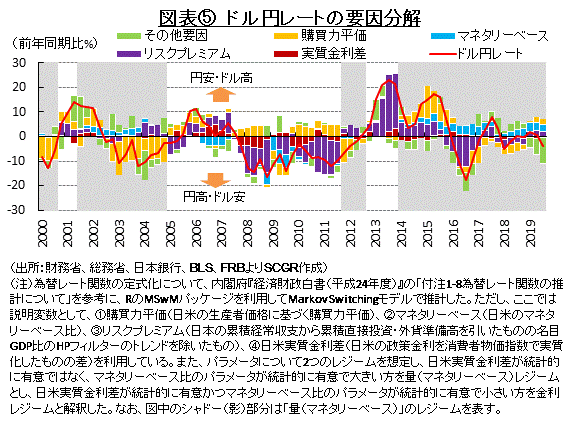
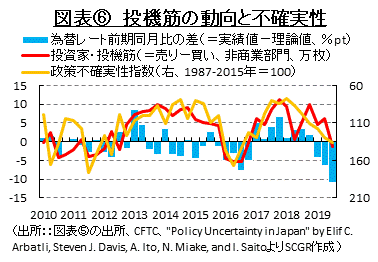
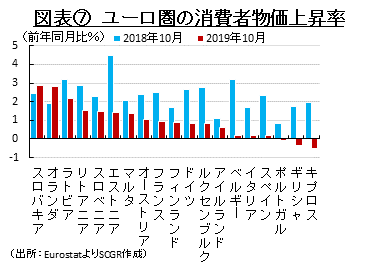
続いて、同じようにユーロドルレートについて要因分解を行ってみた。まず、ユーロ圏の経済状況についてみると、ユーロ圏各国の置かれた状況が異なることがわかる。9月に決まった資産買い入れプログラムの再開について、意見が分かれた一因は経済環境の相違にあると考えられる。
図表⑦のように、1年前の2018年10月と、足元の2019年10月の消費者物価上昇率を比べてみた。これをみると、ばらつきがこの1年で拡大している。1年前には、他国に比べて消費者物価上昇率が低いアイルランドやポルトガルがあったものの、総じて2%前後の国が多かった。
しかし、足元では、スロバキアやオランダなど3%弱の国から、ギリシャやキプロスなどマイナスに転じている国まで、その幅は広い。こうした環境において、ECBが打てる金融政策は1通りしかない。その影響は各国によってかなり異なることになるため、緩和に反対する国と賛成する国とに意見が割れる結果になったのだろう。
こうした各国の経済環境の相違を踏まえると、ユーロドルの動きを考える上で、ユーロ圏平均の経済のファンダメンタルズには、各国の大きな相違が含まれていると想像できる。足元にかけて、このばらつきがユーロドルの変動にも悪影響を及ぼしている可能性がある。
図表⑧のように、2018年以降になってから、経済ファンダメンタルズ要因以上に、投機筋の動きに影響を受けるようになっている。ユーロ圏にとっては、米中貿易戦争の悪影響やドイツ経済の減速に加えて、英国のEU離脱問題、なかなか進んでいない米欧貿易協議などの不確実性も存在している。そのため、投機筋のポジション調整などがユーロドルレートに影響を及ぼしていると考えられる。
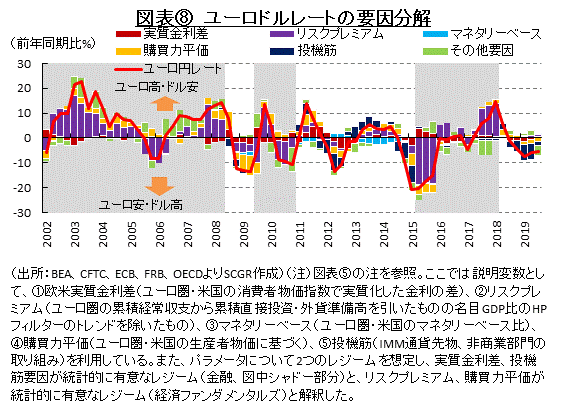
4. 当面、動けない状況が継続か
先行きが読めない不確実性が広がる中、企業は設備投資に慎重な姿勢になっており、投機筋・投資家はポジションを調整して積極的な動きを控えているなど、経済全体が様子見姿勢になっているようだ。こうした経済環境を踏まえると、為替相場も当面横ばい圏(1ドル=104~114円、1ユーロ=1.06~1.16ドル)で推移すると想定される。
先行きについて、米中貿易戦争がどのような決着を迎えるのかが最も注目される。また、米中の交渉が終わっても、次は米欧貿易協議、日米貿易交渉の第2弾などが控えているなど、日米欧を取り巻く不確実性は継続するだろう。
世界経済が減速している中で、雇用・所得環境の底堅さに基づく個人消費が下支え役となって、成長トレンドが維持されるというシナリオが描かれている国が多い。輸出需要が減退して、製造業の景況感が悪化しても、底堅い雇用・所得環境を背景とした個人消費などによって、緩やかな成長トレンドは維持できるという見通しが、不確実な世界経済を下支えしている。米中貿易戦争などからの不確実性の中で、こうしたシナリオが維持されている間は、為替相場が動かない状況が続くのかもしれない。
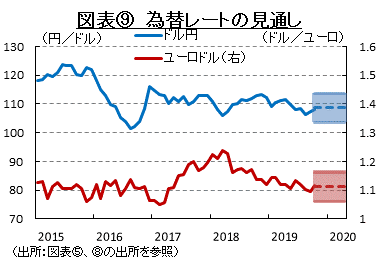
以上
記事のご利用について:当記事は、住友商事グローバルリサーチ株式会社(以下、「当社」)が信頼できると判断した情報に基づいて作成しており、作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、当社及び住友商事グループは、その情報の正確性、完全性、信頼性、安全性等において、いかなる保証もいたしません。当記事は、情報提供を目的として作成されたものであり、投資その他何らかの行動を勧誘するものではありません。また、当記事は筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社及び住友商事グループの統一された見解ではありません。当記事の全部または一部を著作権法で認められる範囲を超えて無断で利用することはご遠慮ください。なお、当社は、予告なしに当記事の変更・削除等を行うことがあります。当サイト内の記事のご利用についての詳細は「サイトのご利用について」をご確認ください。
 レポート・コラム
レポート・コラム
 SCGRランキング
SCGRランキング
- 2025年7月10日(木)
19:00~、NHK『NHKニュース7』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行へのインタビューが放映されました。 - 2025年7月4日(金)
日本国際平和構築委員会『7月研究会』に、当社シニアアナリスト 足立 正彦がパネリストとして登壇しました。 - 2025年6月27日(金)
日経QUICKニュース社の取材を受け、当社シニアエコノミスト 鈴木 将之のコメントが掲載されました。 - 2025年6月27日(金)
『日本経済新聞(電子版)』に、当社シニアエコノミスト 鈴木 将之のコメントが掲載されました。 - 2025年6月22日(日)
雑誌『経済界』2025年8月号に、米州住友商事会社ワシントン事務所調査部長 渡辺 亮司が寄稿しました。

